慢性閉塞性肺疾患(COPD)
更新日:2024年9月9日
COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは
COPDは肺の生活習慣病とも言われ、主にたばこの煙など有害物質が含まれる空気を長期間にわたって吸い込むことで発症します。
有害物質の刺激によって空気のとおり道である気管支や酸素を取り込む働きをする肺胞に炎症が起こり、肺の機能に障害が生じる進行性の疾患です。悪化すると、咳や痰、息切れが強くなり生活に支障をきたします。
日本では約530万人を超える患者がいると言われていますが、適切な治療を受けているのは36万人ほどとされています。
原因と症状
最大の原因は喫煙で、受動喫煙も発症の原因となります。
気管支の組織が炎症を起こし、痰が溜まることで空気が通りにくくなり、肺胞が破壊されて酸素をうまく取り込めなくなります。
気管が炎症を起こすと咳や痰などの症状が慢性的にみられるようになります。
初期は無症状ですが、息切れなどを自覚したところには病気がかなり進行していることが多いです。また。一度壊れてしまった肺胞を元に戻すことはできません。
診断
診断には「スパイロメーター」という機器で呼吸機能検査を行います。これは、思い切り呼吸をしたときの呼吸効率を測定するものです。
まずは禁煙
一度低下した肺の機能回復は困難ですが、禁煙と薬物治療によって悪化を防ぎ、生活をスムーズにすることができます。
薬物療法には気管支を広げて呼吸を楽にする気管拡張薬(吸入薬、張り薬、内服薬)があり、重症者には酸素療法で呼吸をサポートしいます。
呼吸をするだけでも身体に負担がかかりやすい体力の消耗が激しいCOPDにとって感染症は大敵です。
手洗いや予防接種などで予防に心がけましょう。
たばこを吸っている方は一度、下記のCOPD質問票でチェックしてみましょう。

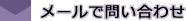
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。