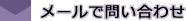国民健康保険‐限度額適用認定証について
更新日:2025年9月2日
限度額適用認定証について
医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、医療機関の窓口に提示していただくと、その医療機関での一月内での窓口負担が、支払限度額までで止まるようになります。
※保険適用外の治療や差額ベッド代、食事代などは、支払限度額の対象外となります。
※70歳未満のかたは、同一医療機関でも、入院、外来、歯科は別々の計算となり、合算できません。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の事前申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※医療機関によっては、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示を求められる場合があります。
※住民税非課税世帯のかたで、90日を超える入院(過去12か月の入院日数)で食事療養費の支給を受ける時は、マイナ保険証を利用されているかたでも、別途窓口での申請が必要になります。
まずは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しましょう。 厚生労働省HP
限度額適用認定証等の交付を受けるには
・必要なもの
1.来庁者の本人確認ができる書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳
など顔写真付きの書類
2.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
※別世帯にお住まいのかたが申請に来られる場合は、委任状もお持ちください。
また、交付申請の要否、認定証の種類については、下記の表をご参照ください。
| 年齢 | 課税・非課税 | 市役所窓口での手続き | 医療機関窓口で | |
| 70歳以上 75歳未満 |
課税世帯 | 課税所得690万円以上 | 必要なし [資格確認証兼]高齢受給者証で対応 |
[資格確認証兼]高齢受給者証 を提示する |
| 課税所得380万円以上 | 限度額適用認定証の 交付申請が必要 |
限度額適用認定証を提示する | ||
| 課税所得145万円以上 | ||||
| 一般 | 必要なし [資格確認証兼]高齢受給者証で対応 |
[資格確認証兼]高齢受給者証 を提示する |
||
| 非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額 減額認定証の交付申請が必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 を提示する |
||
| 70歳未満 | 課税世帯 | 限度額適用認定証 の交付申請が必要 |
限度額認定証 を提示する |
|
| 非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額 減額認定証の交付申請が必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 を提示する |
||
所得区分に応じた自己負担限度額はこちら → 高額療養費について
特定疾病療養受療証とは
厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、人工腎臓を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、特定疾病療養受療証を病院窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額は年齢を問わず10,000円までとなります。
注:人工透析を要する70歳未満の上位所得者(旧ただし書き所得600万円超の方)については、自己負担限度額は20,000円です。
入院時食事療養費・生活療養費の支給
入院したときの食事代・居住費は、標準負担額だけを自己負担していただき、残りは国保が負担します。
※住民税非課税世帯のかたは、食事代が減額されます。また、住民税非課税世帯のかたで入院日数が90日を超えるとさらに減額されます。(長期該当)
入院時食事代の標準負担額(一食あたりの自己負担額)
| 一般(下記以外のかた) | 1食510円 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 90日までの入院 |
注:1食240円 |
| 住民税非課税世帯 90日を越える入院 |
注:1食190円 |
| 70歳以上で低所得者Iのかた | 注:1食110円 |
注:「標準負担額減額認定証」(申請により交付)などの提示が必要です。
※90日を超えた場合は長期該当の申請が必要です。
食事・居住費の標準負担額(自己負担額)
療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。
| 区分 | 医療の必要性の低い者 (医療区分1) |
医療の必要性の高い者 (医療区分2・3) |
||
| 一食の食費 | 一日の居住費 | 一食の食費 | 一日の居住費 | |
| 一般・現役並み所得者 | 510円(注3) | 370円 | 510円 | 370円 |
| 低所得者II | 240円 | 240円(注4) | ||
| 低所得者I(注1) | 140円 | 110円 | ||
| 低所得者I(注2) | 110円 | 負担なし | 110円 | 負担なし |
(注1)年金受給額80万円以下
(注2)老齢福祉年金受給者
(注3)保険医療機関の施設基準等により、470円となる場合もあります。
(注4)90日を超える入院で190円