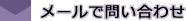平成29年度名張市教育委員会第11回定例会会議録(平成30年2月7日開催)
更新日:2018年9月7日
開催場所など
2.開催日時 平成30年2月7日(水曜日) 午後1時15分から午後4時45分
3.出席者 上島教育長、福田委員、瀧永委員、川原委員、辻委員
4.欠席者 なし
5.事務局 高嶋教育次長、草合教育改革担当理事、合田スポーツ推進担当監兼国体準備室長、内匠教育総務室長、中森学校教育室長、上谷教育センター長、西山文化生涯学習室長、宮前図書館長、田中市民スポーツ室長、福本教育総務室教育総務係長(書記)
6.議事概要 下記のとおり
(教育長)皆さん、こんにちは第11回の定例教育委員会を始めたいと思います。議事に入る前に本日の会議の公開についてお諮りを致したいと思います。本日の事項中、『報告第1号臨時代理した事件』また、『第2号』も同じでありますけれども、『平成29年度3月補正予算の要求』と、『平成30年度当初予算要求の承認について』の項、さらにその他の項の『(3)義務就学者の就学校の変更について』ならびに『(4)児童生徒の問題行動』につきましては、名張市教育委員会会議規則第8条の規定によりまして、非公開とすることを提案したいと思います。委員の皆様方におかれましては、この件についてご異議ございませんか。
(委員)異議なし。
(教育長)ありがとうございます。ご異議がないようでございますので、これらの案件につきましては非公開とし、本日の会議をこれより進行することと致します。なお、本日は学校教育室長が2時30分から別の公務がありますので、一部事項書の順序を入れ替えて、学校教育室所管の事項から順に議事を進めさせていただきたいと思います。まずその他の項の『児童生徒の問題行動(12月分)』につきまして、事務局から説明をお願いします。
議事(3その他)
(4) 児童生徒の問題行動について(12月分)【非公開】
(5) 平成29年度 学校満足度調査(Q-U)結果について
(事務局 説明)
(教育長)ありがとうございました。今の件につきまして委員の皆様方のほうから何かご質問ご意見ございましたらお願いいたします。
(委員)2点お願いします。今、事務局のご説明の中で要支援群という言葉が出てきたんですが、この2枚目のこの割合の中でみると、要支援群というのはどの色の部分にあたるのか教えて頂きたいと思います。それと、もう1点。低学年については満足度と言ってもなかなか子どもたちもアンケートに答えにくい部分もあるのかなと思うんですが、どういう様な質問で満足度をはかられているのか簡単に教えて頂けたらと思います。以上2点お願い致します。
(教育長)それでは、お答えのほう、いかがですか。
(事務局)項目については、今持ってきておりませんので大変申し訳ないです。ただ、生活の満足度の尺度としては・友人との関係・学習の意欲・教師との関係・学級との関係・進路の意識ということで、教師との関係とか、進路の意識については中学校のみになっているんですけれども、子どもたちが学級の中でどんな位置を占めているのかということについてわかることがございます。その表の中で上と対応している一番右側ですが、かなり分かりにくいですよね。これだと4つにしか色が見えないというふうに思います。本当に少ない数字ですよね。もう少しわかりやすく示せるようにしたいというふうに思います。
(委員)この紫色の一番端の学級生活不満足群というあたりの中に要支援のところが加わっているような感じですか。
(事務局)そういう感じでございます。
(委員)ちょっと私計算したんですけど、100%の中には入ってないですよね。これ以外のところで足したら100%になっていたので。ここには入っていないのかなと思っていたんですけど。
(事務局)その通りでございます。それ以外のところで。ダブっているということです。いわゆる、今言っていただいた中に含まれている一番右側のところに含まれているというふうに考えて頂いたらいいかなと思います。
(委員)要支援群の意味は、どういう意味ですか。
(事務局)要支援群といいますと、学級の中に子どもが承認をされていなかったり、他の子どもとの関わりがほとんどなく、完全に孤立に近い状況になっている子どもさんのことです。その子どもさんのことを担任が十分に理解していたらいいんですが、なかなか自分で疎外感があることが口に出せないとか、そういった子どもをこの調査によって初めて分かる場合もございますので、そういう意味で二重三重に子どもの状況を見ているという感じでございます。
(委員)質問項目はどういう質問でこのような判定されて炙り出されるんでしょうか。
(事務局)やはり質問項目につきましては、持ってくるべきでした。申し訳なかったです。
(教育長)後でまた終わってから会議しますので、その時までに、担当からも聞いてもらって。わかるように。今の説明ちょっと分かりにくいかなと思うので。後でよろしくお願いします。
(委員)2つ教えてください。1つは、これ何度も見ていると思うんですが、非承認群、それから侵害行為認知群という意味が難しすぎてわからないので、具体的にどんなことですか。これが1つ。2つ目。6年生、中1、中2が、1回目より2回目の方が満足群が下がっている。この原因はなんと考えられていますか。分析されていますか。
(事務局)まずこの説明について、その他の項目で私自身が大変準備不足できちんとしたお答えができませんので場所を変えて担当より説明をさせて頂きたいという風に思います。それでよろしいでしょうか。
(委員)はい。
(教育長)2つ目の項目はどうですか。小6と中1、中2の1回目より2回目が下がっているのは何と分析しているのですか。それも後からですか。
(委員)満足群が減っていますよね。
(事務局)それにつきましても、実はかなり、なぜかというところで担当も悩んでいるところがございますが、これにつきましても、ちょっと持ち帰らせてください。
(委員)また教えてください。後で結構です。
(教育長)担当でないと、専門的な形になってくるかなと思っていますが、ただ、私も思うのは普通に言えば、1回目から2回目が上がってくるのが今までの普通の状態ではないかなと思うんですけども、それがありながら下がっているのは、この1回目の数字が普通に考えて高すぎたのか、どうなのかなっていうこともあろうかなと思いますが。小学校6年生と中1、中2というこの学年が上がる中で、というところの重大さというか、なぜかなというところは聞きたいなというところではないかなと、ちょっとそこのあたり、分かるように後で伝えておいてください。
(事務局)申し訳ございません。
(教育長)他いかがですか。よろしいでしょうか。
(委員)はい。
(教育長) それでは、この項につきましては一部後から説明をうけるという形にしたいと思います。続きまして (6)小中一貫教育推進の手引き(案)につきましてを議題にしたいと思います。
(6) 小中一貫教育推進の手引き(案)について
(事務局 説明)
(教育長)説明が終わりました。これにつきましては、当日配布で非常に申し訳なかった部分もあるんですが、一昨日の小中一貫コミュニティ・スクール推進協議会の折の資料でございます。その中でも議論されたところでございますが、改めて、今後学校の先生方、保護者、地域の皆さん方にも具体のものを示して分かりやすくするべきではなかろうかなという思いの中で、こういう形のものも作ってもらいました。名前は小中一貫教育推進手引きとなっていますが、これは、名前だけでいいますと、国が小中一貫教育推進の手引きというのを文科省が作った、それを参酌してある部分もけっこうございます。今すぐ見てもらってどうこう言えない分もあると思います。それにつきましては、今、事務局が言ってくれたように、一読していただきまして、もう少し直した方がいいとか、あるいは付け加えた方がいいとかありましたら、事務局へ連絡を頂き、次回の定例の折には、それを修正させてもらって、出来る限り早く皆さんの前にとか、あるいはホームページにあげるとかということを考えていきたいと思っておりますが、今、説明を聞き、見てもらった中で、何かお気づきの点とか、質問とかありましたら、お出しください。いかがでしょう。
(委員)よろしいですか、この間京都のほうであったので、いろいろ聞かせていただいたんですけども、その中と関わっているっていうか、同じような方向で書かれてあるなと思って見せて頂いています。まだ、中はしっかり見ていませんけど。その中で、僕が聞いてきた事で、一つ二つ気になったというか、大事だと思ったことは、やっぱり小中連携する学校の先生方がまず知るということ、知り合うということが大事だということです。子どもを指導している先生方の姿見てみたら、小学校の子どもたちと中学校の先生との間の授業をしている中で、信頼感がある、そういうような授業を見せてもらいました。それが出来るというのは行き来がたくさんあるからというふうに思ったのと、それと合わせて思い返してみたら、私たち教師になった時に昔は教師仲間で寄って懇親会をもったりとか、そんな事があったりとか、それから組合の寄り合いというか、教研集会なんかで年2回集合して総会みたいな形であったんですが、その中で、あの先生は誰。この先生は誰。ということ、老いも若きもそういう交流があったんですが、今そういうことがなくなっているなという。だから、今、小中の先生方であれは誰。こんな人知らないっていうようなことがいっぱいあるのではないかなと。そんな中でやっぱりこれを進めていくのは難しいだろうなというようなことを思いながら、昔のことを思い出し、やっぱり知り合わないといけないのかなということを考えたので、そのこともこちらへ書いて頂いてあるように思います。それと、もう一つ思ったことは、何をやらないといけないではなくて、今それぞれの学校で何だったらできるのか、そういうことから始めていかないといけないのではないかな。ここにも書かれてありますけども、小中一貫で始めるから、あれもしないといけない、これもしないといけないというのは、とても負担感も大きいし、なかなかできにくい。それよりも、うちのブロックなら何が出来るのか、まず出来るのは何だろうかっていうとこから始めないといけないということも教えてもらいました。そんなこともいろいろ勉強させてもらいながらきたんですけども、これ見せて頂いて聞かせてもらってよかったなと思って、また伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
(教育長)ありがとうございます。他、いかがですか。
(委員)案の段階ですがよくいろいろな配慮がされているようにお見受けしました。ぜひとも完成に向けて良い手引きになるように取り組んでいただきたいです。その中で、この手引きを使う方、より参考にする方は誰なのか、読み手は誰なのかというようなことについては、あまりはっきりと明記がなく、その点につきましてはもう暗黙の了解で地域コミュニティの方、コミュニティスクールの関係する方、それから小中の先生方、教育委員会はじめ関係者というようなことなのかもしれませんが、やはりそれぞれ、誰が読み手であって、誰がこの手引きをどんなふうに使うということについても、少し具体的な記述もあってもいいかなというふうにも思いました。そのあたり、いかがでしょうか。
(事務局)ありがとうございます。明記していれば良かったんですが、実は対象は、教職員です。どうしてかというと、本当に大事なのが、今、委員さんおっしゃってくださったように教職員が感じている小中一貫や、コミュニティスクールというのが、モデル校から見えてくるのはどちらかというとイベント的なものが目につく。では私たちはあれをやらなくてはいけないのかとか、そうではなくて本当に今、小中一貫コミュニティスクールで一体何を目指すのかというところをわかって頂く必要がある。それの為に分かりきっていることかもしれないですけど、もう一度こういった文章をもって教職員に対して、各学校の校長先生方が語って頂くっていうことを再度やっていくことが必要だなということで、作成をさせて頂いているところです。今言って頂いたように、読み手をしっかり示させて頂くこと、それから字ばっかりで読む気にならないというふうに教育長からも指摘を受けておりまして、もうちょっと分かりやすくと言われております。校長先生方にご紹介をさせていただいたところも、一刻も早く欲しいと、こういったものをもって喋りたいとも言って下さっております。また、委員さんが言ってくださっているように、今では、実は少しずつですが懇親の機会もありまして、そういう知り合うということも含めて、会議も仕組み作りも徐々に進んでいるところではございます。頂いたご意見をもとに、また分かりやすく現場に伝えていきたいと思います。ありがとうございます。
(教育長)今、司会させてもらっているので、補足をさせて頂きますが、実はこれ、この件は当初の事項書の議題に上がっていなかった件でございます。一昨日、推進協議会をした中でその時は、今、事務局が言ったようにこの手引きは学校の教職員向けのものを策定したというふうなことで説明をしたところであります。貝ノ瀬先生からも、もちろん学校の先生方にきちんとわかってもらうのは大事だけども、関係する保護者、地域の皆さん方についてももう一度きちんと名張市が目指す小中一貫教育についてわかってもらうのが大事であると。そのことを進めるためにも、なかなか優れものの良いものを作成してあると貝ノ瀬先生に評価いただきました。だけど、今おっしゃってくれたように教職員向けに書いてあるのでは、読みづらいのでその概要版というか、図なりを入れてですね、A41枚くらいのを付けてもらってはどうかと思います。小中一貫の進め方がありますが、方針というか方向だけであって、もう少し具体の方策的なものも入れた方がいいのではないかという意見もございましたので、今日、定例教育委員会があるので委員さんにも説明をさせてもらって、意見を聞いたうえでそういう方向であればやっていこうかということでございます。もちろん主は学校の先生方がきちんと分かってもらわないといけないわけですけども、関係者の皆さん方にも知ってもらおうという意味でこれをもとにさらに良いものを作って、どんどん情報を発信したほうがいいということでございますので、そういう方向にするために今日は諮らしてもらったという経緯がございます。
(委員)おっしゃる通りだと思いました。手引きの“はじめに”のところについて、もしこういう形であればまた分かりやすいのかなという意味で提案さして頂きたいんですが、背景ということで、一般的な背景のところが最初のパラグラムのとこかと思うのですけども、3つ目のパラグラムのところから国のその方向性ですね、法制度の関係の話が出てきていたりというようなことで、やはり背景にあるその法的な枠組みの部分、それから名張市でこれまで推進してきたところの部分というふうに、少し落として頂いて、今後どういう方向に行くんだというような、タイムテーブルみたいなものもお考えでしょうけども、そういったものも少しあると、今、プロセスの過程、真ん中にいるんだというような位置づけで理解が進む資料になるのかなというふうに思いました。
(教育長)ありがとうございます。他いかがですか。
(委員)保護者の立場からのことになるんですけども、これは教職員の方向けの手引きで保護者が置き去りになっているのではないかなと私は思っていまして、実際のところ、桔梗学園というお話があったときにも、私は名張小学校の校区内なんですけど、もう自分たちは関係ないんだと思っていましたし、実際教育委員させてもらうまで小中一貫がこんなに進んでいるというか、目指していたっていうことも、私の勉強不足もあるんですけど、知らなかったので、たぶん保護者の方ってあんまり、知らない、情報が無くて知らない方が多いんじゃないかと思うんですね。だから、保護者、または地域の方向けにもうちょっと発信していったほうがいいんじゃないかなと感じました。
(教育長)ありがとうございます。おっしゃる通りでございまして、これは大きなことで、教育委員会で今説明会させてもらっても、最初説明した時は、何。ということであった訳ですけども、回を重ねるに従って、小中一貫教育ってこんないいところもあるのかということも分かってもらえることもあるので、どんどんそれは、発信をしていく必要があるだろうし、またそういうことについて何が分からないのかということの情報もこちらとしてキャッチしながらそれに見合うものを作っていくべきではないかなと。これは本当に大事な課題でございまして、名張市の教育ってなかなか見えにくいものがありますけども、目指していくことは間違いないと思っています。その方向できちんと伝えていくつもり、また別の視点からのいろんな声も聞いてですね、それも反映できるとこは反映していくということも大事かなと思っています。今おっしゃってくれたことは、本当に大事なことではないかなと思っています。
(委員)一点、お願いします。この手引きを教職員向けにということですが、今までに実際に行っている南中学校ブロック以外の先生方が、こういう小中一貫の名張市の方向性を文章で手にされたっていうのはあるんですかね。
(事務局)小中一貫教育につきましては、実は、パンフレットでお示ししてありますので、大きな流れについてコミュニティスクールを含めて、説明はしてはいるんです。ただ、やはり誤解もあり、あれを自分たちもやれと、市は言っているのかと、そういう風にやっぱりとられてしまう。いろんなところで誤解とか負担感が一番あるということで、やはりきちんと文章で書いてしっかりわかって頂く事が必要だなということがございました。実際にはパンフレット等を使って説明をしております。すでに、だいぶ前に。
(委員)それでしたら、先ほど教育長からもご意見あったっていうことですけど、これを頂くと、余計負担に思うと思います。これだけの文章、文字ばかりのもの、またこれ何かきたなというイメージがあるので。やっぱりもう少し、こういう事もあるんだなという風にもっと分かりやすい表とかいろんな形のパターンも入れて頂いて、もっと手にしてみようと思うような内容にして頂けたらなと思います。以上です。
(委員)教職員の方が、特に学校現場の先生方がやらされ感がある、今の限られている資源の中でやるというのは、非常に時間も労力もタイトな時間ですね、タイトな状況にあるということでどうしても全体の像が見えないんじゃないかと思います。この小中一貫を進めることで本当に子どもの教育指導がしやすくなる部分、変な表現かもしれませんけど、やりやすくなる、教職員の指導においても非常に教育指導の効果が上がりやすくなるというような何かチャレンジすることで自分たちの能力も高まるし、子どもの能力も高まるしと。能力といいましょうか、努力が実る取り組みなんですよというふうな積極的な方向性の哲学と言いましょうか、そういったものが示されると、少し良いのかなというふうに思います。先ほどおっしゃられたように、何をするというふうに具体的な話にすぐ入ってしまうところがありますので、やっぱりもっとアイデアのところですね、これはもっと進めて頂いて良いかと思います。ビジョンを、やっぱり明確に示すことだと思います。これはホームページなどを通じて、市民の方も巻き込んでやって頂くことも必要なのかなと思います。ですから、保護者の方が先ほど置き去りになっているような意識はもっていらっしゃるような場合もあろうかと思いますので、教員研修の折とかですね、いろいろな学校の分の時に、できればPTAの方、保護者の方のご協力を頂いて、それこそシンポジウム形式といいましょうか、座談会、公開座談会形式みたいなこととかですね、公の場で保護者の方や地域の方のお話を踏まえながらこれに向けてうちの学校はこういう風に進んでいきたいですという様な事を発信するような、そういう企画があってもいいのかなという風に思いました。こういった手引きだけが、紙だけできますと非常に重荷になるような気もしますので、そういうイベントも併せてはどうかなと思いました。
(事務局)貝ノ瀬先生にも、今委員さんのおっしゃられた通り、全体構想、グランドデザインを示しロードマップを示す。そして説得力のあるのは絶対的に数値であると。一番保護者が望んでいる、地域が望んでいるのは、どれだけこのことによって学力が上がったかとか、これによって効果がこれだけあるとそういったものが示されて初めてこの良さがわかる。そういったことを踏まえてやっていかないといけないということを教えても頂きまして、大変たくさんの宿題を頂きながら事務局としてやれることを頑張りたいというふうに思っております。本当にご意見ありがとうございます。
(教育長)ちょっと付け加えさして頂きますと、皆さんのおっしゃられたこと、ごもっともなことでありますし、一昨日の会議の中でもこういうことが出てきたところですが、やはり、結論から言いますと、これまでいろんな事をしております。教職員も今のパンフレットも全員配布はしてあるんですけど、今、つつじと南中学校は1小1中でやっていますから、これはうちには当てはまらないだろうという思いもあるわけです。そうではなくて、名張市がお願いしているいわゆるスタンダードの部分と、もう一つは1中5小のところもあるわけですから、それに合ったものを考えてもらう。これ一律にこうやりなさいっていう事じゃなくて、スタンダードはスタンダードを示しながらやっぱり自分達だったらどうしていこかとか、いうことを、同じ形にしなくても良いので、それについてはいろんな声を聞きながら早い段階その方向性なりを示して、そういうところについても話し合いをしてもらう。それに一番良いのはこれから作ろうとしているコミュニティスクール学校運営協議会の中でもですね、目指す子ども像もしっかり持ちながらその為にこの小中一貫教育をどう固めていくのか皆さん方の声も拾い上げてもらって、やってもらうようにすると成功に近づくのではないかなと。トップダウンばっかりしているとなかなかそれは一定できたとしても本当に長続きするかどうか分からないということもございまして、こちらにつきましては今日こうやって急遽教育委員の皆さん方にもお示しさしてもらって声を聞かせていただきました。まだありましたら、遠慮せずに事務局へおっしゃっていただけたらけっこうかなと思いますので、宜しくお願い致します。
(事務局)どうもありがとうございました。
(教育長)学校教育室は以上でございますが、何か学校教育室に対して、委員の皆様方からこの際聞いておかないといけない様なこと、よろしいでしょうか。それではちょっと先にさして頂きましたけど、どうぞ退席いただいて結構かなと思います。それでは戻りまして、事項書の順番でいきたいなと思っております。
議事(1報告)
第1号 臨時代理した事件(平成29年度3月補正予算要求)の承認について【非公開】
第2号 臨時代理した事件(平成30年度当初予算要求)の承認について【非公開】
議事(2議案)
第1号 第二次名張市子ども教育ビジョン進捗状況報告について
(事務局 説明)
(教育長)説明が終わりました。これらにつきまして皆さん方からのご質問ご意見ありますか。
(委員)15ページの(4)の一番最後の行です。これはおそらくタイプで残ったところかと思うんですが、「者や地域住民と丁寧に協議を進めながら」っていうとこ、“保護者”だと。そうしましたら、前の言葉と少しダブりましょうかね。あの、「協議を重ねながら進めていく必要があります。」と、今回訂正の資料に書いてまとめておられますのでその後のとこは削除かなというふうに思っております。
(事務局)ありがとうございます。
(教育長)事務局よろしいか。
(事務局)ありがとうございます。訂正させて頂きます。
(委員)つまらないことですけど、17ページの家庭教育の向上のところで、「子どもの発達に係る悩みに対し、具体的な支援の方法を学ぶことができました」ってあるんですけど、この文章は誰が書いている文章ですか。これだと、普通やと一般市民ですよね。これだと。そういう書き方でいいんですかね。
(教育長)事務局どうですか。
(事務局)ここのところは教育センターで行っています。子育て支援と家庭教育連続講座なんですけども。保護者・地域の方向けの講座でして、家庭教育という部分で、その家庭教育連続講座を受けて頂いている方に、家庭教育をもっと広めて頂く、家庭教育のスタッフを育てている部分もありまして、5番の検証のところでは、そこに参加した人が家庭教育を広めていくスタッフにという意味で支援することができたというのが2行目の方に書いてあるので、そういう意味合いです。
(教育長)1行目はちょっと、その家庭教育講座っていうことがないから、わからないということでしょう。
(委員)主語がもうひとつ、よくわからないので。すみません。つまらないことでしたが。
(教育長)いや、大事なことです。よろしいですか。再度見てもらってですね、教育委員会が最終的な形になってきますので、細かいとこまで見て頂いて、疑問点がありましたら、なるべく早い機会に、また事務局連絡して頂いて、一応この場ではこれは了承ということでよろしいでしょうか。
(委員)はい、結構です。
(教育長)この議案第1号につきましては承認ということで処理をさせて頂きたいと思います。
第5号 平成29年度名張市教育委員会事務の点検・評価について
(事務局 説明)
(教育長)説明が終わりました。何か、これについてご質問ご意見。
(委員)最終案が往復ページにでるということでありましたら、いかがでしょうか。1ページ目の〈施策1〉の中で【基本方針】の4行目にありますESDの略の語記もあったら分かりやすいかなというふうに思います。
(教育長)これについて事務局どうですか。
(事務局)基本的には、基本方針いうのは、新・理想郷プランの中の基本方針をそのまま抜き書きをしているんですけれども、注釈という形で表現をして考慮していきたいと思います。
(委員)はい、ぜひとも。最初の施策1のところから、読んで分からない言葉が出てくるのは、後へ続かないと思います。
(教育長)その方向で分かりやすくしてもらうということで。
(事務局)もう一度そちらの方表現を検討しますので。
(教育長)他にいかがですか。
(委員)皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっと教えて頂きたいんですけれども、2点なんですが、放課後子ども教室っていうものと、総合型地域スポーツクラブっていうのを、ちょっと私理解できてなくて、説明して頂けると有難いんですが。
(教育長)はい、事務局。
(事務局)放課後子ども教室でございますが、名張市では土曜日、日曜日の子どもの居場所づくりと体験をして頂くという形で、主に地域づくり組織の方に、企画して頂きまして放課後子ども推進事業という形でお世話になっております。
(教育長)総合型についてはどうですか。
(事務局)地域スポーツクラブというのはですね、国が進めている施策の1つでございまして、地域でスポーツ活動を、子どもから高齢者の方まで取り組んで頂けるような、そういう組織づくりをしようという形でございます。名張市では3年間、最初の2年間育成のための組織づくりの支援をさせて頂いて、立ち上がったら活動を頂くという形で、今現在は3つ、それから30年度、今年で1つ立ち上がって頂きますので、そういう形で今はサッカー関係の総合型が3つと立ち上げに進んでいるのが、百合が丘が地域を主体とした総合型スポーツクラブっていうのを立ち上げていまして、順次、理想としては各地域に1つくらいなんですけども、そういう形で地域に根差したスポーツ活動が出来る組織を作っていこうということでございます。
(教育長)よろしいですか。他どうですか。
(委員)施策4の10ページの今後の方向性のところなんですが、今、生涯スポーツということで書いて頂いているんですけども、今後の方向性の2つ目、例年開催しているスポーツ関連行事等の文章のところですが、指定管理をして頂いているところもありますので、そういう民間の指定管理というところの力も借りて既存の形にとらわれないような、そういうイベントもやっていくというような中身にして頂いたらどうかなと思いました。指定管理さんとの関係というのが今後の方向性の中には出てきてないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
(事務局)ご意見頂いた部分、関連行事の部分になると思うんですけども、事務局ともつめさせて頂いてご意見の部分については検討させて頂きます。
(委員)はい、お願いします。
(委員)5ページで、先ほどご質問ありました放課後子ども教室というのは、これは臨時開催するものですか。常設のものですか。
(事務局)放課後子ども教室でございますが、地域の方にお世話になって、していますので、一応、名張市としては月に1回、年間10回から12回程度という形になっています。
(委員)わかりました。はい。別件です、10ページで、5番にあります行政評価委員会による総合評価の中でも言われているツーリズムの促進ということと、スポーツ健康づくりということと、どういう関連で、この文脈が出てきているのか。もちろん、6.今後の方向性の2つ目のポチの下のとこにも、ツーリズムの促進とありますけども、それ以外のところでツーリズムという話があるのかもしれませんけども、これどういうことイメージされているのかが、あんまり分からないんですけど。市民の方にどういう働きかけをされるような、または、その為にどういうリソースを使うのか、どんなイメージでどういうことを基準として動いてらっしゃるのか教えてください。
(事務局)5番で行政評価委員会からですね、健康づくりを通じたツーリズムということで、言葉が出てきているんですけども、一応評価委員会の方の考え方としてはですね、名張市は今、観光を一つの産業と捉えて、エコであったり、農業体験であったり、様々なツーリズムを名張市の目玉として広げようとしている。その中で、健康、スポーツも1つの産業と、せっかく整備されました陸上競技場であったり、そういうスポーツ施設があるという中で、合宿誘致であったりですね、市民の方も巻き込んだ、何かできたらというイメージを持たしていただいている。
(委員)はい、よくわかりました。
(教育長)他いかがですか。
(委員)これ見せていただいていて、例えばこの小中学校の教育環境に満足している市民の割合っていうのがあって、目標値が65%になっていますよね。この教育委員会でいろいろ参加させていただいている中で、それこそ、本当に行政の方でよく頑張って頂いて学校の教育環境一生懸命良くするために努力して頂いているけども、それが市民に伝わっているのかなということを考えていた時に、自分の身近や兄弟やそんなことを聞くと、うちの子どもが小学校中学校卒業したら、もう学校とは離れてしまっている。だからもう学校で何が起きているのかわからない、っていうのが普通の人の考えだと思うんです。それと、学校がこんなに良くして頂いた、教室の電子機器もすごいきちんとなっているし、耐震補強もきちんとしてもらったし、もうあとは空調だけ。これも、もうしてもらえるっていうような状況になっている事すら一般の人は知らないと思うんですよね。行政一般ですけども、やってくれていることは、関わりのある人は知っているけど、関わりの無い人はほとんど知らないという中で、教育環境に満足している市民の割合、この指標65%とかそれが本当に正しいものなのかなという、そんな気がするんです。行政でいろいろ仕事して頂いている職員の皆さん、本当に歯がゆい思いすると思うんですけども、そういう意味でやっぱり一般市民へ、公募もあるわけですけども、もっとアピールし、認識を深めてもらえるような、そんな市としての取り組みをもっとしてもらわないといけないのではないかな、そうでないとせっかくやってもらっていることが見えないというのは本当に残念に思います。そんなことを思いました。それからもう一つ、本のところですけども、市民一人当たりの年間図書貸し出し冊数が7冊ということで今数値目標があるんですけども、これ、前のところを見たら市内では6.5冊と県下でも比較的高い水準にありますってありますよね。7冊という目標は適切なのか高すぎるのか、そのあたりはどんなものかな。妥当な目標なのかなというのがちょっと気になるんですけども。みんなが、赤ちゃんから年寄りまで、なべて7冊ですよね。申し訳ないんですけど、私借りた事ありませんし、申し訳ないんですが、その辺のとこの目標の取り方というの、これは出来上がっているものですから仕方ないんですけど、新しい計画立てる時には、その指標なんかをもうちょっと精査してもらったらいいのではないかなとそんなこと思いました。感想です。
(教育長)よろしいですか。はい、事務局。
(事務局)おっしゃって頂きました市民の意識調査の件につきましては、毎年5月に2000件の調査をかけています。基本的に二十歳から七十代までで、ある程度年齢が偏らないように無作為に何パーセントか抽出をして発送して返していく。毎回50%程度、1000件くらいの回収ということの中で、特になんですけども、先ほど、事務局からも言いましたが、ちょうど教育の中で特に、そういう風な、これはあまり大きな声では言えないですけども、反対とかされている方のところに行くと、当然大きな声でバツという形になるんですけども、逆にそういうような方はそんなとこが逆に普段はあまり回答はされないんですけれども、この際にということで回答される場合はどうしてもやっぱりポイントが落ちるというようなことがあります。大体例年、高齢者の方がやはりこういう様な回答率が高いんで、高齢者の方が多い場合はやはり教育関係のところはあまり関心が無くなってしまうので、まぁいいのではないかというような形で、どうしてもポイントが高くなってしまう状況があります。今おっしゃっていただいた様に、本当に皆さんがちゃんとした情報の下でこの調査をしているのかと言われると非常にクエスチョンの部分もありますし、私どもも今おっしゃっていただいたようなことで、どんどんやはり情報提供、情報をもっともっと発信していかなくてはいけないのかなということを思わして頂きました。どうもありがとうございます。
(教育長)すぐにどうこうできない訳ですけども、そういうことの指標の目標、それは今後の検討課題いうような形にしてもらったらどうかなと。他いかがですか。
(委員)11ページ施策5についてです。先ほども、ちょっと申し上げたかもしれませんが、何か新しい文化振興というようなことで、取り組みを、新しいものチャレンジしていかれるという方向性もあるのかなと思っておりまして、11ページのナンバー1.2.3.4とあります事務事業の中で教えて頂きたいんですが、今後の方向ということで、1.2.3.4の1つ目は改善、継続改善ということですが、下の3つは継続で拡大とあります。これについてどういうお考えかをお聞かせください。他の施策においては継続というものとか、現行というような表記が多い中でこの施策のこの2.3.4.については拡大という点が目立ちました。教えてください。
(事務局)文化振興費の予算と上からの補助の関係でございます。まず最初の文化振興費でございますが、こっちにも書いてありますように、『市民文化祭及びの市美術展覧会を開催し、創作活動の発表及び鑑賞の機会を提供し、市民の芸術文化への関心を高める』とありまして、まず市民文化祭につきましては、1つは、市の文化協会ございますもので、文化協会さんとか他も協力させて頂きまして、現在、市民文化祭のほうやっております。また、市美術展覧会につきましても、今現在は市美展の審査委員会だけでございますが、運営委員会という形の方もしまして、さらに発展させるような形を考えておりますもので、そういったことも含めまして、継続拡大という形でさせて頂きました。そして続きまして文化財保護費でございますが、『指定文化財の保護及び史跡の維持管理を行い、後世に伝えるとともに、地域のシンボルとして活用を図る』という形で文化財保護につきましても名張市では90を超える市の教育文化財がございます。それにつきましても例えば、美旗の地域づくりさんと協力して美旗の古墳群をアピールする機会等、市内外の方に発信するような機会を設けたいという形で今回継続(拡大)という形で書かせて頂きました。以上です。
(委員)大変、良く発展的なお取り組みをされていることよく拝察致しました。よく理解できますが、内外発信といった時には、ホームページなど活用されていることかと存じます。今の中では例えばこういう文化振興の中身について、外国人に向けた情報発信ということでも積極的にホームページでの発信というようなことも、ぜひともチャレンジしていただければと思います。何故かと言いますと、名張市にたくさんの外国人の方が来て頂く、外国人の方も来て頂く、また、子どもたちもそういった事で英語に触れていくという2つの効果もあろうかと思います。取り組みの成果の中でちょっと懸念しておりますのが、こちらの市で非常に文化資源として古くからある観阿弥、能楽の分なんですけどもこの年の所属関係で申しますと非常にそういった古典芸能に興味関心をもつ若い方というのがだんだん年々減ってきていたり、またそういったことをやられている方が年配の方が多い割には、若い方がなかなか少ないというようなことで、参加する人数がクラブ活動なんかもそうなんですけど、参加する人数が減ってクラブが廃止になったり、またなかなか存続が難しいというようなことも多々見受けられます。こちらの市ではそういったことないのかもしれませんけれども、ちょっとそういうような事を考えると、この資源をいかに残していくかというのは非常に重要な課題の様に思われます。いかがでしょうか。
(事務局)委員さんがおっしゃる通り古典芸能、特に能文化ですね、名張にもサークルあるんですけど、高齢者が多くて、すでにそういった団体の方のお話を聞いておりまして、また、子どもさんも参加できやすい形で名張では子ども教室、また、能楽囃子教室という形でサークルを立ち上げて、子どもさんの育成もしております。ただ、青年層が入るというのがやっぱ少ないというのが課題でございますもので、それをいかにして入ってもらうかというのが今後の目的でございます。
(教育長)今後の方向を見た時に継続の多くは現行というのが非常に多いわけですが、拡大が文化振興非常に多いと。名張は文化に非常に力をいれているなとこれだけ見たら思うかもしれませんが、予算みたらどうだろうかというようなことも思うところでして。このことが、本当にこの点検・評価の報告書として統一されてなされているんだろうかというふうな事の中で、この表記の仕方について誤解を招くという事のないようにしないといけない、個々のところの施策が1~5まであるわけで、それぞれ、個々の担当でやってしまっているじゃなくて、やっぱり調整をですね、どこかで図ってもらうほうが良いのではなかろうかなというふうに思います。これ今すぐ出来ないことでございますが、今後の課題としていかないとですね、やっていることと、この報告とがどうなんだろうというふうな形に答えられないかなと思うのでこういう点も考えてほしいなと思います。あと、細かい事、ちょっといかしてもらいますと、2ページの事務事業のところの最後、“学校支援地域本部事業”これ、同じことが6ページの中の2番目に同じものがあります。これは、今後の方向性は2ページと6ページが現行と拡大、これどうなっているのかなというふうな気がいたしますが。ここらはきちんと整合性をとってやってくれているんでしょうか。
(事務局)すいません、これは事務局のミスで、これどちらかが間違っていると思いますので、申し訳ないです。これ早急にちょっと確認をさせて頂きたいと思います。すいません。
(教育長)両方入れなくてもいいのではないですか。片方に入れておいた方がいいのではないかなと思ったりするんですけども。
(事務局)考え方として、両方の施策に繋がるということでこういう様な事業の他にも何個かあります。ですので、この事業によって2つの施策。
(教育長)わかりました。それとそれと今言った形の中でちょっと、方向性だけ整合性をとってもらっておくほうが。それではまた、これも再度検討し、この場では一応この第5号につきましては承認という形で進めていきたいと思いますが、再度見てもらってですね、細かい点、所々の、ありましたら事務局へ、なるべく早く連絡してもらうということで進めたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(委員)はい。
(教育長)それでは第5号につきましては一応承認という形で処理をさせて頂きたいと思います。
議事(3その他)
(1)通学路交通安全プログラムに基づく「対策一覧」の公表について
(事務局 説明)
(教育長)はい、説明が終わりました。委員の皆さん方からご質問、ご意見ございましたらお願いします。
(委員)ご説明ありがとうございました。ホームページで公表なさる資料というのは、どの資料になりましょうか。教えてください。
(事務局)はい、事前に配らせて頂きました一覧表、対策一覧表といったものと、対策箇所図といったものです。総括表については資料ということでホームページには載せないということで、一覧表と箇所図がホームページに公表されます。
(委員)Aグループのところで“名張中学校、梅が丘小学校は危険個所なしで報告“ということは、これは学校側から危険な箇所はありませんという報告があったということですか。その旨はホームページには載せられますか。
(事務局)今のところは2ページ以降ですので、何も載らないということです。
(委員)載らないということですね。やっぱり、私梅が丘ですけども、保護者の方でも草があまりにも生えている空地とか、そういうところいろいろお聞きはするんですけども、そういう部分で、今回は学校から危険な個所の報告はなかったというような事を入れて頂く方が良いのかなと思うんですけど。どうでしょう。
(事務局)その件については一度、校長の方から教育委員会へ報告さしていただて、そういうようなご意見があったということで、確認をした中で、一度検討してみたいと思います。
(委員)はい、お願いします。
(教育長)特にこれ、通学路の安全ということですから、そのことについて、普段いろんなところの危険個所ってたくさんあると思います。通学路についてのことですから、そのことを限定していると分かるようにしたらいいのかなというように思います。今言った形の中で、無いからに挙げていないでは、調べたのか、やってないのかわかりませんので、ちょっとそれだけ書いてもらう方が納得してもらえるかなということで、お願いします。他、いかがですか。
(委員)これ、いつも地区懇談、小学校の場合地区懇談会の時に、地区委員さんのほうから、危険個所ありませんかって保護者の方にいつも問いかけている感じなんですけど、それをこう、集めた分なんですかね。保護者の。先生方が見て回っているわけでは、きっとないんですよね。
(事務局)学校によってはいろいろあると思います。地域の方がかなり見守りされていますので、地域の方からあそこ危ない、ここ危ないっていうことで学校に聞いている部分でありますとか、保護者の方も同様に。ただ、学校も全く現場を見てないということはまずないと思いますので、そういう意見があった時には、学校としても確認をしていただきながらたぶんPTA、地域の方と相談しながら対策箇所として挙げて頂いているという、私たちは認識しております。
(教育長)せっかく、こうやって公表もしてくれるんでしたら、過去やってきて今回はこういうことでしたと、いう様な事をしてもらう方が誤解を招かないかなと。また、これまでやって、それはもうある程度解消されているとか、あるいはこれはもういくら挙げてもできないことで、国・県の方へ申し入れをしているとかあるんだったら、それと一緒に挙げておいたらいいのではないかなと思うし、そういう取り組みを今回はこうやって出ているけども、これまでの分もあるわけですから、それもちょっと加えて、もし公表するんでしたら最初の説明の中で、今回こういう形でこの29年度で点検した取り組み状況はこうでしたという風にしてもらうほうがわかりやすいかなと、誤解を招かないかなと思うので、ちょっとそこのあたりを配慮してもらったらいかがなものかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
(2)今冬のインフルエンザ発症状況について
(事務局 説明)
(教育長)はい、報告終わりましたけど、何か委員さんのほう、聞きたいこと、ご意見、ありましたら。全国的にも過去最高の数がでるということ、マスコミでは報道されているところで。まずはやっぱり罹っているのに蔓延さしてはいけないわけだから休む措置ということも非常に大事なことかなと思うところであります。子どもの健康面は最重視することは非常に大事なことかなと思うところでありますけども、また一方では、子どもたちがその抜けた部分をどこでどう保障してくれるのということも保護者のほうからも、これまでも教育の問い合わせもあったこともあるわけですから、そのへんはきちんと学校として後の対応、対策ということについてのことは、納得できるような形のものをきちんとやってくださいと。しかし、かといって、授業日数確保しないといけないから、かなり人数いても閉鎖しないではいけないと思います。やっぱり子どもの健康管理ということは大事にしないといけないわけですけども、併せてのことの事は、とりあえずきちんと言っておかないといけないのではないかと思います。その辺のこと併せてよろしくお願いしたいなと思っています。まだまだこれから寒さ、そして乾燥続いてくると思いますので、出来る限りかからないように、又かかってもそれを広めないように、ということをして頂くということでお願いして頂きたいなと思います。よろしいでしょうか。
(委員)大流行ということで今年の流行が来年そうでなければと思うわけなんですけども、どちらかというとこういう学級閉鎖とか学年閉鎖いうのはイレギュラーなことでありましょうから、その時の対応ということについては学校ごとでそれぞれ校長先生の指揮のもとで対応されている事とは存じますけれども、やはり一定の非常事態対応といいましょうか、そういったことについてのある程度の枠組みみたいなものもあってもいいのかなと。現場のその、先生もインフルエンザになられて出勤が停止のような状態になられる場合もありましょうから、そういう意味でもインフルエンザに限りませんけども感染症とかですね、そういった時の対応について、ある程度の方針と言いましょうか、そういうものも各学校にあるのかもしれませんけれども、非常事態の対応ということについては現場の先生たちが疲弊しないような対応でやって頂ければと思います。そのあたりいかがでしょうか。要は、休んで、そのツケが子どもたちにきてもいけませんし、教員個人が引き受けるっていうことでもいけませんでしょうから、そのへん、たしか文科省から言われていますように、チームとしての教員組織というようなことがありますので、そのへん、チームでどういうふうに転がりきってくかっていうようなことについては、今、非常事態対応という視点で何かあってもいいかなというふうに思います。いかがでしょうか。
(事務局)今、残念ながら、教育委員会でのその対応は体制としてはないんですが、市としては何かありましたらすぐにその体制がとれるようになっています。だから最終的には市でそういうような事が設置されますと必然と教育委員会にむいていくというような形になりますので。教育委員会と学校の中でのっていうことではちょっと今のところは、今、学校長でしているというところではございますが、市としてはそういうふうな体制は持っていません。
(教育長)すぐにどうこうというのは難しいと思いますので、文科省からしていただいているガイドラインも参考にしながらですが、現場の状況全く違いますので、そこのあたりの分を、例えばチーム学校という形で、おっしゃられる通りなんですけども、そのチームすらできないという状況にある学校も出てくるわけでして、非常に難しいところでございます。やはり集団生活をするところですので、子どもも先生も。そのあたりどういうふうな対応・対策をとっていくことが、常時あることと違いまして、突発的というか臨時で起こることでございますので、なかなかその対応難しいんですが、そのことによって大きな被害にならないように手を打つことが最大の方策です。あとのフォローについては極力、ある一定のことは指導しておいてもらっておかないと、学級閉鎖なり一時休業している、こんな意味のことが、子どもも親もそれなりにわかってもらってやらないと、結局ズルズルいってしまうということになりかねないと思います。非常に教育委員会として難しいところですけれども、何かその辺のことについては考えておかないといけないことも今後でてくるのかなということに、目をやって頂くようにして頂ければ有難いなと。よろしいでしょうか。
(3)義務就学者の就学校の変更について【非公開】
(7)平成30年度研修講座等の実施予定について
(事務局 説明)
(教育長)説明が終わりました。この事につきまして何か、ご質問、ご意見いかがでしょうか。
(委員)6ページの3番目、教えてください。“グループ研究部会”というのは、これはどんな開催でしょうか、場所はどちらで。
(事務局)これはですね、10個のグループ教科であったりとか、それから道徳や人権的な事とかテーマがございまして、その10個のグループに分かれて、それぞれ各学校からそのグループに所属して研修を行うというものです。これが平日の水曜日が原則で行われておりまして、3時半からもう各学校を出て、それぞれの会場へ集まって、研修をやっていると。その研修というのは市の施策でめざしているところに、例えば、小中一貫教育であったりとか、いうふうなものを加味した中身であるんですけれども、そういうふうな、それぞれの、英語だったら英語、国語だったら国語というので集まってきて研修をしているというのがグループ研究部会です。
(教育長)自由に選択をして自分の入りたいところをやって、1年間同じところに所属して研究をしていくと。こういうことですが、中に、必要なことについては若干学校によって全く自由にということでないところもあります。基本的には自主性を重んじているところでございます。教科内容等、今言ったように十以上のものあると思いますけど、やはりそれぞれについての内容はこれからの学習指導要領のこともあるし、喫緊の教育課題のこともあるし、研究の中身としてはそういうことを踏まえてやってもらっているということでございます。場所はバラバラでやってくれているということでございます。他どうですか。それではこういう形ですが、1つだけ、先ほど言った教育講演会8月17日ですが、実はこれ、働き方改革の中で県もこの週は、県の会議とか研修等々はやめておこうという事の中で、来年度は8月の13~17のこの5日間、月曜~金曜までを県としては行われますし、市町も協力してくださいということですが、先ほど言ってくれたように、どうしても講師の都合、会場の都合でこの日しか取れないのでということで、あらかじめ言わせてもらっているところです。なお、それと別ですけども、本年度も先生方の勤務を考えた中で、夏休み中お盆の今年は13~15だと思いますけども、3日間学校を閉校にするとしておりまして、来年度は13~16の4日間を閉校にしようかと、その方向で検討しているということについては校長会でも話をしているということです。よろしいでしょうか。
(8)平成30年度成人式について
(事務局 説明)
(教育長)教育委員の皆さん方もお休みのところご出席を賜りましてありがとうございました。先ほど室長から報告あったように、今年はADSホールが工事の関係で、またHOSアリーナの方に戻ったということでございますが、いろんな状況の中、特に事務局の皆さん方にお世話かけたところでございますが、無事に終えて頂きまして有難かったなと思うところです。何かご意見なり、感想なりありましたら。よろしいでしょうか。
(9)名張市民野球場ネーミングライツ(命名権)募集について
(事務局 説明)
(教育長)それでは、ネーミングライツ プラス 夜間照明の陸上競技場の件がありましたけど、この件につきまして何か、委員の皆さん方からご質問ご意見ございましたらおっしゃってください。
(委員)2点お願いします。ネーミングライツの方で、この国体期間中は月額1万円のアップで年間12万円ということですけども、これは月額1万円のアップというのは団体さんで練習とかそういうので利用されることが多いであろうということになるんでしょうか。
(事務局)ネーミングライツにつきましては、名称がいろんな媒体に出るということで国体の場合、テレビで軟式野球の開催に決定しておりますので、そういうポスターに出たりとか、大会プログラムに出たり、そういう関係で報道の中で、テレビで、ローカルになると思うんですけども、そういう広告としての露出度が上がるということで、1万円。ただ、1万円かどうかはその当時にそういう価値はあるだろうと検討頂いた結果で月額1万円という形になっております。
(委員)分かりました。それともう1点。照明を修繕して頂く訳ですが、完了というか、使えるようになるのはいつごろになるんですか。
(事務局)2,800何がしの予算は、8機を全て直すという。11月の時点で4機ダメだったんですけども、おそらく同時に施工していますので、同じようにダメになるということが予想されましたので、教育次長や教育長にも無理を言いまして設計を、予備費等財政からも頂いて12月に全体8機の設計を上げていますので。ただ、4月に、市役所の手続き上ですけども、入札にかかりましても実際に施工にされるのは、ほとんど特注品でございまして、工場で全て生産してきて、現地で設置という形になりますので、我々の思いとしては夏前、7月には何とか間に合わせたいなという、今現在の予定でございますので。これはやっぱり電線、電気材料なんかもですね、オリンピックの関係でなかなか難しいと聞いています。それと、天候模様、外の工事になりますので、それらの見合いもありますので、今の予定としては7月の頭にはオープニングさせたいなと思っているんですけども、また状況等ありましたら定教委の中でもご報告させて頂きます。
(委員)わかりました、ありがとうございます。
(教育長)最悪を想定すると、今の4月上旬にはしたいんですけども、なかなかそうはならないという可能性が大であるということは、ちょっと。4月初めはできなくていいということにすると、また誤解を招く恐れもあろうかなと。他、どうですか。はい、それではこの件につきましての議案を終えたいと思います。どうもありがとうございました。これをもちまして第11回の定例教育委員会を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
・定例教育委員会の日程等について
(3月定例) 3月6日(火曜日)午前9時30分~
(3月臨時) 3月13日(火曜日)午後4時~
(4月定例) 4月9日(月曜日)午前9時30分~