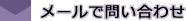平成29年度名張市教育委員会第8回定例会会議録(平成29年11月6日開催)
更新日:2018年9月6日
開催場所など
2.開催日時 平成29年11月6日(月曜日) 午後2時から午後4時50分
3.出席者 上島教育長、福田委員、松尾委員、瀧永委員、川原委員
4.欠席者 なし
5.事務局 高嶋教育次長、草合教育改革担当理事、合田スポーツ推進担当監兼国体準備室長、内匠教育総務室長、中森学校教育室長、上谷教育センター長、西山文化生涯学習室長、宮前図書館長、田中市民スポーツ室長、福本教育総務室教育総務係長(書記)
6.議事概要 下記のとおり
(教育長)それでは只今から第8回の定例教育委員会をはじめたいと思います。議事に入ります前に本日の会議の公開についてお諮りをいたします。本日の事項中その他の項目の(1)就学義務就学者の就学校の変更について、(2)児童生徒の問題行動について(9月分)、(6)第10回なばり本の帯コンクール審査結果についての項目につきましては、名張市教育委員会会議規則第8条の規定によりまして非公開とすることを提案したいと思います。委員の皆様方、ご異議ございませんか。
(委員)異議なし。
(教育長)はい、ありがとうございます。ご異議がないようですのでこれらの案件につきましては非公開として本日の会議を進行することといたします。それでは事項書に基づきまして会議を進めていきたいと思います。まず1.報告 第20号臨時代理した事件(教育委員会職員の人事異動)の承認についてを議題といたします。
議事(1報告)
第20号 臨時代理した事件(教育委員会職員の人事異動)の承認について
(事務局 説明)
(教育長)はい、報告が終わりました。何か委員の皆さん方ご質問ご意見ありませんでしょうか。
(委員)はい。2点質問をお願い致します。この子どもさん以前にお聞きしたかもわかりませんが、アレルギーの重度というのはどのような状況なのかということと、それからこの新しく臨時でついてくださる2人の介助員さんは看護師の免許はお持ちなのかをお聞かせください。
(事務局)重度のアレルギーは牛乳、卵、大豆、小麦、そば。でかなり同じ部屋にいてその空気を吸っても出るというようなことで、給食についても基本的にはこのいわゆる3年生の児童は、一般の子どもたちとは離して給食を食べてもらっています。当然のことながら、あとの今回新たに任用した2名につきましては、基本的に技術員という事になっておるんですが1名は看護師の免許をもっていて、1名は看護師の免許をもっていない。ただこれを色々調べていく中ではいわゆる寄り添いという事でございますので、基本的に看護師免許をもっていなくても、ライセンスをもっていなくてもできるということですので、基本的には1名は元々市の職員で看護師免許をもっている職員でございましたが、退職してお願いをしたというようなことでございますけれど、基本的にずっと1日寄り添っていただけるということでございまして、今の所大きな事故もなく順調に毎日過ごしていただいているということを聞かせていただいています。
(委員)はい、わかりました。ありがとうございます。
(委員)同じく、寄り添うということでこの技術員の方がその対象となる児童の方にどのような寄り添い方を教室の中で、又学校の中でされているのか、ちょっとご様子をお聞かせいただけるとありがたいのですけれども。
(事務局)この児童につきましては、教室の中に空気清浄機を2台おかせていただく形でべったり横についているのではなく、教室の見守れる範囲の所に机を置いていただいて絶えず凝視というか見ていただいている状況ですので、体育等につきましても近くで必ず見守っていただくことを続けていただきました。専門の医師とも学校とそしてまたこの介助員とも引き継ぎさせていただいているということで、こちらの方も親御さんとも校長と共に面談させていただいてご了解の上引き継いだという案件です。
(教育長)はい、それではこの件の報告という形で了承させていただきます。続きまして議案の方に進みたいと思います。議案第17号名張市就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱の制定についてを議題とします。
議事(2議案)
第17号 名張市就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱の制定について
(事務局 説明)
(教育長)事務局からの説明が終わりました。委員の皆さん方ご質問ご意見ございましたらお出しください。
(委員)1番最後のところですが、当該申請のあった日の属する月の翌月からの給付ですけれども、4月に当該申請した場合に4月の翌月としたら5月ではないのか。
(事務局)本来であれば、翌月ということで5月に申請があった場合は6月に支給をはじめるということになるんですけれど、基本的には入学児童については、もう一度4月に申請の方を行なっていただく、改めて申請を行なっていただく必要がありますので、本当でしたら4月から支給が必要な対象者がおりますので、4月の申請につきましては4月から支給できるようにとカッコ書きで4月についての申請だけ改めてちょっと書かせていただいているような状況になっています。
(事務局)要綱改正につきましては、基本的には簡単に概略を申し上げますと、いわゆる入学に係る学用品については、前年度の対象者にお渡しをしているということでございますので、先程も言いましたが、3月の中ごろ位には、特に来年度小学校に入学を予定される方について、もうすでにその時点でお渡しさせていただいております。あくまでも入学は30年度の4月ですけれども前年度の29年度にその事業をおこすと、そういう形の中で今回それに見合う例規の改正をしていく。中学生につきましてはもうすでに今現在、対象となっておりますので、今対象の現在6年生の児童に対して中学校の入学の学用品をお渡しするというような形になっております。ですので、新たに手続きをいただくということになりますと、来年度入学を予定されている児童の保護者の方から申請をいただくという形です。
(委員)スケジュールの事で聞き洩らしたかもしれませんので、教えてください。1月26日で締め切りをされて、それまでに申請をされた案件について2月で委員会の中で認定の作業をされると。3月の中旬には支払該当者が確定して支払い手続き、銀行振り込みが行なわれると、こういう理解なんですけれども、その時にちょっと分からないのがですね、改正案の第5条の所で毎年度とありますが、これもスケジュールとしては年間で1月の申請の時期1回限りというようなことの意味合いですか。申請をするタイミングは年に1回ですか。
(事務局)この新入学児童学用品費等につきましては、この2月に認定作業を行ないます。そのあと本来であれば今、在学中の児童・生徒につきましても毎年度申請の方をしていただくというような形になりますので、これについては今年度中に申請を出していただいて、翌年度認定をさせていただいて4月からの支給をさせていただくというような形になっておりますので、この新入学学用品については、今言わせていただいた2月認定になるんですけれども、また今の在校生につきましては一度にというとちょっと事務的にも難しいので、時期を少しずらして認定させていただいて来年度の支給に間にあわせるようにしているというような状況です。入学した後にもう一度申請をしていただきますので、対象者小学校1年生につきましては、4月にもう一度申請書を出していただいて改めて認定作業をすると。おそらく認定については、要件はほとんど変わらないのですけれど、今年度につきましては所得を対象にしていますけれども、来年度につきましては29年度の所得です。29年度につきましては28年度所得を基準に認定しているんですけれども、来年度になりますと29年度の、本年度の所得を対象にしますので、対象が変わってくるという事もありますので、改めて新1年生につきましては2月に認定作業を、本年度についてはしているんですけれど、改めて来年度4月から支給できるかどうかについてはもう1度認定作業をすると。来年度4月に、というような形に。
(委員)手続きとしては理解できました。そのことについてですけれども、その申請をする親御さんの立場からすると1月の段階で申請されているにも関わらず、また4月に入ってから4月の色々バタバタ忙しい時にもう一度申請をしないといけないというのは、それなりにご負担ではないかなと思う次第ですが、手続き上はその所得をベースにしている支給だからということかもしれませんけれども、決定認定自体は前年度29年度について28年度所得でのベースで2月にはもう認定しておられるわけですから、4月でひっくり返るお話でしたら何ですけど、ひっくり返さないんであればもう一回なぜ申請手続きをされるのか、親御さんの立場からすると非常に不安でもあり、なぜ2回も重なるように申請しなければならないのか、ちょっと理解できにくいんではないかと思うんですけれど、そのあたりいかがでしょうか。
(事務局)委員のおっしゃっていただくことは非常によく分かるんですけれど、これはどこかで線を引かなければならないという事で、要綱の方にも前年の所得ということで、ここにはない改正の案のところで前年所得で、あくまで学用品、入学に係る学用品費においては特例措置で、前年度にお渡しするということになります。それ以外のものについてはあくまでも30年度の事業という形になりますので、前年29年度の所得を確認をしてお渡しをさせていただくということで、その作業がどうしても要綱からしてもやらざるを得ない状態。確かに不安になるという気持ちはわかるんですけど、やはり所得は少しずつ変わっていきますので、特にその所得でやる1.2以内ということもちょうどすれすれの線におられる方については、28年は極端な話300万やったのが400万になって対象外になるというようなことも考えられる、どうしてもそういうような中で、再度30年4月以降にその作業が必要になってくる、その分についてはご理解いただけるように説明をしていく必要があると。
(委員)はい、だいぶ理解が進みました。第4条の第1項の(1)~(7)の中で(7)の所だけが前払い、特例扱いということからこのような2段階措置になったと。(1)~(6)のところにつきましては、その今年度ベースの所得での要は30年度においては29年度ベースになるので、新年度の児童さんにおいては2回というようなことになるんだと。そういう理解。
(事務局)そうです、そうです。
(委員)承知しました。はい。理解できました。
(教育長)今までやっていた所の他は何も変わりなくやるわけですが、新たにこの国なり或いは議会等の要望も受けた中で、入学時に多額の経費かかるからその負担をできるだけ早く減らすのがよかろうというので、4条の7項を作り、そのための手続きを早くやるというふうな解釈で、今まで、例えば4月に申請して6月の終わりに渡した分の中で、新入学に関わる分のことについてのみ年度内に前年度内に渡すというために諸手続き、申請を上げてもらって審査をすると、こういうことでいいわけですね。
(事務局)はい、そういうことでございます。はい、ここだけ、先程言いました新入学云々で抜き出してということです。
(教育長)はい。わかりました。
(委員)はい。もう1点教えてください。第5条の第2項、第3項で、中ほどから委員会が指定した書類を添付してとあるのですけども、どのような書類なんでしょうか。
(事務局)就学援助申請書ということで様式を定めております。この就学援助申請書っていう、それぞれ毎年書いていただく申請書があるんですけれども、それを改めて作らせていただいてありますので、保護者の方に書いていただいているというような状況です。
(委員)文言では就学援助申請書に委員会が指定した書類を添付して、となっていますが、そのことをお尋ねしています。だから添付書類が多ければ、保護者の負担も大変なので、そう意味も含めてどれぐらい大変なものかなという事を知りたいがためにお尋ねしております。指定した書類が毎年変わるとは思うのですけれど参考に教えてください。
(事務局)添付書類につきましては、この就学援助の対象となる要件というのが色々ありまして、児童扶養手当を受給されている方につきましては、児童扶養手当の受給者証のコピーを付けていただきます。あとはその種目の部分ですけれど前年度の収入という、今年度につきましては28年度の所得というのは市のほうで把握していますので特に必要がないんですけれども、来年度の4月にまた申請していただくときについては前年度の所得がわかる源泉徴収票等のコピーというような書類が添付書類としては考えられます。申請理由としましては、生活福祉資金の適用を受けている世帯の条件もありまして、その場合は社会福祉協議会からの決定通知書のコピーであったり、失業対策事業適格者手帳を有する者の場合は手帳のコピー等が添付書類として考えられるところです。
(委員)はい。これを申請する方に何がどういう書類をという一覧になったものをお渡しになっておられると思うんですけれども、該当しない者がある場合は、これは申請できないわけでしょうから、今おっしゃったような源泉徴収票というのもない方もおられるでしょうし、非常にそのあたり明確な指示がある方がよろしいんだろうなというふうに思います。ちょっと今の説明では私がもし申請しようとしたら非常に不安に思いました。それから市の方に書類を出す時に児童関係の書類を市の方に出される方も、平日就業時間と言いましょうか、平日のお役所がやっている時間にしか受け付けてもらえないと。これは何かと大変提出しづらいというような事情もあるんですけれど、そのあたり市の方ではどういう対応をされているんでしょうか。やはり通常の勤務時間といいましょうか、なかなか特殊事情のある方について、特殊な受け取り方ができるのかどうか、そういうあたりいかがでしょうか。
(事務局)添付書類につきましてですが、就学援助の申請書のほうに添付書類は明記させていただいていますので、こちらを確認していただくような形になります。あと、この就学援助の申請書につきましては、教育委員会に出していただく形と学校を通じて出していただくという方法もあります。その中で又保護者さんから書き方等わからない場合も教育委員会へ連絡入ってきたりしますので、そこは柔軟に対応しているところです。
(委員)この改正については、今の説明で理解できました。この機会に教えていただきたいんですけれども第4条の援助の種類について見せていただいて、実際入学するとなると小学校では制服のある学校、制服のない学校があるんですが、制服についてはここ該当するところが見当たらないというのと、中学校でも自転車通学をする方もいらっしゃる場合、自転車の購入に対してはここには該当しないようなところもあるんですが、そのあたりは具体的に現状としてはどのような取扱いになっているか教えていただきたいと思います。
(事務局)今回の新入学児童生徒の学用品費等ということで、これは文科省が出している言葉になるんですけれど、この「等」の中には学用品プラス通学に係る用品も含まれてくるというような中ですが、名張市の場合ですと遠距離通学の補助というのがこれとは別にあります。例を挙げますと中学校、梅が丘等から自転車で通われる子どもについては、通学するために買ったという領収書をつけて、学校を通して申請していただくとその自転車の購入費を補助したり、そういうのは又別で用意してあります。
(教育長)よろしいか。他どうですか。ちょっと私から何点かですが、1番大事なことはこの7番ができてですね、今まであるような援助費プラス7が入ったと、上乗せされるということのないようにしていかないとというふうに思います。今まで、これまで援助の中で今、委員さんがおっしゃってくださったことが全部含まれているわけで、それらも時期は遅くなりますけれど一定渡していたと、今まで6月の末に渡していたと、例えばですけれど5万円渡した分を入学時に必要な額だけ渡してそのうちの3万だけを先に渡しますよと。そのことを申請される方については何月何日までに出してくださいと。そうすると3月中旬には振り込みをさせてもらうと。こういう解釈ではないかなと思うんですけれども。そのことを間違いのないように、分かりやすくやっていただくということと、それから受益者の立場にたってですね、考えていただくような手だてをとっていただく。こういうことでどうかなと思うんですけれども、こういう解釈でよろしいでしょうか。
(事務局)はい、結構です。その新入学の分だけ抜き出して、前年度に置き換えるという形で準備をすすめております。今の考え方でいきますと2重払いになるということはまずない。基本的に、委員もおっしゃっていただきましたが、どんな方でも毎年度申請をいただきます。基本的にはチェックをさせていただきまして、まず対象か対象にならないかチェックをさせていただきます。ということですので、今回新入学の分だけはその分だけ先にチェックさせていただきまして、翌年度また新たに今年でしたら30年度に新たに申請いただく、それ以外のものについて支給をさせていただくというような形です。
(教育長)ということは、今回のことは入学前に申請をしていただきたいという人にのみ申請をあげてもらって、それに必要な添付書類はそれに合った中でだしてもらうという形の中で従来やっていったことについては、それはありますよということ。従って入学前に修正しなかったらもらえないけど、後で修正したらもらえるのだったら、後でもいいというのだったらしてもいいんですか。必ずその時点で事前にしないといけないのですか、後になってもいいのか。
(宮本)2月の時点で出てきた分については、認定させていただきます。そのあと4月にもう一度申請のタイミングがありますので、その時に新入学の用品費。重ねては当然だせないんですけれども2月に申請を忘れていた方や、また、3月に引っ越してきて、その申請が間に合わなかったけれども、新1年生で対象になるという方については、4月に申請いただいたときにもう1度認定作業を行ないます。その時に払っていない対象者については4月に認定させていただいて学用品、新入学児童生徒学用品についてもお支払いをさせていただく予定にしております。それと2月に新入学の形で申請していただいた対象者については4月になった時点で、もう1度申請をしていただくんですけれども、抜け落ち、申請で認定されていた方が申請していない場合については、学校の事務の職員さんや担当が連携して、申請のしわ寄せがないように連携をとっていこうということで、担当者と学校事務の先生とで打合せをして、抜け落ちのないようにというような形で考えております。
(委員)はい、大変抜け落ちがないようにということで、色々ご配慮いただいていることだと拝察いたします。是非ともそのようにお願いしたい次第なんですが、そういう面では最終2月で申請を認めていただいたあとで、また4月でもフォローアップといいましぃうか、拾い上げていただくというような2段階ということでは、非常によくやっていただいているものだと思いますが、学校側としましては学校で受け付けるといったときに児童生徒さんの、保護者の方がこの第3条にここの交付対象となるものというところの、第1項第2項の中で非常にこういう色々なご事情があるということが拝察されるような立場におられる方、非常に脆弱な立場におられる方のことを鑑みますと、申請をする側からしますと、子どもの事を考えると学校側、ましてや担任教師にこういうことをあんまり知られたくないというか、そういうふうな思いをするのではないかなと思うのですけれども、そのあたりは通常はどのような連携をされているんでしょうか。要は学校担任がこういうことに全面的にコミットするのか、それとも先程おっしゃられたような学校事務の方から保護者さんの方に連絡というような形でなさるのか、それによっても教師が、クラスに子どもをそういうふうに見ないこともないといいましょうか、ちょっとそういうようなこともきっかけになるような気がしまして、そのあたりの手続きといいましょうか、そういう流れも少し教えていただけませんでしょうか。
(事務局)この就学援助の申請につきましては、あくまで申請主義ということで今、委員さんがおっしゃったように知られたくないという方も恐らくいないとは言えないと思いますが、こちらで全員を把握している現状には至っていない状況です。全児童生徒の保護者さん宛にこういう制度がありますというふうな通知をさせていただいて・・・。
(委員)それはいつ頃その通知をだされて、どういう形式で出されるんですか。正確に教えてください。
(事務局)毎年度2月頃に学校を通して保護者さんに通知をしているというような形です。今回の新入学児童生徒学用品費等につきましては、就学予定者については12月の20日頃に申請書類、口座振替の用紙等、全部あわせて通知させていただこうと現在考えております。該当者につきましては2月頃に保護者さん宛に就学援助の資料をこういう制度があるということを全校配布していただくという形です。
(教育長)ということは、今までの事でいきますと、在学している児童生徒の場合は学校を通して就学援助の制度はこういう制度がありますよと、申請される方はこうしてくださいとかいう案内の文書は全部の在籍している子どもたちを通して家庭の方に配布すると、そこから申請をあげてもらっているということですね。今度新しく入る子については学校で渡すことができないから、小学校1年生の子については郵送ですか。
(事務局)対象者全員に郵送で配布というような形です。就学時検診が11月にありますのでその時に配布するという方法等も考えられるんですけれども、本年度につきましては12月補正が認められた後での業務になりますので、今年に限っては郵送で対応させていただきたいと。来年以降につきましては、もう少し経費のかからない方法も考えながら全員に配布できるように体制を作っていきたいと考えております。
(教育長)一旦は全部の児童生徒を通して保護者の皆さん方に制度の主旨を伝えると。そして申請されるんであれば、あげていただく。そして今年度は新入学時の学用品等々が新たに入ってくるので、これはまだ議会を通ってないから補正予算が通った段階で本年度に限り郵送する。次年度以降は別の方法も考えながら徹底することでやっていこうとこういうことですね。
(委員)今の事と同じことなんですけれども、12月20日に申請書類を各家庭に送付されるという事は、年末の忙しい時期にかかるタイミングでもありますし、1月21日までに締切という事は1か月で、市役所側としてはそういう1か月の準備ということでしょうけれども、年末年始をはさむことから考えますとちょっと短いというふうな市民感覚があります。それから子どもさんがいる家庭で封書に入った書類が送られてきて読んでそして、それを理解して書類をそろえて、それをまた市役所に持って行ってというのは至難の業なんですよね。もっと簡便なやりかたを工夫していただけないかなということを思います。例えばヘルプデスクを明記していただいて、そこに電話をかけてすぐ相談してくださいというような流れや、普通のですね、字の大きさの郵便をですね、小さな子どもさんのいる家庭に送っても書類を見る暇がありませんので、ちょっとそのあたりももう少し配慮いただけたらなというふうに思います。
(事務局)この就学援助の制度につきましては、名張市の広報等でもこういう制度があるということで、知っていただく機会を設けるようにはしているんですけれども、それが完璧かどうかと言われるとなかなか完璧とは言い難いこともあります。就学援助制度を、広く知っていただく機会についてはさらに考えていきたいと思います。
(教育長)重ねて期間が短い、また大量の資料の中身ということになってくるので、分からない方もおっていただけると思うので、今言った相談窓口、ヘルプデスクなり色んな事も考えてもらって、やはりきちっとそんな制度が活用できる、したいと思っている人には行き渡るようにですね考えていただくという事がいいんではないかなとこういうことです。他、どうですか。細かい事ですが、改正理由の就学援助を求める小学校入学前の就学予定者。これ中学校もそうなのと違うのかな。
(事務局)中学校は就学予定者とは言わない。小学校義務教育の間だけで6年で認定します。ですので中学生にも対象で渡すということなんですけれど、今回の一部改正については、あくまでも義務教育に入る子どもさんのために今回要綱を改正することになりました。基本的には中学生の方も対象として渡すんですけれど、要綱の改正については特にそこを意識して改正しました。
(教育長)実際問題、新入学児童生徒の学用品等を前倒しということは、中学校へ入る子も対象なのだからこの言葉じりを、もうちょっと適切に使ってもらったらいいのでは。
(事務局)これはあくまでも要綱ですので、当然ご案内の時には中学校の方にもご案内させていただきますけれども、ご案内というかこれは実際今6年生で対象になっている。前年度ですので、今の6年生は自動的に申請してもらわなくても大丈夫、お知らせしているという形です。
(教育長)それも申請があがってきた者だけではないのか。
(事務局)今現在、小学校6年生については認定してありますので、その認定されている人を対象に中学校へ上がるときの新入学児童生徒学用品について、認定されている人には支給するという形です。
(教育長)というということは中学校入る子は入学前にいわゆる、今まで渡していたものをという形でなくて分割で渡すということか。
(事務局)そうですね、分割になります。もう一度30年度中学校上がった時には学用品、学用品以外の分で改めて申請していただくということ。
(教育長)他よろしいでしょうか。この件につきましては承認という形でよろしいでしょうか。
(委員)はい。
(教育長)それでは第17号は以上で。続きまして第18号第三次名張市子ども読書活動推進計画(素案)の確定についてを議題とします。
第18号 第三次名張市子ども読書活動推進計画(素案)の確定について
(事務局 説明)
(教育長)はい。説明が終わりました。委員の皆様方から何かご意見ご質問等をよろしくお願いします。
(委員)8ページのところ2.人的体制の整備というところで、現状の課題の4行目のあたりちょっと教えてください。現状は授業や学級経営等により学校図書館活動を指導できる期間は限られていますということですが、現状どのような授業それから学級経営等との連携を学校図書館ではやられているか、そのことについて状況を教えてください。
(事務局)ここにかいてある現状というのは司書教諭のことで、司書教諭の場合その資格を持った者が学級担任をしていたり、それから専科の授業をしていたりとか、授業等の中で専門的な技術を使って授業をするということは考えられますが、すべてのクラスっていうのはなかなか回らない。現実、図書館を利用しているという中では現時点では難しいところでございます。それを学校司書、教育センターに配置しております学校司書が学校を巡回していくなかで、授業の中に入ってというふうに、学校司書は司書教諭、又担任と協働しながら授業をするというパターンがございます。ただ現状としてはそんなに多くはございません。あくまでも学校の授業は時間数的なものもありますので、なかなか難しいところもございますが、実際にやってございます。
(委員)どの小学校、どの中学校で何日何時間というようなことは、把握はされていますか。教育センターの学校司書さんが各学校を回られていて、サポートされる、支援されるという活動にどれくらい従事されているか。その実績を把握されていますか。
(事務局)現在、4名の学校司書が名張市の小中学校を回っているんですけれど、時間数的に週当たり60時間になっています。60時間を4人で回っているという形になっています。
(委員)回って何をされているんでしょう。教えてください。
(事務局)授業の中に入るっていうのも1つですし、それから学校図書館の環境整備、図書の整備であったりとか、子どもたちが読書意欲がわいてくるような、興味関心をひきつけるようなポップアップを作ったりとか、推薦する本を子どもたちが図書館の中で読みたいなと思えるような工夫をたくさんしていただいたりとかしています。この二次から5年で学校図書館も随分かわりました。本当に明るくなり、子どもたちが自分から読みたいなと思うような工夫を、どの学校もやっているのは成功したなと思います。
(委員)今のお話を伺いますと、確かに変わったというお話。それから以前も他の委員さんの方から学校の図書館の雰囲気も明るくなったと、学校訪問の時の感想でも伺っていますので確かにそうだろうと思うのですけれども、実際にはやはりどの司書さんがどういうふうに回っておられるかと、それから何をしたのかという細かな記録というわけじゃないんですけれども、何かですね、実際何をしているのかということがわかるような形で、ご教授いただけるようにしておいていただいた方が良いような感じが致します。今回のご提案を色々見ている中では、なかなかそこまで想像がつかないです。実際に9ページの貸出密度というようなことで、でてきたパフォーマンスで見ると、成果があがっているというようなこともいえますでしょうし、こういうパフォーマンス以外のものも何か本を借りなくても訪問した児童生徒の数が増えているとか、何か測れる指標みたいなものがあるといいんですけれど、ただあんまり指標を作るとそれが独り歩きしてそればっかりになってしまいますから、それも善し悪しかと思いますが。中学校での年間の0.4冊増えたと0.8から1.2くらいに増えたと、これ読んでいるうちに入るのかなという気がしないでもないので、司書教諭さん、学校司書さんがどれだけコミットして協働されているのかっていう、本当は上手くいっている話だけじゃなく、どういうことが課題かということを現場の教員レベルでどんな話をしているかっていうところもお聞かせいただくほうが本当の話じゃないかなという気もいたします。ちょっと人との関わりっていうのが、もうちょっとこの計画の中からあんまりピンとくるものがないなという私の印象なんですけれど、いかがでしょうか。
(事務局)60時間という、かなり限られた時間の中でかなり細かい作業からやっていただいています。例えば各学校の図書担当者が名張市の図書担当者会をやっておりまして、そこの担当者会で出てきた意見だとかそういった部分を、教育センターで集約しながら学校図書館に何が必要でこの学校にはどういったことに力入れていかないといけないかとかを連携しながら行っています。さきほど、その授業についても入っている所もあるんですけれども、なかなか入れない所ももちろんございまして、課題となっている所、どういった授業の入り方がいいかっていうのもなかなか難しい所もございます。そういう部分についても、時間数の関係や、それから学校司書を学校側のどういった取り入れ方をしていったらいいか、学校側の部分の課題もあります。そういったことも含めて、今ある今の条件というか、環境の中でできるだけのことをやっているというのが現状ではございます。先程中学校の貸し出しの話がありましたけれど、これも課題になっておりまして、実際貸出率だけならこれになるんですけれど、中学校の場合でしたら読書活動を学校もやってくれているんですけれど、例えば図書館で借りずに家から持ってきた本を中心に見ているっていうことも多かったり、その辺は図書館の方も魅力的にやっていかないといけない。そういう課題もございますし、色々多岐にわたっています。ただここの計画にもございますように、限られた予算の中で新刊本っていうのは毎年ちゃんと各校に配布できるように維持していくっていうこと、それから児童生徒の方からどんな本を読みたいといったアンケート調査をして、学校でどういう本を持っていたらいいか、そういう仕事も学校司書も入ってやっている。
(委員)だいぶ具体的にイメージがついてきました。
(委員)10ページのところに、数値目標として1日あたりどれくらいの読書時間をということで、30分以上と回答する児童生徒の割合という事で目標を立てていただいているんですが、よっぽど読書が好きな子じゃないと30分以上集中して授業時間以外に本を読んでいるという事はまず考えられないなと思うんですね。できればこの学校の授業時間というのは、調べ学習とかそういうので図書館を利用したとか本を利用したとかいうことに当たると思うんですが、できれば学校の中で、月に1回なり2回なり読書の時間という項目を取っていただいて、集中して本を読むという時間をとるようなカリキュラムを作っていただきたいなと思います。それに伴って例えば週や月にどれくらい時間を取ることが、学校教育室では必要と思ってらっしゃるのかお聞きしたいということ。それから12ページの児童サービスの担当司書を配置していただいているということなんですが、これは市立図書館にいらっしゃるということですね。私よく図書館に行かせていただくんですが、先日も図書館に行ったら保育所の子どもたちが遠足の途中で訪れていました。滞在時間15分位だったんですが、それぞれみんな好きなところであっち行ったりこっち行ったりがやがやしているような状況で、もうそしたら帰るよっていうような形だったんですね。もしこういう方がいらっしゃるなら、子どもたちを集めて例えば図書館はこういうふうに使うんだよとか、紙芝居を1つ読むなりして、みんなにそういう絵本に親しむ時間をとるとかそういうこともしていただけたらよかったのかなというような印象を持ちました。後の方が要望でその先の、学校としてはどれくらい週、月として必要と考えていただいているかお聞かせください。
(事務局)はい、必要っていうことでいくともちろん必要ですけれど、実際のところ教育課程の中で読書だけに集中してっていう時間はなかなかとれないと思うんです。学校によって今、現状としては、長いところだったら15分、学校のなかで一斉に15分くらいの朝の読書時間っていうのを設定している学校もあれば、10分というところもあります。それが適切かと言ったらもうちょっと本当は子どもたちに時間を取りたいっていう子もいれば、なかなかその10分が厳しい子ももちろんいます。その中で学校としては毎日ただ読書に触れる、本に触れるという時間設定はしていただいていません。
(委員)おそらく委員さんがおっしゃられたのは、そういう各学校の活動を更に促進、確定していただくためにも、それなりに目標をもって時間を定めたり学校ごとで成果を披露しあっていただいて、切磋琢磨していただくようなこともひとつあるんじゃないかなということも思う次第です。それから私も要望なのですけれど読みなさいと言っても読まないですし、行きなさいと言っても行きません。そういう面では非常にご苦労なさっている、苦渋なさっていることも重々拝察するのですけれども、それでも学校の活動の中で時間だという事でひとつ決まっていれば、だいぶ違うんじゃないかと思う次第なんです。これ大学生でも同じことがござまして、何でもどんな本でもいいよというと本当にどんな本でもあてはまってしまうんですね。それも本かなと思うようなものまではいってしまう。そうではなくて良い本に当たらせるという指導も大事なんじゃないかなと思いまして、私の方ではなるべく指定図書を、期限をきって集中させて読ませると、もちろん感想文も書かせるということでインプットだけじゃなくてアウトプットの機会も設けるようなそういう活動の中で読書をすると、学生が言うにはこういうことでもなかったら図書館にも行かなかっただろうし、本も読まなかっただろうという子が多かったんです。大抵そんなことなんだろうと。それでそのあと読むようになったかどうかは別なんですけれど、各学校ごとでそれぞれ学校要覧の中に入っているのかもしれませんが、図書計画の中のそれぞれ時間ですとか、活動計画みたいなものもおありでしょうから、そういったことと有機的にこの活動が整合していくといいなというふうに思う次第ですけれど、いかがでしょうかそのあたり。
(事務局)どの学校も読書時間については設定してくれている。その中身は例えば学年によってもちょっと違っていて、例えば低学年であったりすると読書ボランティアの方に来ていただいて読み聞かせをしていただくときもございますし、高学年ぐらいになってくると例えば割と長い小説なんかを日を分けて例えば1週間なり2週間かけて、読書時間10分間位15分位しかない時間を使いながら続きまた明日みたいな形でやっていったりすることが多い。あともう1つ良い本をという部分では学校司書がブックトークをして、進めていることもございます。子どもたちが本の紹介をし合ってというような形で読んだ本をというような部分もあると思います。ただ先程言われていたアウトプットの部分という、読んでどう考えたかっていうことを書いたりするっていう活動については、そこまで時間を取っていないと思います。アウトプットすることで思考が深まるというか、力がついてくるということは本当に大事なことだと思いますので、その時間じゃなくてまた違う形の使うところに時間をとるとかするというふうな部分の課題としては思っているんですけれども、ちょっとそこらへんはそこまでは取組めてないとは思います。
(委員)はい。今2名の委員さんのご意見とまた重なるところもあるんですけれども、第3次の計画全体としては第1次、第2次を踏まえてということで、素晴らしいものだと思っております。ただやはりこの中の小中学校における読書活動の推進、これ計画という意味では問題はないんですけれども、中身がとても大事になってくると思います。それで、この中にも書かれているように学年ごとで学習内容に応じてということなので、それぞれ中身がちがうというのは前提になっているんですけれども、そのあたり小学校と中学校 少し区別して表現してほしかったなという感想を持ちました。小学校はボランティア体制など又子どもたちも本に親しむっていう部分があるので取り組みやすい、時間も取りやすいと思いますが、中学校は部活もある学習内容も大変高校受験もひかえるということで、本を読めと言っても実際本を読む時間を取るのは難しい現状がある中で本を読むようにもっていく目標の数値も出しているということにあたっては、もう少し何か具体的な指針になるものを中学校向けのものも用意してほしかったなという感想を持ちました。ただこれは指針としてしっかりあるのでそれをどういうふうにして活用いていくかという事が大事だと思うので、各学校そのあたり教育センターや学校教育室も合わせてまた充実していっていただきたいと思います。でもう1つ。ボランティア活動の件なんですけれども、小学校は地域の方が朝の読書活動をしていることを耳にするんですけれど、中学校では地域の方などのボランティアの活動は具体的にはどんな例があるのでしょうか。教えていただきたいと思います。
(事務局)現在、学校図書ボランティアっていうのは中学校は今はいないです。2年前は5人くらいの方が入っていただいたんですけれど今年は中学校は読書ボランティアはいないです。
(委員)はい。ありがとうございます。1つ続けて感想言わせていただきたいんですけれど、個人的な感想なんですけれど、この前提の中で図書の提供の機関として移動図書館のことも記載があるんですが、図書館協議会に出ている中で聞かせていただいている中で、名張市のやまなみ号の活動に高い評価をいただいています。これもすごく充実して活動しているのであえてこれ以上のことを書くことがないからだと思うんですけれども、逆に言うと充実したものはこの5年たっても更に充実、質が落ちないような努力を更に続けていただきたいなという感想を持ちました。それと電子図書についての記載もでてきているんですが、5年の間に今よりも更に電子という媒体が割合や質が変わってきてもっと世の中に浸透してきて、本と今の紙の媒体と電子と競合するような部分もあるかと思いますけれど、本を読んで理解してまた発信するという事については違いはないのでそのあたり、またこれは第4次につながっていくかと思うんですけれども、この5年の間にかなりまた見方が変わってくるという事を踏まえて進めていただきたいと思います。以上です。
(事務局)第4次に向けたそういった雰囲気で私達も意識しておりますので、確かに電子書籍の動向というのは本当にこれから先どんどん変わっていく可能性もありますのできちんと注視して、読書の形態というのが確かに紙のものだけではない今の世の中ですので、そこらへんを意識しながら今後活動等を続けてまいりたいとそういうふうに思っています。
(委員)今のご質問の中で、中学校の読書ボランティアはどうしてなくなったんでしょうか。教えてください。
(事務局)ちょっとはっきりしたことは、理由は把握しておりません。ただ中学校の読書時間をどの学校も設定されて子どもたち、朝の読書っていうのをやっているんですけれど、中学校の場合読み聞かせとかいったことはないのかな、あまり。だから読書ボランティアに来ていただくのは読み聞かせっていうのが多いんです。あと学校図書館の環境整備を手伝うみたいな形で手伝っていただく方もいらっしゃるんですけれど、以前はそういった方もおるんですけれど、以前はそういった整備の方に来ていただいていたことがあったのかなというふうに思うんですけれども、今読み聞かせっていう部分ではないのかなというふうに思いまして、ちょっと私の方でその辺は把握できておりません。
(委員)今までずっと聞かしていただいていて感想だけです。3つほど言います。1つは今、委員さんが言っていただきましたが、うちは孫が2人、5年生、6年生がおるんですけれど、比奈知にやまなみ号が来てくれています。ものすごく楽しみにしています。この間、学級懇談があったときに子どもは先に帰れって言われた日に「やまなみ号が来るので僕はそれを待たな、頼んであるやつを是非借りて帰らなあかん」とバスを遅れてでも待っていました。それくらい楽しみにしています。それで非常にいい活動だと思わせてもらっています。2つ目ですが、学校での子どもの読書活動で、学校の授業時間以外で普段云々とありますが、子どもは非常に忙しいです。小学生も。この中で、多分学校の中で読書の時間は大事なことですけれども、まとまっては毎日はとれないのではないかなと。事務局も言ってくれましたけれど、朝の15分、20分でも毎日読書はできないと思います。学力充実のために算数の勉強、計算問題、漢字の勉強等。今度1時間の時間数も不足し、英語を帯でとるとか言っていると、する時間がないと思います、多分。やっぱり体力もつけないといけないので、子どもを昼間は遊びに行かせる、休憩時間は外へ行くようにと言わなければならない。することがいっぱいある中で、いいことですけれどこれだけに特化はできないのと違うかなと思うのですけれど。子どもはどこで読書時間をというと、家へ帰ってしないとしょうがない。しかし家へ帰ってもスポ少がある、塾がある。特に中学校になったら、もっと家での学習時間が増えて、本当に本を読む時間がないようになると思います。本を読むのが孫は好きみたいで、隠れて読んでいますけれども、それぐらい好きなものと嫌いなものとでてくるんで、まとまってというのは非常に難しい。特に学校ではまとまった時間をとれないのではと。子どもは非常に窮屈になってくるなというふうに思います。それから3つ目ですけれども、これも子どもの話ですけれど、娘は今転勤で米子に行っているんですが、米子へ行ってびっくりしたことは本屋、図書館がすごい満員でなかなか行けないというんです。この辺とえらい違いやと言っていました。今も本屋へ行けば結構人はいますけれど、子どもを連れて、赤ちゃんを連れていけるような状況にないようなことを言っていました。山陰の方はもっと本を読む人が多いんだなと、その時感じたんですけれど。そんなことを思いました。
(教育長)司書教諭あるいは学校司書、ボランティアが何をするのか、もっと明確にやっていかないと、全部おまかせにしてしまうことはどうなのかなと。何のためにこの読書活動をやっているのかと考えた時に、司書がどういう役割をするかっていうことをもうちょっと明確にしないといけない。ボランティアにしてもそうですけれど、読み聞かせをするためのボランティアなのか、人はなぜ必要なのか、図書館に行った時に誰かいてもらうのと、おらへんのでは全然違うという、そういうことの中で、行った時にその人に聞いたら教えてもらえるとなったら、その人も図書室にいて、図書館の状況も把握しないとできない。学校現場も校務分掌に位置づけられている司書教諭というのを置いてありますけれど、その人と学校司書との関係はどうなのか、ボランティアとの関係はどうなのかということをちゃんと把握しているのかどうか問われてくると思いますので、担当としてきちっと把握をして、適切な指導をしていってほしいなと思います。この件について、よろしいでしょうか。はい、それでは、第18号につきましても承認ということで、受理させていただきたいと思いますが異議ございませんか。
(委員)異議なし。
(教育長)はい、それでは承認という形にさせていただきたいと思います。それでは3.その他の所に入っていきたいと思います。順番にこのまま進めていきたいと思います。(1)義務就学者の就学校の変更についてを議題とします。
議事(3その他)
(1)義務就学者の就学校の変更について【非公開】
(事務局 説明)
(2)児童生徒の問題行動について(9月分)【非公開】
(事務局 説明)
(3)平成29年度全国学力・学習状況調査の結果分析と公表について
(事務局 説明)
(教育長)説明が終わりましたが、委員の皆様何なりとありましたらお出しください。ちょっと私から言わしてもらうと、これ今年度で10回の全国学調が行われたわけですけれど、やっぱり10回ひとくくりという形の中では、きちっとした経年の変化、更には統計で見た時に名張の小学校、中学校あるいは教科はどうなのかということについての分析とした中で、それらをきちっと保護者の皆さん方なり地域の皆さん方に発信をしていくべきだと思います。その1つの方法としては、今度の教育フォーラムの中で発表していただけるような資料を作っといてほしいなと思うところです。やはり一定その10年というスパンの中でどうかということの名張としての取組の成果なり課題なりを出さないといけない。そしてやはりこれからの学校教育は学校でやるべきことは学校でやり、学校でできないことについては保護者・地域の協力を得てやっていこうということになっているわけですから、名張としては学力をどういうふうにとらまえてやっているのか、さらには将来見据えてどういう力をつけていこうとしているのか。それには学校としてはこういう形で進めていきたい、そして協力支援お願い等、家庭地域の皆さん方にもわかるように、発表出来るようにしていっていただきたいなと要望でございますがよろしくお願い致します。忙しい中ですが、毎年分析をしてもらって非常にありがたいことですけれど、それについては国なり国研(国立教育政策研究所)なり、名張市の取組について評価をしていただいている所が多いわけです。取組とか分析だけでなく少しでも前進をするということが大事なことではないかなと思うので、教育委員の皆さん方に読んでいただいて、又わからないところは担当の方に聞いてもらったり、或いはご意見でもって、是非とも伝えていただければありがたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
(委員)大変丁寧にまとめていただいて、わかりやすく作っていただいたと思います。ありがとうございます。ただこれを進めていっていただくには、指導主事の先生方が学校に入っていただいているという事なんですけれど、この成果がどうやったのかということが1年後のこの学調では違う学年の子たちが対象になるわけですよね。この子たちに今受けていただいたこの学年の子どもたちが成果として次年度また例えば6年生の子どもたちが次3年生になったら結果がでるわけですけれども、どういう成果があったというところをわかるようなことも教えていただけたらなと思う事と、それと魅力ある学校づくりわかる授業づくりっていうのをよく言ってくださるんですけれど、私としては子どもが興味をもって1時間楽しかった、あっという間に終わったねっていうようなそういうような授業をしていただくと、又子どもたちも理解できて更に次の事が知りたいというような意欲もわいてくるのかなと思いますので、是非子どもたちが興味をもって楽しく1時間を授業時間を過ごせるようなそういうような授業づくりを考えていただけたらなと思います。
(教育長)他、よろしいでしょうか。尚ですけれども、27日の月曜日定例の教育委員会の午後ですけれども錦生赤目小学校に文科省から来てもらって授業研究させてもらうようになっておりますので、教育委員の皆様も時間が許す限りご出席をいただけたらと思います。色んな現場をみてもらって、その雰囲気なりを知ってもらうとともに忌憚のないご意見いただければありがたいなと思っていますのでよろしくお願いします。それではこの件はこの位にさせていただきたいと思います。続きまして(4)未来へつなぐ学びの支援事業(学校図書館を活用した子どもの居場所づくり)の成果と課題についてを議題と致します。
(4)未来へつなぐ学びの支援事業(学校図書館を活用した子どもの居場所づくり)の成果と課題について
(事務局 説明)
(教育長)はい。報告が終わりましたが、何か皆さん方の方でご意見ご質問ありましたら。
(委員)この事業については、この冬休みとか以降も継続はあるんですか。
(事務局)本年度ですね、10日間を目途にということで、冬休みはかなり難しいということで、夏休みに皆さん設定されて10日間、一応この事業は夏で終わっています。来年度は当初予算で、地方創生のお金をいただいて続けてできるように努力します。
(教育長)夏休みは暑かったということで、冬はストーブもあるので、どうですかという声かけ位はどうかと思います。
(委員)今回、ボランティアの募集などの期間も短かったようなので来年度はそのつもりで準備したら、各方面もうちょっと繋がっていくんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。
(委員)課題の最後の文字ですが、居場所として本を読みに来る生徒は名中ではいなかったとございますが、生徒さんたちの活動中の様子は、調べものとか何か自主学習のようなことでございますでしょうか。
(事務局)本当、家で居場所がないので図書館へ来て、ここやったらほっとして行けるかなっていう感じの使い方ではなく、宿題をちょうどやれるとか調べ学習できるとか部活終わってからみんなとあそこでみんなで一緒に勉強しようとかそんな感じで使うので、中学校の方も意図的に折角この事業をするから先生にも呼び掛けて使っていこうよと協力して下さった感があるので、もっと自然に、これからですね地域の方がいてほっとできるような居場所も含めた空間になるには少し時間がかかるかなという話でございます。
(教育長)はい。よろしでしょうか。それではまたこれを参考に次につなげてもらえたらいいなと思います。続きまして(5)第60回名張市美術展覧会結果について文化生涯学習室からお願います。
(5)第60回名張市美術展覧会結果について
(事務局 説明)
(教育長)はい。委員の皆さん方何かご意見ご質問ありませんでしょうか。運営委員会というのはどういう事をするためにやるのか。あらかた他の伊賀市なんかはどうなのか。
(事務局)今まで名張市は審査委員会の方で各展覧会の要項等を決めてもらったんですけれど、そういった要項につきましても、運営委員会の方で実際。例えば開催の日時、開催場所、運営する先の出品の内容等、募集要項等につきましてもその運営委員会の方でご意見をいただいてそれを参考にしまして開催するということを考えております。
(教育長)その要項を運営委員会が決めるという事か。
(事務局)はい。そういうことです。
(委員)入場者数の一覧について教えてください。今回の美術展覧会に出展、応募された数との比較はいかがでしょうか。
(事務局)作品は今回128点でございます。昨年が140点でございます。
(委員)一昨年はいかがですか。
(事務局)平成27年度は162点でございます。作品に比例して入場者も減っているということです。
(教育長)なぜ作品が減ってきているのか、入場者も少ないのかということや美術展そのものの意義を、もっとしっかり考える場としてするのだったら意義があると思うのだけど、そこをしっかり考えてやらないと賞を増やしてもたいして増えてない形もある。県立美術館移動美術展のところは非常にたくさん来てくれ、県下でも他の市がびっくりするぐらいの人数が来てもらっているわけですから、市展なったら来ないのはなぜかそのこともきちっとした分析をしないと、せっかくこうやって多額の経費、期間、場所を使ってやっているわけですから。更には今、市民センターまつりに私も行かしてもらっていますが、そこに行くと結構素晴らしい作品もたくさんあります。それを美術展にだしてもらったらいいのになぁ思うのですけれど、出してくれない理由は何なのかな。審査委員会だけではなかなかできませんから、ちゃんと生の声をキャッチしてもらってというような努力もしないといけないのではないかなというふうに思いました。
(委員)私もそのように存じます。出展なさった方にアンケートを取られてはいかがでしょう。要は出展しにくい理由をいくつかあげていただいたり、出展したいと思われる動機をあげていただいたり、ということで原因分析にはいいのではないかなと思われます。
(教育長)それと表彰式そのものだけど、上の方の方は出席されるけども、入選とかなってくると来ない状況もある。位置づけ意識をきちっと踏まえた中でよりよいものを作ってほしいなと。毎年やっているから恒例のという形ではだめだと私は思います。
(委員)審査委員長をさせていただいているわけですが、今回につきましては、書道の部の出展が少なかったという事が1つの要因でもございました。それから今、委員がおっしゃっていただいた、出展された方にちょっと色々聞いてみてという中では、作品自体を作って下さっている方は高齢の方が多くございましてその作品を出展するにあたって、搬入が難しいという方、あと高校生につきましても学校のクラブ活動等にもお声掛けをさせていただいているんですが、先生がまとめて車で運んでくるというような学校もあると、そのあたりについてももうちょっと配慮してもらえたら、子どもたちも生徒ももうちょっと出すのと違うかなと。あと現に高校生、上野高校それから青峰高校の子どもたちが高校で展覧会をしてくださっているんですけれど、そこには本当に大作のいい作品もたくさん出してくれているということも実際にございますので、そういう搬入についてももう少し手助けができないかなというようなことも、次からやっていく運営委員会の方でも、そういうお声を審査員の先生方以外の先生方にお出しをいただけたらなというふうに考えている所でございます。
(委員)具体的なことは全く分からないんですが、搬入の時期が短いとか、時間が短いとかその時間帯が平日のほんとに9時、5時で搬入できないとかそういうようなことはないんでしょうか。
(事務局)今回の搬入につきましては金曜日の3時から夜の7時まで。ただ土曜日がふれあいの休館日でしたものでやめまして、日曜日が10時から5時までという形でさせていただきました。
(委員)表彰式は何曜日にやっておられるんでしょうか。
(事務局)10月1日、日曜日の昼からという形になっています。
(委員)それでも来られてないんですか。
(教育長)課題もたくさんあるわけですが、いいところは残してもらって引き継いでもらうところは引き継いでもらうという形で、活かすところは今後活かしてもらって反省材料もたくさんあるわけですから、それを改善していただければ結構かなと思います。この件についてはこれぐらいでよろしいでしょうか。はい、続きまして(6)第10回なばり本の帯コンクール審査結果等についてを議題と致します。
(6)第10回なばり本の帯コンクール審査結果等について【非公開】
(事務局 説明)
(7)その他 ・各所属からの諸事項
(事務局)さる10月20日名張市小中学校音楽会小学校の部を実施させていただきました。委員の皆さん、来ていただきましてありがとうございました。本日、資料のほうで11月9日の中学校の部のプログラムをおかせていただきました。11月9日、昼からですけれども音楽会をさせていただきます。素晴らしい姿を見ていただけると思いますので、ご都合がよろしければ是非ご参加いただけたらと思います。ただ、5中学校の生徒全員が参加という形をとっておりますのでホールがいっぱいなんです。席が小学校の時みたいにまとまって教育委員会という形でとれないので空いている席に座っていただかなくちゃならないことになります。申し訳ないんですけれども。是非見ていただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
(教育長)はい。小中学校音楽会 中学校の部11月9日ですので時間が許せば是非ともよろしくお願いします。小学校5年生の演奏を聞かせてもらったんですけれど、発表も見学の態度も予想以上に素晴らしいと思わしてもらいました。中学校は例年の如くいい演奏をしてくれるのではないかなと思いますのでよろしくお願いします。他ございませんか。
(事務局)本日テーブルの上に教育フォーラム、今回で第7回となります。チラシをおかせてもらいました。すでに第1回目のチラシで各学校児童生徒には配布しております。保育園・幼稚園にもお配りをさせていただきます。今回は第2回目ということで、まもなくお配りをしたいなということで。内容的には講演会、また1階のほうでは体験コーナーということで今年も考えておるんですけれど、裏面を見ていただきますとたくさんのご協賛をいただいております。今年のサブテーマといたしまして食育ということで企業さんにも色々とご協力をいただくということです。昨年700人程度の来場者数を得ましたので、それを目指して進めていきたいと思います。教育委員さんの方につきましては、1日お付き合いというような形になるとは思いますけれど、ご参加の方よろしくお願い致します。以上でございます。
(教育長)よろしいでしょうか。これマクドナルドとか、ヤクルトとか協賛で何かあるのですか。
(事務局)裏面を見ていただきますと、食べる事それからヤクルトでしたらおなか元気教室とかいうことで、実際に子どもたちを集めて色んな事をやっていただく。私もまだ詳しい内容のところまで聞いてない、私自身が聞かせていただいてない状況です。
(教育長)食育ということで、今回はたくさんいれてくれてあると。
(事務局)そういうことです。あと小学校の給食を委託しているメイハンさんや魚国さんも出てきていただいて、ご協力をいただく。基本的には担当の方が色々な活動をされているところでお声掛けをさせてもらったということで、ご協賛をいただいたと聞かせていただいています。
(委員)ここと関係ないんですけれど、この間10月28日の日に科学の祭典というのを教育センターでやっていただいてまして、現職の先生70人ほど協力して10何ブースありました。20ブースを超えていました。たくさんの子どもたち 保護者も来て喜んでやっていました。1番うれしかったのは、現職の先生方がこれだけ協力して理科だけでなく先生方が全部やってくれ、これはうれしい事だと思って見せていただきました。
(教育長)市内だけではなく市外からの先生も参加をしていただきました。雨、台風の影響もあってだいぶ心配したんですけど、だいぶ電話で問い合わせもあったみたいですが、たくさん参加してくれて無事に終わってくれて良かったと思わせてもらいました。それでは以上をもちまして第8回の定例教育委員会を終えたいと思います。ありがとうございました。
・定例教育委員会の日程等について
12月定例教育委員会 11月27日(月曜日)午前9時~ 庁議室
1月定例教育委員会 1月 9日(火曜日)午前9時30分~