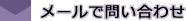平成29年度名張市教育委員会第5回定例会会議録(平成29年8月2日開催)
更新日:2018年9月6日
開催場所など
2.開催日時 平成29年8月2日(水曜日) 午前9時30分から午前11時30分
3.出席者 上島教育長、福田委員、松尾委員、瀧永委員、川原委員
4.欠席者 なし
5.事務局 高嶋教育次長、草合教育改革担当理事、合田スポーツ推進担当監兼国体準備室長、内匠教育総務室長、中森学校教育室長、上谷教育センター長、西山文化生涯学習室長、宮前図書館長、田中市民スポーツ室長、福本教育総務室教育総務係長(書記)
6.議事概要 下記のとおり
(教育長)皆さま方、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第5回の定例の教育委員会をはじめたいと思います。議事に入る前に本日の会議の公開についてお諮りをいたしたいと思います。本日の会議の事項中、議案第14号平成30年度使用小学校特別の教科道徳の教科用図書の採択につきましては義務教育諸学校の教科用図書の無償化措置に関する法律等の規定によりまして、名張市と伊賀市が同一の教科用図書を採択しなければならないというふうになっております。つきましては7月20日に開催されました第2回伊賀採択地区協議会におきまして両市教育委員会における審議につきましては、適正かつ公正な採択審議の妨げになることがないよう非公開とすることを、申し合わせをしておりますことから、本議案に係る審議につきましては非公開とすることを提案します。尚、議事内容につきましては、採択審議が完了する8月31日まで時限的に非公開とすることとし9月1日以降公開することに致したいと思います。従いまして本日の協議第14号でございますけれども、これにつきましては本日の会議の最後に回させていただきまして関係事務局のみ入った上で委員会をお願いしたいと考えております。又、協議の項の義務教育、義務就学者の変更について、並びにその他の項の児童生徒の問題行動につきましては個人情報保護の観点から非公開とすることを提案いたしたいと思います。委員の皆様方このことにつきましてご異議ございませんか。
(委員)異議なし。
(教育長)ありがとうございます。それではそのようにしたいと思います。又なおでございますが、教育委員の皆さん方には事前に配布させていただきました事項書と一部変更させてもらっております。本日の事項書の通りでございまして前にお声がけさせていただきました中の第15号につきましては、ちょっと変更等の再検討させていただいておりまして、割愛させていただきたいと思っております。従いまして旧来の議案につきましては15号というふうに繰り上げさせていただきたいというふうにも考えておりますので、旧の事項書につきましては外させていただきたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。それでは会議を進行致します。議案第13号名張市学校給食調理等民間委託業者選考委員会委員の委嘱及び任命につきまして事務局から説明をお願いします。
議事(1議案)
第13号 名張市学校給食調理等民間委託業者選考委員会委員の委嘱及び任命について
(事務局説明)
(教育長)説明が終わりました。ご質問等ございましたらお願い致します。よろしいでしょうか。それでは意義なしということで第13号につきましては承認といたします。続きまして、第14号を後回しにさせていただきまして、第15号子ども読書活動推進計画策定検討委員会委員の委嘱及び任命についてを議題といたします。
第15号 子ども読書活動推進計画策定検討委員会委員の委嘱及び任命について
(事務局説明)
(教育長)はい。それでは、説明が終わりましたので委員の皆様方からご質問ご意見等を賜りたいと思います。
(委員)はい、お願いします。任期期間について確認をさせていただきますが、第3次計画が30年度からスタートということで、その前の29年度8月25日からこの計画策定に関わるので、そこから任期がスタートするということでよろしいんですかね。
(事務局)そうですね。
(委員)終了が今度30年度の子ども読書活動推進計画が終了するまでになるんでしょうか。
(事務局)はい、任期のことに関しては要綱の第5条に委員の任期は委嘱又は任命の日から第2条の報告までということになっておりますので、第2条ではこの検討委員会の事務が計画案について検討し教育委員会に報告する、それでこの日までという任期です。
(委員)30年度の計画が始まるまでというような考えですね。
(事務局)30年度の計画を策定し、教育委員会に報告するまでです。
(委員)はい、わかりました。ありがとうございます。
(委員)ということは、平成30年からあと何年間の計画をするかということをこの会議で決めるわけですね。
(事務局)はい、そういうことになります。
(委員)そうすると、30年までに今までのお話ではないですけれど、報告をあげてもらわないといけないと、おのずと期限がそこまでっていうことですか。それとも、もっと長い事時間かかって十分な計画を立てようと思ったら、31年になってしまったということもあるんですか。
(教育長)はい、どうぞ。
(事務局)今のところ、30年度からスタートできるように検討いただくと、策定いただくというふうに考えております。
(教育長)他、いかがでしょうか。はい。
(委員)第3次とあります、30年度から何年度までの分の計画なのでしょうか。聞きもらしたかもしれませんが、教えてください。2次の時に25年から29年の5年間ということでありましたので、3次とありましたが、どのような期間を対象としての計画なのでしょうか。
(事務局)はい、期間につきましてはこの検討委員会で具体的に決めていただきたいと思っております。
(委員)すいません。これも調べたらわかることなのですが、第1次は何年から何年までだったでしょうか。参考までに。
(事務局)第1次につきましては、平成15年2月に策定されております。この時にはこの計画について何年間というふうな年限をいれた規定がなされておりませんでした。
(委員)はい。
(教育長)よろしいか。私からですが、そのあとの2次はですね、それをうけて策定したというわけですね。
(事務局)はい、そうです。
(教育長)その時の必要というか第2次の検討をしたのは、推進計画でどういう理由から、第1次の期限がない中で。
(事務局)平成15年に策定しておりますので、まず計画策定後10年が経過しました。その後なだらかに状況が変化しておりますので、なおかつその間に国とか県とかの読書活動推進計画が策定されたり、改訂されたりしておりますので、そういったことも反映して第2次を作ろうということになりました。
(教育長)はい、わかりました。
(委員)設置要綱第1条で法律に基づいて、この計画を策定することを検討するための委員会の設置となっておりますが、名張市においてのこの教育計画といいましょうか、全体のプログラムの中でのこの子ども読書活動推進というのは、何かその上にある計画のところから降りてきている、そういう関係性のあるものですか。要は全体感が見えないのですけども。設置要綱の第1条では確かに法律に基づいてこの市での計画を設定すると、策定するということの主旨は理解できるのですが、名張市での教育計画そういったプログラムの全体像との関わりというと、どこにあてはまる話になりましょうか、教えてください。
(教育長)よろしいか。
(事務局)不確かな話ですけれども、子ども教育ビジョンの中に少し謳われていたような記憶があるんですけれど、ごめんなさい、今ちょっと資料を持ち合わせていないので。
(教育長)はい。
(事務局)子ども教育ビジョンの中には子ども読書の方、推進していくということは当然ございますし、今、特に読書によって学力をつけてというようなこともございますので、そういうふうな位置づけの中から改めて第3次のほうを進めていきたい。こういうふうな形で教育委員会の中では調整の中で進めていきたいということです。
(教育長)よろしいでしょうか。
(委員)はい。大変、非常に子どもの読書活動推進ということは大事な活動だと思いますし、是非ともそういったことを推進していただきたいということからなのですけれども、この前回の2次からの計画で何か成果がでているんでしょうか。で、そしてそれを受けて更に必要と認めて計画を、先程も同じようなことを聞かれたかもしれませんけれども、新たにこれを推進していくというお話なのか、引き続き前回で何か持越しの案件があって成果がでないので引き続き検討しているということなのか、予算と時間をかけてやるその意味としましてどういう背景といいますか、何か次のめあてというようなものがあるのかどうか、そのあたりを聞かせていただきたい。なぜこういったことが、必要であろうからこれだけの方にお集まりいただいているということもわかるのですけれど、成果として今度どういうふうに今後子ども達の教育活動にフィードバックできるのかと、そういうなんて言うのでしょうか全体のプロセスの中での非常に大事な計画を練っていただく部署であるがために、そのへんのここで話したことが次にどういうふうにおりてくるのかちょっと見えないのですけれど、そのあたりまた前回までの経緯がありましたら教えていただきたいのですけれど。
(教育長)はい。
(事務局)私、僭越で申し訳ないのですが、子ども教育ビジョンの担当として、それとこちらの方も評議員をおいていわゆる進捗状況を確認しておるのですけれども、考え方としましては、第2次で主にはやはりその大きくは本の充実というようなことに重きをおいています。その中でもやはり、今後保育所、小学校、中学校という、連携という事を第2次の方ではある程度意識をさせていただきながらやってきたんですけれども、特にですけれど第3次については逆に教育の部分では、今すでに5歳児から小学校につなぐというそういうふうなこともありまして、より強固にその連携が必要になる、それにつきましてはやはり、こういうふうな図書こういうことも通じて勉強していかなければならないのではないのかなと。それともう1つ、新たな展開といたしまして今年度から学校教育室が主担当として進めていく、各学校の図書館を地域の方へも開放していく。また逆に地域のほうに開放することによってちょっと学習に困難な子については、地域の方にサポートいただくというようなことも連携の中で進めていけたらということです。第3次についてはそういうことも含めまして、新たな少し展開を考えながら、また第2次からまだ果たせていない連携の強化並びに、本の充実、ただ本の充実は新刊を全て入れるので充実ということじゃなくて、やはり整理をしながら充実を進めていくということが必要です。それと特に私が感じさせていただいているのが、第2次につきましての学校のほうがかなり図書館ということについて、意識をもってきていただいているのではないのかなと。今までは教育センターから派遣している学校司書、図書館司書の方はある程度まかせきりの部分もあったんですけど、学校が積極的に図書館を活用しながら色々授業もとかそういうことも工夫をされながらきたんじゃないかなというふうな感想をもたせてもらっています。以上でございます。
(教育長)よろしいでしょうか。ちょっと私、聞かせていただきたいんですけど。さきほど委員さんの質問にもあったんですけれど、子ども読書活動推進計画の法律の第9条第2項の規定に基づいた中での推進、名張市の読書活動推進計画、第1次からこの法の規定に基づく中でのことを受けてですね、やっていくということで、特段その第1次からこの計画をする予定を第3次のところの、更にその上に何か基本になるものがあるかと、そうではないと。この第1次からやっていくことで法に基づく中でもやっていくというふうに私はこの判断をしているところでありますけれども、そういう意味の中では、当然その時その時のやはり色んな施策の変更もあると思う。だけどこれは室長が言ったような形の中で、やはりこれからの子どもの読書活動あるいは子どもの居場所、あるいは学習支援、そしてコミュニティ・スクールを含めた地域、学校との協働という形も入ってくると、第3次からの大きな変更点ではないかなと思うところでございまして、それらのことを受けて、その時その時に合ったものを単年度じゃなくて複数年度で計画を立てていくというようなものが、この名張市の読書推進計画の部分ではなかろうかとこう思っている所です。他いかがでしょうか。はい。
(委員)これはもう感想的なものになるんですけど、やはりこの計画はとても大事で、特に第2次のあたりなど成果が出ているというのを感じています。私の子どもが小学校、中学校でお世話になっていたころは、図書室や図書館は整備途中だったっていうこともあって、その間で、この2次の間に学校図書館が本当に整備されて、バーコードで管理されるようになったりとか、これはシステム上の問題だと思うのですけれど。それとか学校訪問で各学校へ行かせていただいて、図書館をのぞくと本当に子どもに親しみがあるような工夫がすごくされていて、掲示の仕方とか、また各学校の図書委員さんの活動の報告もだされているとか、本当にこの数年の間で図書館が明るい場所になっているというのを感じているので、やはり計画の成果だと感じていました。それで又今、第3次の目的っていうのをちょっと聞かせていただいて、コミュニティ・スクールや、地域との関連も重要な場所になるようにっていうことを聞いたので、更に期待をさせていただいてます。このメンバーをみせていただいても、ボランティアの方もスペシャリストだと思いますので、是非とも充実した計画を立てていただけることをお願いしたいと思います。以上です。
(教育長)はい。他どうですか。私、すぐどうこうってことはない、人数の事もあるんですけど、メンバーをみさせてもらうと名張市に関係するところの方ばかりでないかなと。市外の方とか学識経験者等々をいれると人数がオーバーするので、削らないととなってくるんです。そういう部分は検討されたんでしょうか。市外の方の事は。
(事務局)実は第2次の時に非常にお世話になりました皇學館大学の高倉先生、今でしたら当然入っていただくつもりではいたんですけれど、突然亡くなられたということもあって、その先生にかわる方もそう簡単に見つけられない関係で、第2次の時に検討委員の一員であって図書館長をやっていただいていた木村さんにお願いするというところまでは考えました。市外の方については考えていなかったです。
(教育長)この10人のメンバーの方は素晴らしい方ばかりで、言う事はないんだけれども、この読書活動推進計画という大きな形、また第3次の計画の意義等を考えた時に、ちょっと市内の、在住はどこでもいいんですけれど、そういう形の中でですね、高倉先生はもうお亡くなりになって、早急にそういう方もいれながらですね、広く見ていくほうがいいのではないかなと、ちょっと急な思いなんですけれど言わしてもらいました。検討する余地があれば、要綱を変更すると。もしあるとすれば、そんなことも検討の1つとして、しなさいということとは違いますが、してもらったらどうかなと思うところです。
(委員)同じ意見です。要綱の第3条の2項の6にですね、そういったことで何かですね、その他必要と認めるというものを入れていただく、そういう余地があるかなというふうに私も思います。で、主旨としましては読書活動といっているものの範囲をのせて、それから概念がハードカバーの、ハードコピーの本を対象として狭い範囲で考えるのか、それとも近未来的に進んでいるデジタルの図書ですね、デジタルメディアの分を意識したような形でのそういうメディア教育ということまで踏む込むのかどうか。また別途そういったことをやる部署があるのかどうか。そのあたりも少しご検討いただければなぁ、委員会があったらなぁと思います。また他市町村、また他のですね図書館、公共的な図書館以外の民間の図書館のことで、色々議論もありますけど、そういうところにも色々視察など行っていただくなり、お話を聞いていただくなりして少し広い視野で見ていただくのも非常に重要なことかなと思います。と、申しますのは私の関係するところで恐縮なんですけれど、新しい図書館を作るときに関係者の中で、賛否両論がございました。その賛否両論がある中で、反対者が多い中で、初歩的に初めてそういった図書館改革がございます。でまだわかりません、成果はでません。それから教育活動ですから将来的に何かわからないんですが、何か始める時にどうしてもそういうふうに外からのある程度勉強といいましょうか、知見もいれないと、中々かわらないのかなと思っております。そのあたりもご検討いただけたらなと思います。
(教育長)今の意見に対して、何か所見はありませんか。よろしいか。それでは特にございませんので、この委員の選考につきましては承認ということでよろしいか。あとにつきましては今後、要綱の変更等の検討もされると聞かせてもらってございますので、先程言ったことも踏まえてですね、検討の材料の1つとして考えていただき、実行性のあるいい第3次の読書推進計画を立てていただくのがいいのではないかなと、教育委員会としては考えますのでよろしくお願いします。この件、これで終わらせていただきます。それでは議事の第2、協議の方に入りたいと思います。傍聴の方はおりませんので、このまま進めたいと思います。義務就学者の就学校の変更についてを議題と致したいと思います。
議事(2協議)
義務就学者の就学校の変更について【非公開】
(事務局説明)
議事(3その他)
(1)児童生徒の問題行動について(6月分)【非公開】
(事務局説明)
(2)名張市青少年補導センター、名張少年サポートふれあい隊合同パトロールの実施について
(事務局説明)
(教育長)はい、説明が終わりました。何かこのことにつきましてご意見ご質問ありませんでしょうか。はい。
(委員)8月4日、このあとの行事計画で私も出席ということになっているんですけど、ちょっと岐阜に行っていて、この時間に帰っているかどうか。とりあえず欠席にはしてあるんだけど。
(教育長)帰ってこれると思いますよ。でも余裕はないと思いますけど。
(委員)帰れたら行きます。
(事務局)ありがとうございます。
(委員)帰れなかったら、時間ややこしかったらごめんなさい。
(事務局)8月4日が61名、8月5日が62名という形で、両日合わせて123名のご予定という形で伺っています。遅くなりましたが平成28年度は2日間で121名、平成27年度は129名のご参加をいただきました。
(教育長)8月4日は名張の祭りと違うかな。
(委員)はい、イオンで。名張地区の。来年、その時と重なるわけですね。だいたいそうですよね。
(教育長)名張の祭り、よく考えたら9時という時間がちょっと早いのかなと。問題は後の方にあるのかなと思ったりするけれど、限界があるから、柔軟に対応してもらったら非常にありがたいなというふうにも思うところです。直接関係ないんですけれど、先程の問題行動も同じことですが、ご承知のように9月1日は子どもの自死の一番多い日でございまして、子ども達は長い休みのあと新学期を迎えるわけで、非常に不安定なときでもあり、色んな休みの延長の部分もあろうかなと思っておりまして、非常に大事なこともあろうかなと思いますので、是非とも担当の皆さんには大変お世話をかけるところではありまして、すみずみまで見ていただき、又声掛けも一声していただくということも非常に大事かなというふうに思っております。いずれにいたしましても、夜間のことですので皆さん方、事故等にならないように、十分気を付けていただけたらなと思っています。よろしいでしょうか。はい。それでは続きまして、次の項目に行きたいと思います。その他所属からの連絡事項がありましたらお願いします。
(3)その他 各所属からの諸事項
(事務局)実は前回ちょっと質問をいただいて、持ち帰った件で。すいません。1点は、教育支援委員会についてなんです。私の方が2回と申し上げたところなんですが、大きな就学指導に関わっての機会は2回ですが、その準備のため又まとめとして計4回実施させていただいています。ただ2月には行っていないのですが、持ち回りにつきましては他県、他市から急な転校等でその就学先に迷いがなく、保護者の意向と就学先の指導が合致するケース、難しいケースではなくその本当にほぼ間違いないというケースについて持ち回りをさせていただいているということです。この間ご意見いただきましたことを踏まえまして、就学支援という意味も踏まえ又就学支援指導後の就学の指導後のあり方のことも含めまして、異論なくすすめていけるよう検討していきたいというふうに思っております。もう1点がいじめ専門委員会についてということで、その情報提供をどのように行うかということでございました。これにつきましては個々に対して担当より情報提供を行なっているという事で、専門委員の皆様は校外生指委員会とか生徒指導の委員会に参加していただいている方については、そういうふうに担当の方から言わせていただいたり、直接出向いてですね、お話をさせていただく事、機会を通じて情報提供を行なっているという事で、月ごとに詳細に行っているのではないという状況です。システムとしてなんですが、学校教育室室長と担当とそして教育センターのSSWとの月1回の情報交流・公開と適応指導教室の月1回の情報交換を必ず行っている所です。専門委員会につきましては大きくは年度初めと年度終わりにまとめての報告となっています。緊急時には緊急に召集して行わせていただくという事で思っております。今後協議会運営のマスコミ関係や弁護士の参加もいただいている所ですが、又検討していきたいと思っております。以上です。
(教育長)今の学校教育室の説明についてご意見ご質問ある方、どうぞ。ちょっと私、先程の持ち回りを含めて4回の持ち回りって何ですか。
(事務局)持ち回りは12月までに8日行ないますもので、この1月からのケースで先程いった他県他市から急な転校で、その就学先に迷いがないとか保護者と就学指導委員会との意見が合致するというケースについては、それぞれの委員さんのところへ持っていくというのが1月以降でございます。ただこれは難しいケースでもそんなことするっていうわけではありませんので、その場合は緊急に行わせていただくなどの対応をするということで進めていっているという事です。
(教育長)会議は2回。
(事務局)4回、4回あるんですね。12月までに4回。
(教育長)2回じゃなくて4回。
(事務局)そうなんです。間違っておりまして、大きい会議が2回ということで前後がありまして、申し訳ございません。
(教育長)4回以外に、該当のところが、急な案件があれば持ち回りもあるということ、こういうことですね。1月以降は。
(事務局)はい、そうです。
(教育長)はい、わかりました。では続いて市民スポーツ室。
(事務局)私の方から2点ほどご報告をさせていただきますけども、前回7月の定例教委の中で報告をさせていただきました、本日の資料についてなんですけれども、シニアスポーツ大学の講座について、委員さんのほうから統合してはとお声をいただきまして、検討させていただいた結果、7月29日に資料提供させていただいたんですけれども、定数の加減もありましたので10名ということで、大変申しわけないんですけれども、公募をさせていただきました。ただ公募に係る要件といたしましては、シニアというカテゴリーを一体いくつからという色んな意見もあったんですけども、29年4月1日で50歳ということを1つの区切りにしようかと。それからやはり折角受講していただいてスキルを付けていただいた方については、地域で活躍頂ける元気隊のリーダー等になっていただけるという意気込みのある方をというこの2つの条件を付けさせていただいて公募させていただきました。それともう1点。もう何回もお願いさせていただいているんですけれども、いよいよ来週になってきましたラジオ体操でございますけれども、8月11日金曜日ということで、早朝の時間帯ではございますけれども、より多くの方にお集まりをいただきたいということで、目標を1日でございますけれども2,000人という大きな目標をかかげまして、警備計画についてはうちのほうで策定し、警察、消防とも協議を完了しております。1か所に2,000人が集まりますので事故のないように、入場それから実施、退場まで行えるよう安全の体制はしているつもりですけれども、何事もなく終われるようにと思っております。当日是非ご参加の方お願いしたいと思います。
(教育長)この件につきまして、よろしいでしょうか。他よろしいでしょうか。はい。
(事務局)本日、委員さんのほうだけなんですけれど、前回学校給食運営委員会でどんなご意見がありますかということで、意見の部分でまとめさせていただきましたので、今日はその時どのような対応をしたか、それ以降どのように対応したかという事でまとめたものをお配りさせていただいたものです。基本的には、その場で回答させていただける分に関しては回答させていただいたということで、1つ名張小学校の上から2番目の所なんですけれど、1年生、4年生は学校で準備したものを使っているが5、6年生はナフキンを持参しているのを、持参するのではなく同じにしてほしいということで、基本的に、名張小学校については本年4月から全校でお盆を使用する、そのあとどうも担当の方と学校の方と色々協議をさせていただいて、基本的に色んな家庭の状況もあるんですけれど、もう1か月も2か月もナフキンを洗わず、そのまま使っている、非常に不衛生なというようなことも色々聞かせていただいている中で、このような対応をさせていただいた中で、どの学校も全て対応できるという事ではないんですけれど、その場でほぼ難しいものは難しいと検討していくという形の中で対応させていただいくということでございますので、また折を見てこういうような形で情報提供させていただきたいなと思っておりますので、一応またご参考にしていただけたらと思います。以上です。
(教育長)はい。この件はよろしいでしょうか。
(委員)1点だけすいません、よろしいでしょうか。ちょっと教えてください。このつつじが丘小学校ででている牛乳がおいしくないという件で、この対応の所に書かれているんですが、平成28年度は業者が変更したためっていうのは、業者が牛乳を変更した。
(事務局)すみません、これ表現が。業者が変わったんです。28年度だけ変わったんです。
(委員)28年度だけ変わった。
(事務局)28年度だけ変わったんです。
(委員)28年度だけが変わった。
(事務局)毎年入札をされるようなんですけれど、1年だけ変わったんです。やはり敏感な子は味に気付かれたということも、ちょっと聞かせていただいております。
(委員)わかりました。
(教育長)よろしいでしょうか。それ以外ありませんか。はい、ありがとうございました。それではその次ですが、29年8月の諸会議・行事で何か間違いなどございませんか。よろしいですか。それでは、色んな行事もあるわけでございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。他よろしいですか。ありがとうございました。定例教育委員会の第14号の議案を除く部分につきましては、これで終了したいと思います。
(委員)ありがとうございました。
(教育長)それでは再開したいと思います。議案第14号平成30年度使用小学校「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択につきまして、学校教育室からよろしくお願いします。
議事(1議案)
第14号 平成30年度使用 小学校「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択について
(事務局説明)
(教育長)はい、説明が終わりました。今、最後におっしゃってくれましたようにこの定例の会議におきましては、30年度使用の道徳の教科用図書の選定を行いたいと思っておる所ですけれど、採択協議会が伊賀地区採択地域になっておりまして、そこで決定されたことが、今おっしゃってくれました文教出版株式会社の教科用図書であるという事でございますが、最終的には各市町村の教育委員会が決定することになっておりますので、これからその手順に沿って、ちょっと時間をとらせていただいて、今の伊賀地区採択協議会で決めていただきましたことを含めて、教育委員の皆様に再度検討していただき、進めていきたいと思います。2、3分ちょっと時間を取りたいと思います。よろしいですか。
(委員)そうですね。できればこの日本文教出版さんに決めていただいた、決定理由は書いていただいているんですけれど、調査報告書に基づいた中で特にここに決めた内容、特にぬきんでたところ、他社に比べてというところを説明していただけたらなと思うんですけれど。細かく色々内容を書いていただいていますよね。この調査報告書。
(事務局)はい。その時にですね、その調査員の代表が申しましたことをそのままお伝え申し上げたいと思います。1.取り扱い内容、主体的に考え、問題解決する学習や体験的な学習を進める上で、適切かつ効果的な内容になっている。2.内容の選択及び扱いについては、導入から展開後の後段にいたるまで児童の思考の流れに沿った発問を設定し、自発的な思考を引き出せるように配慮されている。3.児童の興味関心を喚起させるだけではなく、人間の弱さとそれを乗り越えようとする強さや気高さについて理解をさせることに重点がおかれている教材が多数取り上げられている。4.内容の構成及び配列、各教材に主題名を記し道徳的価値又は教材に関わる導入の発問例を示しているため、児童は見通しをもって学習できるようになっている。教材タイトルの部分にあらすじを示したり、主な登場人物を整理して配置したり、読むときに抵抗ができる限り少なくなるように配慮されている。5.創意工夫 問題解決的な学習方法が想定される教材には、教材のあとの学習の手引きに問題をつかむ活動や考える活動を促す発問等が示されている。6.使用上の便宜 別冊道徳ノートが用意され自分の考えをまとめたり、友達の考えを記録したりするようになっている。まとめの場面では学習の思考の深まりや気づき、今後の目標などを振り返ることができるようになっている。また、委員から出された意見としては子どもがよく知る人たちが多く登場している教材がたくさんあるので、その生き方を通じて子どもへのメッセージを送っている。読み物の教材がよいので登場人物の絵も子ども達の読みも助けてくれる。導入的な発問がよい。道案内みたいで考えやすいという好評価があった。ただ別冊のノートについてはだいぶ議論されています。これがあったらいいのか、なかったほうがいいのかということで、1年生においては学期ごとに追われてしまうというそういったことでございましたが、このノートにつきましては議論されたあと委員さんもご意見をくださいました。その中でやっぱり初めての分野ということで、先生方の力量で大きく差がついてもいけないし、子ども達がまず考えをもって道徳にあたるよう、書くという作業を通じて、そして議論をしていく。そういうためにもこのノートは有効で、全部を使えというわけではないけれども改めてプリントを作ったり、そういった作業を含めて考えれば35時間を十分やらなくてはいけないということになれば、これは有効であるということでご意見がまとまりました。
(委員)はい、ありがとうございました。
(教育長)すべての委員さんからは意見が出されたところで、委員さんも出てくれていたのでその時の感想なり、ちょっと聞かせてもらったら。
(委員)はい、2回目だけ出させていただいたんですけれど、感想としてはそれぞれ各市から3人ずつ委員がでて話をさせていただいたんです。1つ思ったのが、校長先生が調査委員長でして、でその方からここの報告書には、いい点ばっかり書いてあるんですけれど、それぞれの会社の少し問題だった点も発表していただいた中で、伊賀地区の先生方の実態もふまえた上で会社を選定していただいたというように私は受け取りました。私もこの道徳の方面、現場にいたときから、色んな「にんげん」とかそんな本も使いながら教えたんですけれど、教科書となると事前に2、3回こちらに通わせていただいて、みんな文科省の指示してある通りの項目は全部入っていますし、どれがいいかなっていうのはなかなか分かりませんでしたし、ただこの規定から行くと県の参考資料がでるはずだと、また地域の地区協議会のほうから許可させている調査報告書もでています。それを基にしながら勉強させてもらおうかなと思ったんですが、どの教科書を使っても先生方の使い方だなと思いつつ、取りあえず決めて次の段階でもう一度きちっと採択し直したらいいのと違うかなとの思いをもちながら、見せていただきました。ただ、だいぶ難しかった。あんまり関わっていない人は、これはどうやって選ぶかなと疑問に思います。私は気になったのは、1つは文の長さ。あんまり長くて、読むだけですんでしまったんでは子どもは悩みにいかないだろうなとか、その文章の長さを考えました。あと1つは評価をどうするのかなと、そのへんで別冊ノートになっているのがいいのか、悪いのかそれも悩みましたけれど。これは子どもの成長の記録だとかそんなものも考えながら、1年たったときにどんなふうに心が変容したかなっていうのを見る上で、あった方がいいのとちがうかな、ただそれを書かないと絶対いけないんだというのもおかしいしなというところで、簡単でも、メモ程度でもいいので書く欄があったらいいだろうなってことで思いました。そんな点から協議会で出していただいた結論で賛成させていただいた状況です。以上です。
(教育長)今もありましたように、初めての教科書選定ということで、大変ご苦慮いただいたところで、私自身もなかなかこんなこと采配できませんでしたが、先程室長さんから報告があったように採択協議会の中で、調査員からの報告というところを重点的に考えさせていただいたところですが、委員さんの方から何かありましたら。
(委員)よろしいでしょうか。事前にちょっと見せていただいて、文教出版さんの文の長さっていうのは委員さんもおっしゃっていただいたように、ちょうどいいかなと思ったんです。中には4ページ、5ページある会社もあって、これは国語の授業になってしまうなというのもありました。ただこの文教さんについては、歴史的な人物とかはあんまり使っておられないなという印象があったんですね。さっきおっしゃっていただいた報告の中には、子どもが知る人がよく出てきてというような表現がありましたけれど、私の印象ではこの中ではあまり歴史的な方とかを、学年によったのかもしれませんけれど、あんまりそういう登場人物がなかったなと思ったんですね。以前議会の中でも道徳の中で、どうしてこの日本の素晴らしい歴史的人物を、子ども達に伝えていかないのかというご意見をちょっと記憶にとどめていたもので、やっぱりそういう歴史的なものを、歴史の中だけではなく道徳的なことの中で伝えていく必要があるなぁと思っていたので、ちょっとそこだけメモ書きした記憶があったので、もうちょっとその点では思っていた中身とちょっと違うなと思ったんですが、他、評価の点とかそういう点、色々考えていただいて決めていただいたので、それについては他は何も意見はございません。
(教育長)はい。
(委員)今の委員さんのおっしゃる通りで、同感です。世界の偉人という事について大学生で1年生なんですが発表してもらう授業をしています、それを通じて自分の生き方を考えるという機会にと思っています。1年生の段階で世界の偉人、書いた本を選びましょうとすると、誰が偉人かわからない。ですので、そういう言い方はやめまして100年以上前に出版された本でカタカナの作者、日本人ではない方という意味合い、色々あれなもんですから、簡単に言うと外国の人という感じで選ばせました。その選ぶこと自体ができないんですね。だから世界の偉人とか、その人の生き方を学ぶっていうことをこれまで意識していないのかなと、そんな意識がないのかなと感じた次第です。それで結果としまして、書籍を2つにしてそこから本を選ばせて読ませたんですけれど、こういう機会がなかったら全くこういうこともしなかっただろうという感想が多く、その全く別の時代で全く違う国の全く違う背景の人だから、自分と全く遠い人であるということをわかっていて、そこから学ぶことがあったということが驚きだったようです。そういうことで、大学生だからということではないとは思うので、委員さんがおっしゃられたことを踏まえると、そういうこともやはりあるなというふうに、これは感想ですけれど、今回の選定についてどうこういうということではないのですが、そういう視点もあるのかなということも思いました。もう1つ、気になりますのがオリンピック選手、たくさんテキストにもでておりますけれど、本当にこれがよいことがどうか、非常に視覚的に訴えますし、印象も強いですし、挫折感ということを学ぶ、そういう勉強をしないといけないんではないかと思う反面、オリンピック選手ばかり称えると、多くの子は挫折を経験しながら生きていかなければいけないというのがありますので、そういうことが学べるようなテキストのほうが現実的ではないかなと。ちょっと今オリンピックの写真を見て思いました。自分の事でないっていうふうに最終思ってしまうと、全然勉強の視野に入ってこない。それも大学生が思うことがありまして、ある資格を目指しましょうと話しても、自分の事じゃないとものすごく意欲が下がるんですね。そういうことがあるかなと思う点、それが2つ目。ちょっと教えていただきたいんですけれど、次点採用は、やや適しているということで、次点と考えてよいのでしょうか。
(教育長)はい、室長。
(事務局)最終ですね、おっしゃって下さったように2社で最終検討がされました。
(委員)決定打はどういうことだったんですか。
(事務局)取り扱われている教材についてが1番。3点について話し合われています。1つは取り扱われている教材についてです。2社とも大変精選されていてということで、それぞれの部分でも例が出ていましたが、2点目は教材の導入から展開の後段、それから授業の終わりについてどのようになっているのか、見通しが持てるのかということと、それから3点目がノートのことなんです。それで1点目も2点目も、実はその決定打にはならず、最終ノートがどうなのかとそれについても、話し合いをされて。
(委員)次点にはノートがないんですね。
(教育長)ないんです。
(委員)授業の準備をしないといけないという話でしたね。プリントを準備しないと。
(事務局)全員が、本当に教材研究をして子ども達の心に残る、考えを議論する道徳をしていくっていうことについて、それぞれ先生に頑張っていただかなくてはいけないんですけれど、最終、どの先生もがこんな差ができるんではなくて、やっぱりしっかり初めに考えさせて、ペアで考えて、グループで考えて初めの自分の考えをもっと深めていけたり、色んな意見を聞いてよりよく生きようとする道徳的価値というか、そういったものを身につけていってほしいという、そういうふうに考えた時にあっていいのか、ないほうがいいのか大分議論されたということでした。
(委員)あの参加者の人のアンケートも様々でしたね。あると加減が悪い、あったらいい。だいたいアンケートを出してくれてあったのは伊賀市と名張市と先生方らしいのと、アンケートが多かったです、色々でした。
(教育長)どうでしょうか。
(委員)はい。私も教科書を見せていただいたんですけれど、参考になる、何をっていうのがわからないんですけれど、この最後の一覧を見て比較はさせていただきました。結局、どれも必要なことは網羅されているので、好みかなと思ったんですけれど、やはり選んでいただいて、これいいものだと見てわからせていただいたところですけれど、これやはりどう活用するのかというところになると思うので、もう決まったもので、35時間という限られた時間で、本当に深いことをどこまでできるかって先生の力量に左右されると思うので、是非よりよくなるように活用していただく方を重視していただきたいと思います。
(教育長)私も委員として参加させてもらったところですが、先ほど委員さんがおっしゃってくれたように、要はこの初めての教科書として選定するので中身を見てですね、それほど大きな違いというものが感じられないかなと。ただその発行の会社によって編成の方針がありますからおっしゃる通りなんですけれども、内容はどこかが抜けているとかいうことはなくて、しなくてはいけないことは検定済みでありますので、一応大きな偏向というのは、偏向は偏向教育のことですが、私自身そんなに大きく感じられない。ということは、こうやって初めて教科書をということで、実際、先生方がどうこれを取り組んでいくかということになってくる。あるいはノート、分厚さとかありまして、これはまた色んな考え方があるので、どちらでも取り上げられるかと。しかし45分の授業の中で全部こなすのはいいのか分かりませんけれど、ただ単にやってはいオッケーやりましたで終わったんでは意味がないわけで、やっぱりきちっと何を道徳の授業で子ども達に伝えていかなきゃならないのか、あるいはそれを子ども達が意欲的に取り組んでもらえるかどうかということが大きな観点ではないかなということであります。全てノートもバラバラでありますけれど、毎時間、毎時間細かくやってその通りすることに追われてしまうのではなく、柔軟に対応してもらうことの方が大事ではないかなというふうな形で、何にも使わないというのは、これはいかがなものかと、全部びしっと書かなきゃならないとか、あるいは書くことに強い子と弱い子も中にはいるわけで、書けない子の意見もやっぱり授業の中では尊重してあげてもらわないといけないのではないかというふうなことも話も出ていたところです。要は、今後一旦初めて使ってみて、その状況をみて次回の改訂の時にはやっぱりもう1回そのことの検証をやることが必要ではないかと。当面は大きな事がないかぎりきちっとした道徳の意味をふまえながら、そして指導と評価をするものですから、それについても学校できちっと意思統一をしてもらって、担任の先生のばらばらな視点だけでしてしまうと、子どもについては、小学校1年生から中学校3年生まであるわけですから、それについては取り扱いがきちっと目標、目的が達成できないということになってくるので、要は現場に、これから本当に今まで以上に、今までの人がやっている学校がほとんどだと思いますけれど、わかりましたで終わってしまうのではなくて、子ども達のために非常によかったと言えるものになるように、引き続きの努力をしなきゃならないのではないか。要は今回調査委員さんが色々検討してくれたことを、地域の先程の協議会としては落ち度がなければそれはそれとして尊重させてもらうのがいいのではなかろうか、こういう結論になったところで言わせてもらったところです。よろしいでしょうか。それではこれにつきましては、挙手で確認したいと思いますので、今の形の中で教科用図書の採択をされました日本文教出版の教科書を採択するということで賛成の方は挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。それでは全員異議なくこの教科書を採択するということで決定させていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。これにつきましては、先ほどもありましたように、8月いっぱいは非公開ということになっておりますので、委員の皆様も慎重にしていただけると大変ありがたいなと思います。
(事務局)どうもありがとうございました。
(委員)お願いします。
(教育長)この件に関しまして異議などありませんでしょうか。はい。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第5回の定例教育委員会を終えたいと思います。ありがとうございました。
(全員)ありがとうございました。
・定例教育委員会の日程等について
9月定例教育委員会 8月30日(水曜日)午前9時30分~ 第1委員会室
10月定例教育委員会 9月25日(月曜日)午後3時~