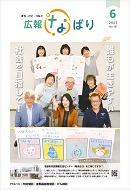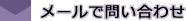広報eモニター「TOMONI」 6月号のアンケート結果
更新日:2025年7月4日
今号は、93人からアンケートの回答が寄せられました。
ご協力ありがとうございました。
1.特集 男女共同参画週間 「自分らしさが原動力です」に関連してお聞かせください【2~3ページ】
1.記事を読んで、「男女共同参画つうしん」を読んでみたいと思いましたか?
| 読んでみたいと思った | 71 | 76% |
| 読んでみたいと思わなかった | 22 | 24% |
| 93 | 100% |
2.問1で「読んでみたいと思わなかった」と答えた人にお聞きします。その理由は何ですか?(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、特集に対して興味がないという意見が多く見られました。特に、若い世代から中年層にかけては、ジェンダーに関する話題がパフォーマンスに感じたり、個別の特集に興味を持たない傾向が見られます。また、特集の内容が女性に偏っていることへの不満や、情報の深さが足りないと感じる意見もあります。高齢層では、男女共同参画が常識とされており、特集の必要性を感じないという意見が見られました。全体として、特集の内容やアプローチ方法に改善の余地があると考えられます。
2.「つくってワクワク!!ダンボールコンポスト」の記事に関連してお聞かせください【4~5ページ】
1.ダンボールコンポストを使ったことはありますか?
| 現在使っている | 0 | 0% |
| 使ったことはあるが、現在は使っていない | 1 | 1% |
| 使ったことはない | 92 | 99% |
| 93 | 100% |
2.問1で「現在使っている」と答えた人にお聞きします。ダンボールコンポストを使っていてよかった点を教えてください。(複数選択可)
回答なし
3.問1で「使ったことはあるが、現在は使っていない」と答えた人にお聞きします。現在使っていない理由を教えてください。(複数選択可)
| 毎日かき混ぜるのが面倒だから | 0 |
| ダンボールコンポストを作るのが大変だったから | 0 |
| 生ごみがうまく分解されなかったから | 0 |
| できあがった堆肥の処理に困ったから | 0 |
| 置く場所に困ったから | 0 |
| その他 | 1 |
その他
40代
・回転式のものを使用している
4.問1で「使ったことはない」と答えた人にお聞きします。その理由は何ですか。(複数選択可)
| ダンボールコンポストを知らなかったから | 65 |
| すでに生ごみ処理機を持っているから | 6 |
| 作るのが難しそうだと思ったから | 12 |
| 置いておく場所がないから | 15 |
| 堆肥を使わないから | 22 |
| その他 | 6 |
その他
20代
・管理が難しそうだから
40代
・畑をしないから
60代
・虫が湧きそうで怖いです
70代以上
・現在、夫婦2人で、生ごみが少ないから
5.記事を読んで、ダンボールコンポストに挑戦したいと思いましたか?
| 挑戦したい | 42 | 45% |
| 挑戦したくない | 51 | 55% |
| 93 | 100% |
6.問5で「挑戦したくない」と答えた人にお聞きします。その理由は何ですか?(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、ダンボールコンポストに対しては、手間や管理の負担、時間の制約、臭いや虫に対する不安が大きな障壁となっているようです。特に、若い世代から中年層にかけては忙しさから時間を割けないという意見が多く見られます。また、堆肥を必要としない、または生ゴミが少ないという理由で挑戦しない高齢層も多く、コンポストの利用価値を感じていないことが伺えます。これらの意見を踏まえ、コンポストの利点や簡単な管理方法を伝える工夫が必要かもしれません。
7.生ごみに限らず、ごみを減らすために取り組んでいることがあれば教えてください。(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、ごみを減らすための取り組みには、食品ロスの削減、リサイクルの徹底、過剰包装の回避が多くの年代で共通して見られます。特に、食品ロスを減らすために食材を使い切ることや、余計なものを買わない工夫が多くの回答者に共通しています。また、リサイクルを積極的に行う姿勢や、過剰包装を避ける意識も広く見られます。さらに、再利用の工夫や家庭菜園の活用など、創意工夫を凝らした取り組みも一部で行われています。これらの活動は、持続可能な生活を目指す上で非常に有意義であり、今後も継続していくことで、ごみ削減に貢献できるでしょう。
20代
・買い物に行く時は献立を事前に考えて、余計な物を買わないようにする。
30代
・減らすことにはなっていないかもしれませんが、物を増やさないようにはしたいと思っています。特に子どもの玩具は大きくなったらいらなくなるものも多いので、できるだけ家にあるものや廃材等使って作れる玩具を考えたり調べたりして作ったりします。
・スーパーに行く時に資源ごみを積極的に出している。なにかで再利用してもらえると嬉しいので。
・分別をしっかりと行いリサイクルに出す。繰り返し使える物を選んで購入する。
60代
・コピーはとらずほとんどの書類はスキャンしてデータで保管する。食べ物は捨てる部分を少なくしてほとんど使う。
・パンやオムツの袋などは生ゴミを入れるのに使ってから捨てたり、いらなくなったTシャツは切って、掃除に使ってから捨てています。ゴミ袋にはぎゅーっと押し込んでなるべくたくさんのゴミを一度に出せるように心がけています。
70代以上
・今まで、野菜の根っこを生ゴミに捨てていたが、野菜プランターの再生用を作り、そこに植えていたら、芽が出てちょっとした時に助かります。小松菜もニラもネギも何でも。芽が出るの楽しみになります。
3.「特別対談「どうする?地域の担い手確保」」の記事に関連してお聞かせください【6~9ページ】
1.対談内容から、地域の担い手確保について、何かヒントが得られましたか?
| 何らかのヒントが得られた | 38 | 41% |
| あまりヒントは得られなかった | 55 | 59% |
| 93 | 100% |
2.問1で「何らかのヒントが得られた」と答えた人にお聞きします。どのようなところがヒントになりましたか?(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、地域の担い手確保においては、人と人とのつながりの重要性が強調されています。若い世代を主役にすることや、彼らの興味を引き出す方法が特に重要視されています。また、個々の得意なことを活かすことで、地域活動への参加が促進されるという意見が多く見られます。多様な人々が集まり、化学反応を起こすことで新しい取り組みが生まれる可能性も指摘されています。これらの意見をもとに、地域活動の場を提供し、参加者が自分の特技を活かせるような環境を整えることが、地域の担い手確保に繋がると考えられます。
3.問1で「あまりヒントは得られなかった」と答えた人にお聞きします。地域の担い手を確保していくために、どんな取組が有効だと思いますか?(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、地域の担い手確保には、地域の魅力向上と若い世代の参加促進が鍵となることが示唆されています。地域を魅力的にし、若者が積極的に参加できる環境を整えることが求められています。また、活動に対する報酬の提供や職業化も一部で支持されています。さらに、世代を超えた交流の場を提供し、情報発信を強化することで、地域の結束を高めることが重要とされています。これらの取り組みを通じて、地域の担い手を確保し、持続可能な地域社会を築くことが期待されます。
4.対談の中で、支え合いの社会を築くためには「人と人が出会う機会や場が必要」との考えが示され、地域福祉計画の重点取組にもなっています。 皆さんの周りで、人が集い、つながれるような場があれば教えてください。(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、人と人が集う場としては、地域のお祭りやイベント、公共施設、地域の清掃活動や自治会活動が重要な役割を果たしていることがわかります。これらの場は、世代を超えた交流を促進し、地域の結束を強めるための重要な機会を提供しています。また、職場や商業施設、スポーツジムなども、日常的な交流の場として機能しており、これらの場を活用してさらに多様な人々が集まれるような企画を考えることが、地域の支え合いの社会を築く上で有効であると考えられます。
4.「特定健診・がん検診」の記事に関連してお聞かせください【10~13ページ】
1.あなたは健康診断・がん検診を受けていますか?(職場で実施されているものなども含む)
| 両方受けている | 35 | 38% |
| 健康診断のみ受けている | 40 | 43% |
| がん検診のみ受けている | 8 | 9% |
| どちらも受けていない | 10 | 11% |
| 93 | 100% |
2.問1で「両方受けている」「健康診断のみ受けている」「がん検診のみ受けている」と答えた人にお尋ねします。健康診断・がん検診を受けてよかったことを教えてください。(複数選択可)
| 気づいていなかった病気が見つかった | 9 |
| 病気の早期治療ができた | 9 |
| 自分の身体の状態を知ることができた | 67 |
| 生活習慣を見直すきっかけになった | 28 |
| その他 | 2 |
3.問1で「どちらも受けていない」と答えた人にお尋ねします。健康診断・がん検診を受けていない理由を教えてください。(複数選択可)
| 健康診断・がん検診を受けられることを知らなかったから | 0 |
| 近くに受けられる医療機関がないから | 0 |
| 通院中のため | 2 |
| 結果が不安なので受けたくない | 0 |
| 検査など(採血・レントゲン検査など)に不安があるから | 1 |
| 必要な時はいつでも医療機関を受診できるから | 0 |
| 受けに行く時間がないから | 2 |
| 面倒だから | 2 |
| その他 | 3 |
その他
20代
・若いから
4.あなたが、生活習慣の改善や健康づくりなどのために取り組んでいることを教えてください。(自由記述)
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、生活習慣の改善や健康づくりのためには、食生活の改善と運動習慣の維持が重要視されています。多くの回答者が、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけており、これが健康維持の基本とされています。また、規則正しい生活を心がけることや、特定の健康対策を行うことも多くの年代で見られます。さらに、メンタルケアを重視する意見もあり、心身の健康を総合的に維持することが大切であると考えられます。これらの取り組みを継続することで、より健康的な生活を送ることが期待されます。
5.6月号全体についてお聞かせください
1.最も興味が持てた記事は何ですか?
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、6月号で最も興味を引いた記事は「自分らしさが原動力です」と「ダンボールコンポスト」であることがわかります。これらの記事は、幅広い年代で関心を集めており、特に地域の人々の活動や環境に関するテーマが注目されています。また、「田植え体験」や「唐招提寺『うちわまき』」など、地域の伝統や文化に関連する記事にも関心が寄せられています。これらの結果を踏まえ、今後も地域の特色を活かした記事が多くの読者の興味を引く可能性が高いと考えられます。
2.分かりにくい記事はありましたか?
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、多くの読者は特に分かりにくい記事はないと感じていますが、「地域の担い手確保」や「市長の対談」に関しては、内容の理解が難しいと感じる人が一定数います。また、「男女共同参画」の説明不足や、23ページの「ナバリノ」で紹介しているカフェの場所に関する情報不足についても指摘されています。これらの意見を踏まえ、特定の記事においては、より分かりやすい表現や詳細な情報提供が求められていると考えられます。今後の改善に向けて、読者が情報を容易に理解できるように工夫することが重要です。
3.今月のナバリストは、柴 吟子さんです。柴さんへ、メッセージをお願いします。
全体の傾向のまとめ
(AIを活用し、皆さんからのご意見をまとめました)
全体として、柴吟子さんへのメッセージには、応援や感謝の言葉が多く見られ、活動に対する高い評価と期待が寄せられています。多様性の時代における重要な取り組みとして、多くの人々が共感を示しており、今後も活動を続けてほしいという声が多くあります。また、具体的な提案や意見もあり、これらを活動に反映させることで、さらに多くの人々に支持されることが期待されます。