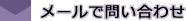【No.3】なばりん検定 解説編
更新日:2023年6月10日

名張と鮎
名張では、鵜飼漁が明治41年まで続いたそうですが、鵜匠が船上で鵜を操る長良川の鵜飼に対して、名張でみられた鵜飼は歩きながらの漁法でした。戦国武将の藤堂高虎も青蓮寺川で鮎の鵜飼漁をしていたと伝わっていますので、相当古い歴史があります。さらにさかのぼって、2000年以上前、伊勢神宮を創建したとされる倭やまとひめのみこと姫命が、天あまてらすおおみかみ照大神を祀るふさわしい場所を探す旅をして名張にも滞在した際、食膳に鮎を供したとも伝わります。
大正14年、下流の大河原(京都府相楽郡)に水力発電所が建設され、鮎の自然遡上ができなくなってからは、川に稚鮎が放流されていますが、コケを食べる鮎にとって、川の環境そのものが味を左右すると言われています。放流された鮎が立派に育つ美しい川を守っていくのは、現代を生きる私たちの努めです。…というわけで、「なばりん検定」【No.3】の答えは(1)の藤堂高虎でした!
「なばりん検定」に戻る