令和7年度教育行政の方針と施策について
更新日:2025年03年03日
はじめに
名張市議会令和7年3月定例議会の開会に当たり、令和7年度の教育行政の方針と施策を申し述べ、議員の皆様、市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
本市の教育振興基本計画である「第二次名張市子ども教育ビジョン」において、計画期間を平成28年度から令和7年度までの10年間とし、めざす教育、めざす子ども像の実現に向け、小中一貫教育及び名張版コミュニティ・スクールの推進・充実をはじめとした様々な施策を推進してまいりました。
令和7年度は、当該計画期間の最終年度であり、これまで継続してきた事業や施策のまとめの年となります。同計画に掲げる基本目標の達成を目指し、市長部局や関係機関と緊密に連携、協調しながら、教育施策を着実に推進し、市民の皆様の信頼と期待に応えるべく、本市教育の更なる充実に取り組んでまいります。
あわせて、令和7年度は、令和8年度以降の本市の新たな教育振興基本計画の策定に向けた準備の年にもなります。国や県の現教育振興基本計画におけるウェルビーイングの観点等を踏まえながら、これまでの取組の成果と課題の検証とともに、アンケートや意見交換による児童生徒の意見も反映しつつ、本市の教育理念の実現に向けた新たな計画策定に取り組んでまいります。
それでは、市総合計画「なばり新時代戦略」に定める施策ごとに、教育行政の方針と施策を申し述べます。
1.はぐくむ
《学校で元気な「ばりっ子」をはぐくみます》
(1)就学前教育
幼児教育と小学校教育との円滑な接続のために、経験豊富な退職教員「ピカ1先生」を、市内全ての幼稚園・保育所(園)・認定こども園に派遣し、5歳児を対象とした「ばりっ子ピカピカ小1学級体験プロジェクト」を実施し、小学校の授業を模擬体験できる機会等をつくり、小学校への見通しと期待感を持てるようにしてまいります。
また、小学校と幼児教育施設等が連携し、子どもたちの成長を切れ目なく支援するために小学校教員の研修の充実や、幼児教育アドバイザーによる継続的な巡回訪問、小学校と幼児教育施設の代表者等による連携会議を行うなど、「しっかりつなぐ育ちのバトンカリキュラム」に基づき、指導内容や指導方法について相互理解を図ることを通して、子どもたちが安心して小学校生活を始められるよう、庁内各部局や関係機関と連携しながら取組を進めてまいります。
(2)コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育
各学校において、学校運営協議会の運営等の活性化に努めるとともに、学校と地域が子どもを中心に据えて、目標やビジョンを共有し、互いに連携することで、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動が一体的に推進されるよう支援を行います。
また、令和6年度に策定した「名張市小中一貫教育推進方針」に基づき、市内各中学校区で「めざす子ども像」を共有し、義務教育9年間を見据えたカリキュラムを編成しながら、系統性・連続性を確保した小中一貫教育を行います。特に、小中学校間の段差を緩やかにするため、小学校高学年、中学年での教科担任制を充実させたり、乗り入れ授業等の小中学校間の教員の交流を積極的に行ったりするなど、子どもの発達段階に応じたきめ細やかな指導、支援を行ってまいります。さらに、小中学校の枠組みを越えて、互いの取組や実情を交流するなど、中学校区の学校と、家庭、地域とが互いに連携、協働しながら児童生徒の資質及び能力の向上に努めてまいります。
(3)特別支援教育
特別な支援を必要とする児童生徒の割合は、年々増加傾向にあります。個に応じた適切な支援をするために、全ての子どもに分かりやすく理解ができるよう、授業のユニバーサルデザイン化を進めるなど、個に応じた適切な支援を提供してまいります。また、早期からの一貫した指導と支援の充実を図るために、教職員への研修を充実するとともに、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、特別な支援を必要とする児童生徒の自立に向けた取組を推進してまいります。
また、名張市特別支援教育システムに基づき、関係機関との連携を図り、発達検査の実施をはじめ、福祉や医療、心理等の専門家等の講師を招へいし、児童生徒の状況を丁寧にアセスメントすることで、特別な支援を必要とする児童生徒への有効な支援に役立てていきます。加えて、幼稚園・保育所(園)から中学校まで、切れ目ない支援を行うために、保護者とも連携しながら、個別の教育支援計画や指導計画を有効活用し、支援の充実を図ってまいります。
(4)平和教育
令和6年度から本市の非核平和事業の一環として、戦争の悲惨さと平和の尊さを継承していく「なばりピースメッセンジャープロジェクト」を進めています。令和7年度も引き続き、市内各中学校からの代表生徒「ピースメッセンジャー」を募集し、平和を考える学習会や懇談会等を通して学びを深めていきます。また、生徒が取組を企画する機会を増やし、実践を重ねる中で平和を考え行動する主体者として自分事として受け止め、市民に向けて平和メッセージを発信していく活動を進めてまいります。さらに、市内小学校に講師を招いて、平和の尊さを伝える紙芝居を上演するとともに、市内中学校では、沖縄平和啓発プロモーション事業に応募することにより現地の語り部の派遣を行うなど、出前授業を実施してまいります。加えて、平和教育を学校で更に推進するために、外部講師の招へいやなばり学での取組を充実させるとともに、学習した内容を学校内外に発信し、平和の大切さを伝えてまいります。
(5)豊かな心の醸成
子どもたちの実態や発達の状況等に配慮しながら、自他を尊重し合い、生命を大切にし、いじめを許さない、相手を思いやる心を養う取組や、我が国の社会や文化に対する理解と愛情を深める取組、人との出会いを通じて自尊感情を高める取組など、教育活動全体を通じて人権教育や道徳教育、キャリア教育を推進してまいります。
また、近年増加傾向にある外国人児童生徒に対しては、安心して学校生活が送れるよう、丁寧に日本語指導や学習・生活支援を行います。
さらに、子どもたちが地域への関心を深め、伝統や文化を引き継ぐとともに、次世代の地域の担い手の育成につながるよう、ふるさと学習「なばり学」で、地域の方の思いや願いに触れる機会を設け、自然や農業等の体験活動も取り入れるなど、名張の自然や歴史、伝統・文化、人、産業・観光をテーマとした学習を推進してまいります。
加えて、豊かな心を育てる基盤として、子どもたちがたくましく生きるための健康と体をつくるとともに、子どもの実態に応じた健康教育やその基盤になる食に関する知識と食習慣、生活習慣が身に付くよう食育を推進してまいります。
(6)GIGAスクール構想実現による学習活動及び統合型校務支援システムの導入
令和7年度には、国が示すGIGAスクール構想第2期による本市の学習用端末の更新時期を迎えます。この端末の更新を着実に進めるとともに、標準仕様に含まれている汎用的なソフトウェアとクラウド環境を活用し、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。また、本市の授業におけるICT機器の活用状況は、小中学校ともに全国平均よりも高い水準にあります。引き続き、児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や、教職員のICT活用等の研修の充実により、学校における端末の一層効果的な活用を図ってまいります。
また、学校DXの具体的な計画や推進のために、名張市GIGAスクールアドバイザーを引き続き市内全ての小中学校に派遣してまいります。
さらに、国が推進する統合型校務支援システムの導入につきましては、現在、モデル校での実証や他市の状況の調査を行っており、セキュリティ対策を強化しながら準備を進めてまいります。
(7)不登校対策
「居心地のよい集団(学級)づくり」のために、個々の児童生徒の特性等を十分に理解し、それに応じた指導方法の工夫や、学校の実態に応じた指導体制の工夫改善により、「個や集団に応じた指導の充実」を図るなど、不登校、長期欠席者の未然防止に継続して取り組んでまいります。また、「学級満足度調査(Q-U調査)」等を有効に活用し、児童生徒一人ひとりを支援する取組を引き続き進めてまいります。さらに、丁寧な初期対応のため、市の「不登校対応マニュアル」や国の「生徒指導提要」等に基づき、学校が組織的に不登校の多様な要因や背景を適切にアセスメントして対応方針を決め、早期から家庭と連携して取り組んでまいります。今後も、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、地域福祉教育総合支援ネットワークエリアディレクター等とも積極的に連携しながら、チーム学校として組織的に取組を進めてまいります。
加えて、不登校傾向にある児童生徒や教室に入りにくい児童生徒に対して、地域や民間団体、外部機関の力を借りながら、校内教育支援センターをはじめとして、学校等における子どもの居場所づくりや学びの保障に努めてまいります。
また、教育支援センター(さくら教室)では、支援シートの活用により個々の支援の方向を明確にし、学校や保護者と連携しながら、学校生活への復帰あるいは社会的自立に向けた支援を行ってまいります。さらに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる訪問型支援も効果的に進めてまいります。
(8)教育センター機能の充実
令和6年度は、教育支援センター(さくら教室)において、スクールソーシャルワーカーによる訪問型支援、学校や保護者とのつながりを丁寧に築いてきたことにより、学校とさくら教室を併用する児童生徒が増えました。引き続き、教育よろず相談を窓口として、学校や保護者が抱える多様な課題に初期段階から適切に対応し、相談内容に応じて関係機関と連携を図りながら子どもの育ちを支援してまいります。
教員の指導力向上のための研修においては、教員の経験年数に応じた講座を設け、あわせて、授業改善、子ども理解、ICT活用等の研修内容を充実させていきます。加えて、教職員が子どもたちと向き合い、よりよい教育が遂行できるよう、それぞれの学校が抱える教育課題に対して、迅速に支援ができる体制を整えます。
一方、子どもの体験や学びの場としては、週末教育事業や親子で学ぼう「なばり学」教室の内容の充実や、市立図書館を活用したジュニア司書の育成や読書活動の推進を図ってまいります。
(9)安全で安心な教育環境の整備
学校施設は、児童生徒が日中の大部分を過ごす場であるため、安全で安心な施設であることが必要です。また、災害時の避難所としての機能を担っていますが、市内小中学校の約7割が、建築後40年以上経過しており、施設の給排水管や電気設備、屋上防水などの老朽化が進んでいることが大きな課題となっております。このことから、「名張市学校施設長寿命化計画」に基づき、財政負担の平準化を図りながら、長寿命化改修をはじめとした学校施設の老朽化対策を進めてまいります。
そして、学校現場の声を聞き取りながら、教職員が行う調査業務等の事務負担の軽減に努め、学校における働き方改革のための必要な取組を進めます。
また、児童生徒全員に安全安心で魅力的な学校給食を持続的に安定して提供するため、中学校給食の実施については、財政状況を踏まえた検討を行いながら、実施に向けた取組を進めてまいります。
2.つなぐ
《文化をはぐくみ、次世代につなぎます》
(1)市民文化の創造
「豊かな心と文化の息づくまちづくり」の更なる推進に向け、「名張市美術展覧会」や「名張市民文化祭」などを継続して開催します。また、芸術作品や工芸作品の展示を行う場として、名張藤堂家邸跡などの由緒ある建造物を若年層等に向けた作品展に活用するなど、幅広い層の市民に広く興味を持ってもらえるよう取組を進めます。
あわせて、舞台芸術の拠点であるadsホール(名張市青少年センター)については、指定管理者と連携し、自主事業等の実施を促進するほか、活用可能な助成金等を利用し、魅力的な文化ホールの運営を目指すとともに、令和8年度からの指定管理者の公募を見据え、舞台芸術のみならず多様な利用を可能とする等、幅広い層の市民の参画と市民文化の発展向上に資する新時代の文化ホールの在り方を検討してまいります。
(2)文化資源の保護と活用
令和6年11月には、安本亀八作の肖像彫刻6件を新たに名張市指定文化財に指定し、市内における国・県・市の指定文化財及び登録有形文化財は、合計120件となりました。郷土資料館、夏見廃寺展示館、名張藤堂家邸跡などの史跡や文化施設等を活用し、地域づくり組織や市民公益団体の協力も得て、企画展示や体験教室等、地域の活性化につながる取組を進め、郷土への愛着と誇りが醸成されるよう、本市の魅力の発信に努めてまいります。
また、特別天然記念物オオサンショウウオの保護事業を継続するとともに、交雑種問題を含めた環境学習や啓発活動に取り組みます。令和7年10月には、日本オオサンショウウオの会の全国大会を本市で開催することを踏まえ、地元の小学校や関係団体の協力を得ながらオオサンショウウオが生息する「清流のまち名張」を全国に情報発信してまいります。
さらに、令和7年は、昌福寺建立1300年という記念の年に当たることから、市内の関係団体とも連携し、夏見廃寺跡において市民への情報発信を目的とした記念事業の実施に向けて、取組を進めてまいります。
市史編さん事業については、市民の財産である本市の歴史・文化を後世に伝えるため、すでに発刊している資料編「考古」、「古代」に続く、「中世」、「民俗」の早期の刊行を目指し、編集委員会を開催するとともに、各部会における資料収集及び調査研究を更に進めてまいります。
(3)伝統文化の振興
能楽の大成者である観阿弥が小波田の地で座を興したとされるいわれに基づき、地域に根付く「能」をはじめとした伝統文化を守るとともに、若年層に伝えるべく「名張子ども狂言の会」などの地域の若年層で構成される団体を支援し「観阿弥祭」や「名張子ども伝統芸能祭り」等の事業を継続して実施してまいります。
また、華道や茶道といった和文化についても、文化施設での体験教室等を実施し、伝統的な文化に触れ、魅力を知るきっかけとなる取組を進めてまいります。
3.つくる
《青少年の健全な育成環境と生涯学習社会をつくります》
(1)子どもを核とした生涯学習ネットワークの構築
社会情勢が目まぐるしく変化し、科学技術の発展や、人々の生活様式の様変わり等によって、子どもたちの育ちを取り巻く環境も様々な影響を受けています。
そういった中で、家族はもちろんのこと、地域の方々や、学校の関係者、企業や団体といった多くの大人たちが子どもの育ちに関わることが重要であることから、地域全体で子どもたちの成長を支えるとともに、社会教育委員をはじめ、関係者の支援も得ながら、学校や子どもを核として地域づくりを目指す生涯学習ネットワークの構築を進めてまいります。
そのために、地域学校協働活動推進員を早期に配置し、地域と学校との情報共有を図るとともに、双方をつなぐ役割の担い手を明確にすることで、多様な連携が更に進むよう支援してまいります。
また、名張市青少年育成市民会議をはじめ、各種団体が主催する体験活動事業の支援を行うことで、社会教育の場で、子どもが学び、集い、つながり会う機会をつくります。そして、これらの事業に市民が参画することで、子どものみならず、大人も集い、活動する喜びを感じられる仕組みと体制づくりを行ってまいります。
(2)継続的な生涯学習機会の充実と整備
市民が、生涯を通じて学ぶことができる環境を整備し、充実した学びの機会を得られるよう、地域の生涯学習の拠点である市民センターとの連携を強化してまいります。
各市民センターの生涯学習リーダーで構成する生涯学習推進協議会を定期的に開催し、研修や、関係者同士の交流の場をつくります。
また、皇學館大学や近畿大学工業高等専門学校などの市と協力関係にある高等教育機関との連携による事業を行うことにより、幅広い学びの機会を提供します。
(3)青少年が安心して活動できる環境づくり
子どもたちが土日や休日を含む放課後等を安全安心に過ごし、多様な体験や活動ができるよう、地域住民等の参画を得ながら、「放課後子ども教室」の拡充を図ります。令和7年度においては、現在の8地域に加え、4地域での新規開設を目標に計画を進めてまいります。また、放課後児童クラブとの一体的推進による子どもたちの居場所づくりについても、それぞれの地域の実情を踏まえ、検討してまいります。
あわせて、青少年活動の支援や指導を行うジュニアリーダーの養成を継続し、その活動組織である名張Kidsサポータークラブが、充実した活動を行えるように、関係団体と連携し、取組を進めてまいります。
(4)青少年を守り、健全に育成する体制
近年、複雑化、潜在化、多様化する青少年を取り巻く諸課題に対処し、青少年の被害や非行問題の未然防止のためには、関係団体や機関同士の連携と協力が重要となります。「青少年補導センター」や「名張少年サポートふれあい隊」を中心として、関係者同士の情報交換や研修の場を設け、行政と地域、関係機関等による連携体制の維持を行うとともに、日々のパトロール業務や社会環境整備活動等を行うことで、引き続き青少年の健全育成に向けた環境づくりを進めてまいります。
あわせて、子どもを守る家事業をはじめとした、地域で子どもを守る取組を推進し、子どもに関わる関係機関が集まる「校外生活指導連絡協議会」や「関係機関打ち合わせ会」、「要保護児童対策及びDV対策地域協議会」等において、情報の交換、共有を行うことで、青少年の問題行動及び背景を知るとともに、状況に合わせた対応が速やかにできるよう、連携の強化を図ります。
(5)図書館サービスの充実
図書館は、子どもから高齢者まで、全ての年齢層の市民が身近な情報拠点として、また、自由に読書に親しめる場として重要な役割を担っています。そのため、利用者ニーズの的確な把握に努め、市民が必要とする図書館資料を適切に提供するとともに、図書館施設の環境整備など、サービスの向上と業務の効率化に向けて、改善を進めてまいります。
図書館を身近に感じていただく取組として、令和6年より、地域貢献団体とともに、血圧測定健康コーナーの設置や毎月の健康相談、交流会、クラフトイベントなど、図書館を活用した「図書館で健康プロジェクト」を行っており、今後も気軽に来館できる場所となるよう取組を進めてまいります。
また、いわゆる読書バリアフリー法の趣旨等を鑑み、図書資料等の音訳、点訳、デジタル化等を進め、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、読書を通じて文字・活字文化の恩恵を享受できる社会の実現を目指しています。あわせて、「第四次名張市子ども読書活動推進計画」に基づき、次世代の読書活動推進リーダーの育成として、ジュニア司書養成講座に取り組むなど、各学校図書館をはじめ、関係機関、団体、ボランティアなど多様な主体とも連携し、着実な計画の推進を図っています。
なお、令和7年度は、江戸川乱歩没後60年に当たることから、令和6年度の生誕130周年に引き続き、乱歩コーナーのPRや関連書籍の充実を図り、新たな企画展やイベントに取り組むとともに、市民団体と連携し、乱歩の顕彰を進めてまいります。
4.ととのえる
《生涯スポーツができる環境をととのえます》
(1)スポーツ・レクリエーション活動等の充実
子どもから高齢者まで幅広い世代の方がスポーツ・レクリエーション活動に親しみ、健康ではつらつとした暮らしを営むことができるような環境づくりのために、スポーツ関係団体や地域との連携を密にしながら、様々なイベントや体験教室等の開催や活動場所の提供等を通じ、生涯スポーツ社会の実現に向けた取組を推進します。
また、より身近で、誰もが様々なスポーツ活動を楽しむことを目的として、現在、市内では六つの総合型地域スポーツクラブが活動を行っています。引き続き、これらのクラブが持続可能な運営が行えるよう支援を行うとともに、新たな総合型地域スポーツクラブの設立に向けては、市民アンケートや地域ニーズを踏まえ、クラブ創設の機運向上を図りながら、支援を進めていきます。
(2)スポーツ活動を通じたまちづくり
スポーツによる地域活性化、まちづくりの推進を図るため、老朽化したスポーツ施設等については、安全安心に利用できるよう、指定管理者と連携し、施設の維持管理に努めます。あわせて、長寿命化を意識した計画の策定や、行財政改革プランに基づき受益者負担の見直しを行い、必要な改修、修繕を計画的に実施していきます。
市民プールをはじめとしたスポーツ施設等の今後の在り方については、厳しい財政状況を踏まえ、本市の公共施設全体の整備の方向性も視野に入れて検討します。
また、引き続き、「ホッケーのまち なばり」の取組の推進とともに、指定管理者、関係協会及び関係部署と連携を図りながら、スポーツツーリズムにつながる取組により地域の更なる活性化を進めていきます。
(3)第2次名張市スポーツ推進計画の策定
令和7年度末で現在の「名張市スポーツ推進計画」の計画期間が満了することから、これまでの取組の成果と課題を検証し、令和6年11月末から実施したスポーツに関する市民アンケートや、国・県の動向を踏まえながら、名張市スポーツ推進審議会等を通じて、第2次名張市スポーツ推進計画の策定に向けて取り組んでまいります。
《おわりに》
今後も皆様の参画を得て、未来を担う子どもの教育環境の向上を目指した教育行政を教育委員会及び事務局職員が一丸となって推進してまいります。皆様の一層のご支援とご協力をお願いし、令和7年度の教育行政の方針と施策とさせていただきます。

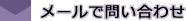
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。