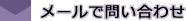児童扶養手当
更新日:2025年05年09日
児童扶養手当を受給するには
児童扶養手当の制度
父母の離婚などにより、児童を養育している母子家庭や父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給できる方
児童扶養手当は、以下のいずれかにあてはまる児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)を監護している母、児童を監護し生計が同一である父、または父母以外で児童を養育している人が受給できます。
なお、児童が身体または精神に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
また、請求者または扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)の前年度所得が一定額以上の場合、全部または一部の手当が停止されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘束されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
注:他の公的年金を受け取ることができるときでも、児童扶養手当の手当額の方が高い場合は差額を受けることができます。
手当の額 (令和7年4月改定)
◎全部支給 月額 46,690円
児童が2人以上の場合は、2人目以降の児童1人につき11,030円を加算
◎一部支給 所得に応じて、月額 46,680円から11,010円
児童が2人以上の場合は、2人目以降の児童1人につき所得に応じて11,020円から5,520円を加算
注:支給は5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回
(各月とも11日、11日が土・日・祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)支給されます。
<参考>
消費者物価指数の変動に伴い、児童扶養手当の額が令和7年4月分から、 下記のとおり改定されました。
| 【改正前】 令和7年3月分まで | 【改正後】 令和7年4月分から | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全部支給の方 | 一部支給の方 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
| 手当月額 第1子 |
45,500円 | 所得に応じて、 45,490円から10,740円までの 10円単位の額 |
46,690円 | 所得に応じて、 46,680円から11,010円までの 10円単位の額 |
| 手当月額 第2子以降 |
10,750円 | 所得に応じて、 10,740円から5,380円までの 10円単位の額 |
11,030円 | 所得に応じて、 11,020円から5,520円までの 10円単位の額 |
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者の所得制限限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人以上 | 1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
注:請求者が父または母の場合、児童の母または父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に加算されます。
手続方法
児童扶養手当を受けるには、認定請求書に以下の書類を添えて申請してください。
- 請求者の離婚日が確認できる戸籍謄本
- 子の戸籍謄本(請求者と同じ戸籍の場合は不要)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 申請者名義(氏変更後)の預金通帳
- 借家の賃貸契約書(原本)
- 本人が確認できる書類
- 本人・子・扶養義務者の個人番号確認書類
注:必要に応じて、この他にも書類を提出していただく事があります。
受給の留意点
受給開始後は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出し、支給要件の審査を受けることが必要
です。この届出がないと、11月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出がない場合は受給資格を失いますので、ご注意ください。
また、手当を受けている父または母が婚姻した(内縁関係等も含む)等の事由により、受給資格がなくなった場合は直ちに届け出てください。偽りの申告を行ったり、必要な届出を行わないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、手当の全額を返還いただくほか、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
公的年金を受けている場合でも児童扶養手当を受けることができる場合があります!
平成26年12月1日に児童扶養手当法が一部改正されました。
受給資格者または対象児童が公的年金給付等を受給できる場合
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
今回の改正により新たに受給できる方
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
申請について
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
対象児童が障害基礎年金の子の加算の対象となっている場合
児童扶養手当受給資格者の配偶者が障害基礎年金を受給している場合で、児童がその加算対象となっているとき、子の加算額が当該児童にかかる手当額を下回る場合には、その差額分について児童扶養手当を受給できます。
一部支給停止措置について
手当を受給して5年または手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要な書類を添えて提出すれば支給停止されません。対象者には通知し、現況届提出時に毎年手続が必要となります。