「ひまわり」掲載記事一覧(2023年分)
更新日:2023年12月13日
「ひまわり」掲載記事一覧(2023年分)
※各リンクを押すと、記事へジャンプします。| 1月号 | 「ヘイトスピーチ」 |
| 2月号 | 「節分に思う」 |
| 3月号 | 「スポーツと多様性」 |
| 4月号 | 「まあいいか」 |
| 5月号 | 「病気・見た目」 |
| 6月号 | 「応援したい!男性育休(育児休業)」 |
| 7月号 | 「自分らしさ」 |
| 8月号 | 「マオリとアイヌ」 |
| 9月号 | 「慣習と文化」 |
| 10月号 | 「『気にせんよ』じゃあ、ない!」 |
| 11月号 | 「自分のものさし」 |
| 12月号 | 「『とびら』」 |
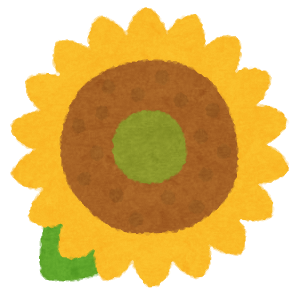
2023(令和5年)
1月号:「ヘイトスピーチ」
コロナ禍が始まって約3年。その間、衝撃的なニュースがありました。
2020年9月、日本人のジャズピアニストが、アメリカのニューヨークで8人組の暴漢に襲われ、右腕などを骨折するなど重傷を負いました。暴行中には「チャイニーズ(中国人)」や「エイジアン(アジア人)」という言葉が飛び交っていたそうです。
人種間での分断が、大きな社会問題となっているアメリカ。特に、アジア系住民に対する偏見や差別はこのコロナ禍で増幅され、罪のない人々が犯罪の標的とされてしまっています。
「もし自分が外国にいて、何の理由もなく急に暴言を吐かれたり殴られたりしたら…」
想像もしたくないことですが、これは遠くの外国だけで起こっている問題なのでしょうか。
昨年、ロシアがウクライナに侵攻を始めてから、日本でも同様に、日本に住む罪なきロシア人やそうみなされた人たちが被害にあっています。経営するお店に無言電話が繰り返されたり、看板が壊されたり、SNS上には「出ていけ」「自分の国を恥ずべき」などの誹謗中傷が書き込まれたりしました。身近にいるロシア人と軍事侵攻の責任者を一緒くたにしてはいけません。
こういうニュースに接するたびに私は、なぜこういったヘイトスピーチは起こってしまうのかと情けなく感じ、人の行動や心理などについて調べてみたところ、『異質なものを排除しよう』とする心理が関係していることがわかりました。
『特定の民族を排除しよう』とする言動は以前からも問題となっていました。そこで2016年には、国籍・人種・民族等を理由とした排他的言動を許さないために、「ヘイトスピーチ解消法」が制定されました。
多様性のある社会の実現を目指す名張市では、現在千人を超える外国人が生活しています。人種などでくくるのではなく、「その人」自身を見て、他者との違いを認め合える自分や社会でありたいと願います。そのためには簡単なようで難しい、『その人をありのままに受け入れること』から始めていきたいと思っています。
2月号:「節分に思う」
みなさんは「節分」と聞いて何がを思い浮かべますか。
節分の日、スーパーの食品売り場が「恵方巻」を求める人でにぎわうように、最近では「節分と言えば恵方巻」が定着しているようですが、やはり「鬼は外、福は内」の豆まきが断トツではないでしょうか。
豆をまいて、玄関先には割りばしに鬼が大嫌いなヒイラギの小枝をくくり付け、これまた鬼が嫌がる焼いたイワシの頭を突き刺したものを飾ります。我が家ではこれを「イタイクサイ(痛い臭い)」と呼んでいました。
ところで「鬼は外」と追い払われる「鬼」とは何でしょうか。
鬼と言えば、頭には牛の角、口は横に裂け鋭い牙、指には鋭い爪、裸にトラ皮の腰布というイメージですが、鬼の語源については「隠(おぬ)」がなまったものだという説があります。「隠」は「なばり」にもつながるだけに親近感を感じますが、もともと、鬼とは隠れていて私たちの目には見えないもの、この世ならざるものということなのかもしれません。
そこから人の力を超えたもの、さらに私たちにとって悪いものが鬼とされたようです。
具体的にはどんなことを言うのでしょう。
まず、思い浮かぶのは、病気、事故、自然災害などの「災い」です。さらには、私たち人間の内にあるもの、心の中に潜む怒り、嫉妬心、憎しみ、欲望、怨みといった感情、つまり「心の鬼」です。
節分は、こうした災いが入り込まないように豆をまき、私たちの心の鬼を追い出すために豆をまきます。
心の鬼は普段は自制心によって抑えられていますが、ふとした拍子に顔を出します。偏見や差別を生み出すのも心の鬼の仕業と言えます。でも、心の鬼を追い出すのは簡単なことではありません。
節分を機に自分の心の中に潜んでいる鬼と向き合い、豆をまきたいものです。年に一度ではなく、できれば毎日。
3月号:「スポーツと多様性」
今年も春の選抜高校野球の季節が近づいてきました。努力の成果をぶつけ合う球児たち。そんな球児たちを後押しする監督やマネージャー、学校や地域の応援団。甲子園に立つまでには様々な経緯があり、学校紹介の時にはいつも感動を覚えます。
昨年、夏の甲子園のニュースを聞く中で、女子の高校野球大会もあることを知りました。26回を迎えた女子高校野球の全国大会。これまで開催日程の都合もあったのかもしれませんが、女子の全国大会の試合が甲子園で行われることはありませんでした。
しかし一昨年と昨年、決勝戦だけでしたが甲子園で試合が行われました。
以前は、女子が甲子園のグラウンドに立つことさえも禁止されていました。1996年に女子マネージャーのベンチ入りが認められた後も、グラウンドでノックの補助をしていて、ベンチに下げられたことがありました。「ボールが当たったら危険だから」という理由だったようですが、当時、話題になったことを覚えています。昨年からは女子マネージャーのグラウンド入りも認められ、女子高校野球と同様に甲子園が徐々に女性も活躍する場として開かれてきているなと感じました。
甲子園だけに限らず相撲の土俵や入山を禁止している場所など、女性ということだけで制限されている現実があります。これらの理由として、それぞれの伝統に縛られた女性観があるのかも知れません。しかし、多様性を認め合うことの大切さが言われている今、この現実にいつまでもとらわれていていいのでしょうか。
2021年に開催された東京オリンピックでは、「オリンピックアジェンダ2020」によって男女平等が推進されました。オリンピック憲章では、「いかなる差別もしない」が基本原則となっており、今や世界のスポーツ界では、ジェンダーイクオリティ(男女平等)は当たり前となっています。
多様性を認め合える社会の確立の一歩として、男女も含め多様な人々がともに楽しめるスポーツの大会のあり方を考えなければならないのではないでしょうか。
4月号:「まあいいか」
ある日、高校生の娘が私に言い出しました。
「なあなあ、小さい時に、お母さんいつも言ってたよな。『自分が言われて嫌なことは、お友だちにも言わんとき』って」
「そやな、よく言ってたな。お母さんも、おばあちゃんにいつも言われてたからなあ」
「でもさ、人によって受け止め方って違うよな」
学校で友だちと行き違いがあった娘は、「そんなつもりじゃなかった」と伝えて仲直りできたようです。
「『書いた手紙は、渡さへんだら相手には伝わらへんけど、言った言葉は取り消せへんから、考えてしゃべらなあかんで』とも、お母さんにはよく言われたよな。でも、これも、めっちゃ難しくない?」
確かにそうです。日常会話でいつも考えてから話すのはとても難しいことです。私も娘のように「そんなつもりじゃなかった」と伝えられたこともあれば、思いが伝わらなかったこともあります。そのたびに「もっと考えてから話せばよかった」と後悔します。逆に人の言葉で引っかかったこともあります。
大柄な人に向かって、友人が笑いながら「それだけでたりるの?」と言っていました。
言われた人は「いつもこれくらいやで」と笑っていました。本当に気にしていなかったのかどうか…。
私は「大柄だからってたくさん食べるわけじゃないやん」と思ったけれど何も言えませんでした。はっきり言うと、友人との関係が悪くなると思ってしまったからです。
同じ言葉を聞いても、受け取り方は人それぞれです。だからこそ、相手のことを考えた言葉を使うようにしたいです。「仲が良いだけに言いにくい」「まあいいか」と他人事にせず「こうしたほうがいいと思うな」と伝えられる人間関係を普段からつくりたいです。「自分だったらどうするか」と考えて行動する自分でいるために。
5月号:「病気・見た目」
この間、友人とこんな会話がありました。
「ウィル・スミスが舞台上で平手打ちした事件があったよね。暴力は絶対いけないんだけど…」
これは2022年3月に開催されたアカデミー賞授賞式で、俳優のウィル・スミスがプレゼンターのクリス・ロックを平手打ちした事件。クリスが、ウィルの妻であるジェイダの坊主頭をジョークのネタにしたのが原因でしたが、彼はジェイダが脱毛症であることを知らなかったそうです。
私の友人がウィル・スミスをかばうのには理由がありました。
「僕も見た目でわかってしまう病気を持ってるから、ウィルに同情してしまうなぁ」
彼は「乾癬(かんせん)」という病気に長年悩んでいると、以前打ち明けてくれました。免疫系の異常によって皮膚に炎症が生じる慢性の疾患で、「かんせん」という病名から「人から人へうつる」と誤解されやすいのですが、他人に感染する病気ではありません。誤解されるのが嫌で、彼はなるべく病名を言わないようにしているそうです。
その病気や、「見た目」に関してネットで調べているうちに、YouTubeである動画を見つけました。その動画は、「道化師様(どうけしよう)魚鱗癬(ぎょりんせん)」という30万人に1人の皮膚の難病と闘う、三重県在住の男の子と両親の日常を伝え、その難病について理解を深めることができる内容の動画でした。
ところがある事件が起こりました。「化け物だ!」などと、その子の容姿を誹謗中傷する文章を執拗に投稿したとして、名誉棄損で容疑者が逮捕されたのです。
病気と闘うだけでも大変なのに、からかわれたり誤解されたりする。そんなことは決してあってはならないはずです。私は友人が言ったあることばを今でも覚えています。「誰もなりたくて病気になってるんじゃないんだよ。」
現実を受け止めながら必死に生きている人が報われる世の中であることを願いながら、決して差別することなく、これからも大事な友人として接していこうと思います。
6月号:「応援したい!男性育休(育児休業)」
「育休取って一年も何すんの?」
これは、ある男性が育休取得の手続きを進めている時に、職場で多くの人から投げかけられた質問だそうです。
質問を投げかけてくるのは多くが男性で、決して悪気があってのことではないのはわかるのですが、みんな少し不思議そうな表情で話しかけてきたのだそうです。
私はこの話を聞いて、二十数年前、制度はあったものの男性の育休取得がまったく現実的でなかった当時、家事と育児に明け暮れた日々を思い出しました。
「何言うてんの?育休やで!育児に決まってるやん!」あるいは「そんなことを言ってるから男性の育休取得が進まんのよ!」と、男性の育児に対する意識の実態を垣間見たように感じました。
男性読者のみなさん、もしあなたがこの質問を受けたとしたらどうですか?「せやな~、何しよかな?」はないですよね。
育児休業法は1992(平成4)年に施行されました。そして、令和3年度の政府の調査によると、女性の育休取得率は85.1%、男性は14.0%になりました。けれど、その男性取得者の半数以上が育休期間2週間未満と短く、残念でなりません。
なぜこんなに男性の育休取得水準が低いのでしょう。やはり『育児は女性がするもの』という世間の思い込みが原因の一つでしょう。また、政府の調査では「収入を減らしたくなかった」(41.4%)が育休を取得しなかった最も多い理由ですが、その裏で約4割の女性が妊娠・出産を機に退職したり、元々無職であったりと仕事に就いていない現実もあります。
3月に政府は、育休中の給付金を給料の手取り同等額とすることなどを表明しました。これを機に男性も女性も同じように育休を取得することが当たり前になり、なにより子どもがたくさん愛されて、家族みんなが幸せを感じながら子育てできるような世の中になってほしいと思います。
そして、子育て世代と共生する私たちがするべきことは、「安心してゆっくり子育てしてね」と寄り添う環境づくり、そして精いっぱいの応援です。
7月号:「自分らしさ」
先日久しぶりに友人と会いました。彼女の子どもが、来年中学生になると聞き、あれこれ話に花が咲きました。
「知ってる?今って中学生の制服もブレザーが増えてきててさ、娘の行く中学校、スカートでもズボンでも自由に選べるんやで」
「そうなんや。ブレザーの学校が増えてるのは、スカートにもズボンにも合わせられるからなんや」
家に帰った私は、家族にその話をしました。娘が通っていた中学校も、娘が卒業した後に制服がブレザーに変わりました。娘は、「私は何となく『スカートよりズボンの方が楽やな』って感じやったけど、友だちの中ですごくスカートを嫌がっていて、制服のない高校へ進学した子がいたわ。中学校の3年間つらかったんやろな」と話しました。
性別に関係なく制服を選べる学校が、2010年代後半から全国的に増加しています。「ジェンダーレス制服」と呼ぶのだそうです。
文部科学省が2015年に性的少数者に対する配慮を学校で行うよう通知したことも背景にあるようです。
トランスジェンダーの生徒の精神的負担をなくすことはもちろんですが、一人一人が自分に合った制服を選べること、「何を選んでも大丈夫」という安心できる環境づくりが、ジェンダーレス制服導入の最大の目的だということです。
「男子はこちら、女子はこちら」と強制的に振り分けられるのではなく、人の数だけある「自分らしさ」を表現できるかどうかは、周りの環境による部分が大きいと思います。
自分がマジョリティ(多数派)に属していると、周囲にも自分と同じ考えの人が多いため、マイノリティ(少数派)の考えに気づきにくかったり、気づいても受け止められずに排除したりしがちではないでしょうか。でも、自分にとっての当たり前が、他の人の当たり前とは限りません。
一人一人の当たり前を尊重し、認め合うこと、「自分らしさ」を存分に発揮できることの大切さを、ジェンダーレス制服を通して考えました。
8月号:「マオリとアイヌ」
8月9日は国連が定めた「世界の先住民の国際デー」です。先住民の権利の推進と保護を支持し、直面させられている課題への取組支援を訴えています。私は「先住民」と聞くと、以前滞在したニュージーランドを思い出します。
現地に向かう飛行機に乗り込む際に、CAさんがかけてくれた「キアオラ」という言葉は、ニュージーランド先住民族「マオリ」が話すマオリ語のあいさつで、英語のハローにあたります。「キアオラ」は日常会話でもごく普通に使われ、テレビのニュース番組も「キアオラ!」で始まります。
また、ラグビーの国際試合前にニュージーランド代表が披露するマオリの伝統的な「ハカ」の踊りが有名ですが、国歌斉唱はマオリ語で始まり英語へと続きます。1987年にマオリ語は英語と並んで国の公用語とされているのです。
ある日、現地でできたマオリの友だちに「マオリと日本のアイヌの歴史には共通点がたくさんあるんだよ、知ってた?」と聞かれ、日本のことなのに全く知らなかった自分がとてもはずかしく感じられました。
マオリとアイヌについて調べてみると、どちらの民族も国による同化政策で自らの言語や文化、価値観、誇りといった民族のアイデンティティが消滅の危機に瀕したことがわかりました。そんな中、マオリ語が公用語と認められるまでに復権したことは一つの大きな成功例です。アイヌの人々がマオリとの交流を通じて、そうした取組の経過などを学ぼうとしていることなども知りました。
でも今も、マオリもアイヌも偏見や差別に苦しんでいる現実があります。多くの人が、私のように歴史や現状を知らなかったがゆえに、差別する側になってしまっているのではと感じました。
三重県はアイヌにゆかりの深い松阪出身の探検家で「北海道の名付け親」松浦武四郎を生み出しています。彼は出会ったアイヌ民族やその文化を守るため、まずは正しく知って理解してもらおうと、生涯、熱心にアイヌの紹介を行い、その保護を訴えました。武四郎の姿勢を見習い、まずは「知る」そして「知らせる」ことから始めたいと思います。
9月号:「慣習と文化」
「塩」は、料理だけではなく、慣習や伝統などでも、私たちの生活に深くかかわっています。葬儀の時の「清め塩」や、小皿に盛って玄関などに置く「盛り塩」などです。また、大相撲の取組前に力士によって塩がまかれることもよく知られています。いずれも、「邪気を払い清めるため」に続けられてきたものです。
今から5年前の4月、京都府で行われた大相撲舞鶴場所で、当時の市長が土俵上での挨拶中に倒れました。場内が騒然とする中、複数の女性が土俵に駆け上がり救命処置を行いました。彼女たちは看護師で、倒れた市長の様子から一刻も早い救命処置の必要性を感じての行動でした。
しかしその女性たちに対し、相撲協会の職員は「女性の方は土俵から降りてください」「男性がおあがりください」と場内アナウンスを行いました。さらに、市長が救急車で搬送され、ひと段落ついた土俵上では、相撲協会関係者によって大量の塩がまかれました。
この塩をまく光景に「女性が土俵に上がったため」なのか「土俵で急病人の発生という事態が生じた」ためなのか、その理由が社会の関心を集めました。
こうした一連の出来事に対し、相撲協会は、「動転して呼びかけたものでしたが、人命にかかわる状況には不適切な対応でした」と謝罪しました。また塩をまいたことについては、力士に大きなけががあった時の安全祈願のためで、女性が土俵に上がったことは関係ないとしています。
清めのための塩といえば、近年、葬儀の際の「清め塩」を見かけなくなってきています。仏教では生と死を一つの世界としてとらえているため、「死」を清めの対象とすべきではないとの考えからです。
慣習や文化を守っていくことは大切なことです。しかし、人の価値観をゆがめたり、尊厳を傷つけたりするような慣習や文化のあり方については、見直していく必要があるのではないでしょうか。
10月号:「『気にせんよ』じゃあ、ない!」
私は23年前、三重県内に越して来ました。あと一週間ほどで引っ越しというころ、雑談していた知人から、「今度の引っ越し先って被差別部落なんだろ」とたずねられました。私にとってはまったく寝耳に水の話だったのですが、「ふーん、そうなん?でも、別に気にせんよ」と答えました。実際気にもしていませんでしたし、「今どき部落差別なんて、何言ってるんだ」という思いもあったからです。その時は・・・。
でも、実際に新しい住まいでの生活が始まりしばらくしたころ、私はあることに違和感を覚えます。自分の住所を書くこと、口にすることをためらう私がそこにいたのです。当時、私の自己紹介は、「こちらに越してきました」で始まりました。この被差別部落の生まれではないことを強調していたのです。
なぜ?被差別部落の人間と思われて、部落差別の対象にされたくないという一心だったのです。
被差別部落の人間かどうかは、その人がそこに生まれたかどうかだけではなく、今、そこに住んでいるか、以前、住んだことがあるか、両親はどうか、祖父母はどうかなど、さまざまな「基準」によって「認識・認定」されます。これは多くの意識調査でも明らかになっています。いくら「引っ越してきた」といったところで、被差別部落出身の人間とみなされれば差別の対象になり得るのが部落差別です。
あの時の知人への、「別に気にせんよ」という私の一言は、「部落差別なんて部落出身でない自分には関係ない、そんなこと気にもならない」という、部落差別の存在を知りながら、それを傍観(容認)することに何も感じないという差別心そのものだったのです。
この気付きは私にとって大きな転機になりました。部落差別を関係ないと言いながら、自らに関わると思えばいとも簡単に差別する側に立つ、そんな差別心を持った自分自身を見せつけられた私。「それでいいのか?どう克服するのか?」を自らに問い、生き方につなげることの大切さを考えさせられました。
人と人の関係で成り立っている社会。その一員である私たちにとって「別に関係ない、別に気にしなくてよいこと」なんて、実は存在しないのではないでしょうか。
11月号:「自分のものさし」
先日、友人とおしゃべりしていると、「この前、子どもの計算ドリル見てたらな、ふとこんなこと思ってん」と、言いだしました。
「『公園でこどもが20人遊んでいます。女の子は7人です。男の子はなん人でしょう』って問題なんやけどな」
「13人やろ?」
「そう思うやろ?うちもそう思っててん。でもな、もしな、LGBTQの子がその中にいたら『ぼく(私)はどっちにはいるんかな。男と女しかないんかな』『なんでそうなるん』ってならへんかなぁって感じてん」
それを聞いて、私はハッとしました。この問題の正解は13人です。でも、自分の性別に違和感を持つ人にとっては、「ぼく(私)はどうなってるの?」とならないだろうか。意図的ではないにしろ、少数者のことが視野に入れられていないことにならないだろうか。
そう考えた時、学生の頃のこんな光景がよみがえってきました。
アニメ好きの女の子の友人が自分のことを「おれ」と言っていました。私はアニメの影響だと思い「『わたし』やろ」と笑って言いました。
彼女は何も言わずその後も「おれ」と言っていました。彼女から「おれ」の理由を聞いたことはありません。でも、「『わたし』やろ」の一言に彼女の表情はかすかにこわばっていたように感じました。この話題は、後にも先にもこの一回きりでした。もしかしたら、彼女は自分の性に違和感を持っていたのかも知れません。
私は、女の子が自分のことを「わたし」と言うのが「普通」だと思っていました。社会では大多数がそうだからです。でも、大多数がそうだからと言って、そのことがすべての人にとっての「普通」であるとは限りません。
「自分の当たり前のものさしがみんなと同じだと考えていたこと」で、これまで私は、知らず知らずのうちに周りの人を傷つけてきたのではないかと考えました。
たくさんの人に出会うことで、「自分にとっての当たり前という目盛り」ではなく、「いろんな人のいろんな目盛り」に気づける自分になっていきたいと思います。
12月号:「『とびら』」
腰痛に苦しみ、2年あまりの間に3度の手術を経験しました。特に最後の手術前の半年間は、足腰の痛みとしびれで、杖が手放せなくなっていました。現在も通院中ですが、何とか杖を手放せるところまで回復しました。
この腰痛との「つきあい」の日々の中で気付いたことがあります。
それまで私は「社会には『障害者』と『健常者』がいる」と漠然と考えていました。
ところが「健常者」として「障害者」のことを考えるという立場にいた私が、杖が手放せなくなりました。当たり前にできていたことが、「困難になる」「できなくなる」という日常が続きました。
そんな中、私に芽生えたのが、「社会には『障害者』と『障害者になる可能性のある人』がいるんだ」という思いでした。
もちろん、「身体的な困難を体験して、障害者問題を自分事として受け止めることができた」とまで言うことはできません。私の体験した困難は一時的なもので、障害者が直面する状況とは根本的に違うものだと思います。
でも、「自分にも起こりうる問題だ」と実感できたことは確かです。今なら、当事者が置かれた状況や思いに、私なりの実感を重ねつつ、思いを巡らせることができると思います。
さらに、その思いを様々な人権問題にも広げることができるのではないかとも感じます。
自分にとっての「人権のとびら」を見つけることで、人権問題全般が実感を伴って、自分の日常に近づくのではないかと思います。
大上段に振りかぶって「人権とは?」でなくても、「これから高齢者になる自分」「かつて子どもだった自分」「松葉杖生活を経験した自分」「外科医と聞いて男性が浮かんだ自分」「外国で右往左往した自分」「ネット情報に振り回された自分」「出勤前、『本日の占いコーナー』に一喜一憂する自分」などなど・・・
自分の日常をちょっと違った視点から見つめることで、それまで気付かなかった「人権のとびら」が、「ここにある」「あそこにもあった」ときっと見つかると思います。
見つかった「人権のとびら」、開けてみませんか?
関連ファイル
- 2023年1月号掲載ひまわり「ヘイトスピーチ」(PDF:543KB)
- 2023年2月号掲載ひまわり「節分に思う」(PDF:587KB)
- 2023年3月号掲載ひまわり「スポーツと多様性」(PDF:314KB)
- 2023年4月号掲載ひまわり「まあいいか」(PDF:676KB)
- 2023年5月号掲載ひまわり「病気・見た目」(PDF:570KB)
- 2023年6月号掲載ひまわり「応援したい!男性育休(育児休業)」(PDF:1,009KB)
- 2023年7月号掲載ひまわり「自分らしさ」(PDF:509KB)
- 2023年8月号掲載ひまわり「マオリとアイヌ」(PDF:564KB)
- 2023年9月号掲載ひまわり「慣習と文化」(PDF:561KB)
- 2023年10月号掲載ひまわり「『気にせんよ』じゃあ、ない!」(PDF:628KB)
- 2023年11月号掲載ひまわり「自分のものさし」(PDF:514KB)
- 2023年12月号掲載ひまわり「『とびら』」(PDF:1,007KB)

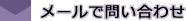
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。