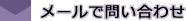城下町の横顔
更新日:2015年3月26日
戦国の世は去り時代は徳川の治世へと移っていた慶長13年(1608)、それまで伊賀国領主であった筒井氏は転封となり、代わって伊予国から藤堂高虎が伊勢・伊賀国領主として入封となりました。
そして、ようやく名張の地に藤堂高吉が転封してきたのは寛永12年(1635)のこと。高虎入封から27年の歳月が流れていました。以来、明治4年の廃藩置県まで、実に260年余り、11代にわたり名張藤堂家がこの地に西方の守りとして居を構えていました。
そして、ようやく名張の地に藤堂高吉が転封してきたのは寛永12年(1635)のこと。高虎入封から27年の歳月が流れていました。以来、明治4年の廃藩置県まで、実に260年余り、11代にわたり名張藤堂家がこの地に西方の守りとして居を構えていました。

太鼓門(県文化財)

名張藤堂家邸中奥
筒井氏時代の松倉氏や高虎時代の梅原氏などの施政により、まちが形成されつつあった名張に伊予国から転封してきた藤堂高吉は、すぐに松倉・梅原両氏が居館を構えていた狭間(現丸之内)の高台に殿館を築き、市街地を区画して伊予から連れてきた家臣や職人・商人の居住地を定め、本格的な城下町の形成に着手しました。
以来、南伊賀の中心都市として発展してきた名張には、現在でも風情あるまち並や名張藤堂家邸跡をはじめ、多くの文化財や祭り、伝統産業、食べ物など城下町の歴史をとどめる文物が残されています。
城下町名張を語る上で欠くことが出来ないのが、名張藤堂家邸跡(県文化財)。
現在残されている屋敷は、宝永7年(1710)の名張大火で消失した後に再建された殿館の一部で、「中奥」「祝間」「圍」などの私的な生活を送る建物です。
「名張藤堂家旧邸図(市文化財)」によると現在残されている屋敷は、全体の約20分の1ほどで、かつては名張小学校の敷地をも含めた広大なものだったようです。この屋敷とともに、「豊臣秀吉朱印状(市文化財)」「鉄唐冠形兜・一の谷形兜(市文化財)」「朱具足(市文化財)」「備前無銘刀(市文化財)」「藤堂高吉公一代記(市文化財)」「羽柴(豊臣)秀吉・丹羽長秀の書簡(市文化財)」など学術的にも貴重な文化財が、平成3年に名張藤堂家から市に寄贈されており、平成4年に保存修理事業が完了した屋敷とともに一般公開されています。
以来、南伊賀の中心都市として発展してきた名張には、現在でも風情あるまち並や名張藤堂家邸跡をはじめ、多くの文化財や祭り、伝統産業、食べ物など城下町の歴史をとどめる文物が残されています。
城下町名張を語る上で欠くことが出来ないのが、名張藤堂家邸跡(県文化財)。
現在残されている屋敷は、宝永7年(1710)の名張大火で消失した後に再建された殿館の一部で、「中奥」「祝間」「圍」などの私的な生活を送る建物です。
「名張藤堂家旧邸図(市文化財)」によると現在残されている屋敷は、全体の約20分の1ほどで、かつては名張小学校の敷地をも含めた広大なものだったようです。この屋敷とともに、「豊臣秀吉朱印状(市文化財)」「鉄唐冠形兜・一の谷形兜(市文化財)」「朱具足(市文化財)」「備前無銘刀(市文化財)」「藤堂高吉公一代記(市文化財)」「羽柴(豊臣)秀吉・丹羽長秀の書簡(市文化財)」など学術的にも貴重な文化財が、平成3年に名張藤堂家から市に寄贈されており、平成4年に保存修理事業が完了した屋敷とともに一般公開されています。